「またあの人、休んでる…」。職場で誰かが頻繁に休むと、ついそんな風に思ってしまうことはありませんか? よく休む人が信用出来ないと感じてしまうのは、あなただけではないかもしれません。仕事のしわ寄せや、コミュニケーション不足から生まれる不信感。
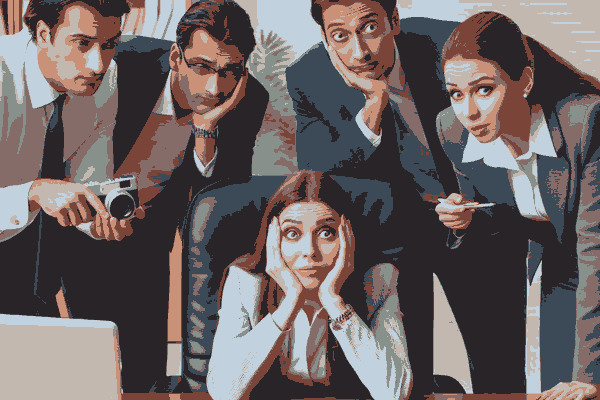
この記事では、なぜそう感じてしまうのか、その心理的な背景を探りつつ、職場の誤解を解き、より良い関係性を築くための具体的なヒントを分かりやすく解説していきます。
- なぜ「よく休む人は信用出来ない」と感じてしまうのか?その心理と仕事への影響
- よく休む人が信用出来ない…仕事のしわ寄せ問題と職場の誤解を解消するには
なぜ「よく休む人は信用出来ない」と感じてしまうのか?その心理と仕事への影響
職場で誰かが頻繁に休むと、周囲の人はさまざまな感情を抱くものです。「またか」という諦めにも似た気持ちや、業務の負担増に対する不満、そして時には「信用できない」という強い感情に至ることもあります。では、なぜ私たちは「よく休む人」に対して、そのようなネガティブな印象を抱いてしまうのでしょうか。
そこには、個人の心理状態だけでなく、職場環境や仕事の進め方など、さまざまな要因が複雑に絡み合っています。この項目では、その心理的な背景や、休みが多いことが仕事や周囲にどのような影響を与えるのかを掘り下げていきます。
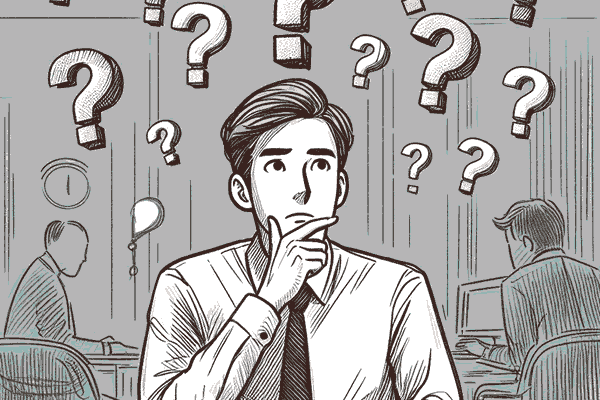
「よく休む人は信用出来ない」と感じる一般的な理由とは?
人が誰かに対して「信用できない」と感じる背景には、多くの場合、期待の裏切りや約束の不履行があります。仕事の文脈で考えると、「よく休む人」が信用されにくいと感じられる主な理由は、大きく分けて以下の点が挙げられるでしょう。
業務の継続性・安定性への懸念
多くの仕事は、個人の力だけでなく、チーム全体で連携して進められます。その中で、誰かが頻繁に休むと、担当業務が滞ったり、他のメンバーがその穴埋めをしなければならなくなったりします。これにより、プロジェクトの進行に遅れが生じる、あるいは業務の品質が低下するのではないか、といった懸念が生じます。
- 担当業務の停滞: その人にしか分からない業務や、専門的な知識が必要な作業が止まってしまうと、全体の進捗に大きな影響が出ます。
- チームワークの乱れ: 予定されていた協力体制が崩れ、他のメンバーの作業計画にも変更が生じることがあります。
- 納期への不安: 決められた納期までに成果物を完成させられるのか、という不安感がチーム内に広がることがあります。
このように、業務の継続性や安定性が損なわれることへの恐れが、「本当にこの人に任せて大丈夫だろうか」「重要な仕事を安心して頼めない」といった不信感に繋がるのです。
コミュニケーションの機会損失
仕事を進める上では、日々の細やかな情報共有や意思疎通が欠かせません。しかし、頻繁に休む人がいると、その人とのコミュニケーションの機会が物理的に減ってしまいます。
- 情報共有の遅れや漏れ: 会議に出席できない、口頭での確認ができないなど、重要な情報が伝わりにくくなることがあります。
- 意思決定の遅延: その人の判断や承認が必要な業務がストップしてしまうことがあります。
- チームの一体感の低下: 顔を合わせる機会が減ることで、チームメンバーとしての連帯感や仲間意識が薄れ、心理的な距離が生まれることもあります。
これらのコミュニケーション不足が積み重なると、「何を考えているのか分からない」「チームの一員としての自覚があるのだろうか」といった疑念を生み、結果として信用を損ねる原因となり得ます。
公平性への疑問
特に理由が明確でない休みが続いたり、休むタイミングが不自然だと感じられたりすると、周囲の人は「自分たちだけが頑張っているのではないか」「不公平だ」という感情を抱きやすくなります。
- 負担の偏り: 特定のメンバーにばかり仕事の負担が集中していると感じると、不満が募ります。
- ルールの遵守意識への疑念: 職場のルールや規律を守る意識が低いのではないか、と見られてしまうことがあります。
- 真摯さの欠如: 仕事に対する真摯な姿勢や責任感が感じられないと、人間的な信頼も揺らぎます。
このような公平性への疑問は、職場のモチベーション低下にも繋がりかねず、「よく休む人」に対する不信感を増幅させる要因となります。
これらの理由は、決して個人的な感情論だけでなく、仕事という共同作業を円滑に進める上での合理的な懸念に基づいている部分も大きいと言えるでしょう。
仕事でよく休む人に対する「迷惑」「ずるい」という感情の背景にある心理
「あの人が休むと、こっちが迷惑するんだよね…」「なんだかずるい気がする…」。口には出さなくても、心の中でそう感じてしまう人は少なくないかもしれません。仕事でよく休む人に対して迷惑だと感じたり、ずるいと感じたりする感情の裏には、どのような心理が隠されているのでしょうか。
「迷惑」と感じる心理:負担増と計画の狂い
「迷惑」という感情は、主に自分の時間や労力が予期せず奪われることに対する直接的な反応と言えます。
- 代理業務による負担感:
急な休みの場合、その人の仕事を誰かが肩代わりしなければなりません。自分の通常業務に加えて他人の仕事まですることになれば、時間的にも精神的にも大きな負担となります。「なぜ自分がやらなければならないのか」という思いが、迷惑だと感じる直接的な原因になるでしょう。 - 業務計画の修正と手間:
予定していた業務スケジュールが狂い、計画を立て直す必要が出てきます。関係各所への連絡や調整など、追加の作業が発生することも、迷惑だと感じる一因です。特に納期が迫っている業務であれば、そのプレッシャーはさらに大きくなります。 - 心理的なストレス:
いつ休むか分からない人がいると、「また明日も休むのではないか」「重要な仕事を任せて大丈夫か」といった不安が常に付きまとい、心理的なストレスを感じやすくなります。この見えないストレスも、迷惑という感情を増幅させます。
「ずるい」と感じる心理:不公平感と努力の相対化
一方、「ずるい」という感情は、より複雑な心理状態が絡み合っています。「自分は我慢しているのに」「自分は頑張っているのに」という思いが根底にあることが多いようです。
- 不公平感と犠牲感:
自分は体調が悪くても無理して出勤したり、プライベートを犠牲にして仕事に取り組んだりしているのに、簡単に休むように見える人がいると、「自分だけが損をしている」「不公平だ」という感情が芽生えやすくなります。この不公平感が、「ずるい」という感覚に繋がるのです。 - 努力や我慢の相対化:
自分が努力して乗り越えている困難(例えば、多少の体調不良や多忙な状況)を、他の人が簡単に回避しているように見えると、自分の努力や我慢が無価値であるかのように感じてしまうことがあります。その結果、「自分も本当は休みたいのに」「なぜあの人だけ許されるのか」という不満が「ずるい」という言葉で表現されるのです。 - 規範意識とのズレ:
多くの人は、「仕事には責任を持って取り組むべきだ」「簡単に休むべきではない」といった規範意識を持っています。その規範から外れているように見える行動に対して、「許せない」「ルール違反だ」という気持ちが生じ、それが「ずるい」という感情に転化することがあります。
これらの「迷惑」や「ずるい」といった感情は、決して意地悪な気持ちから生じるものばかりではありません。むしろ、真面目に仕事に取り組んでいる人ほど、このような感情を抱きやすい傾向があるとも言えます。大切なのは、なぜ自分がそう感じるのかを客観的に理解し、その感情にどう向き合っていくかということです。
頻繁に休むことで起こる「仕事のしわ寄せ」と職場への具体的な影響
誰かが頻繁に休むと、その影響は個人の感情だけでなく、職場全体に波及します。特に深刻なのが「仕事のしわ寄せ」です。これは、休んだ人の業務が他の誰かに降りかかる現象を指し、さまざまな具体的な問題を引き起こします。

周囲のメンバーへの直接的な業務負担増
最も直接的で分かりやすい影響は、残されたメンバーの業務量が増えることです。
- 担当業務の肩代わり:
休んだ人の日々の業務(メール対応、資料作成、会議への代理出席など)を、他のメンバーが分担して行わなければなりません。これにより、各自が本来やるべき仕事に割く時間が減ってしまいます。 - 残業時間の増加:
自分の仕事に加えて他人の仕事もこなそうとすると、どうしても時間内に終わらず、残業が増える傾向にあります。これが常態化すると、疲労が蓄積し、さらなる生産性の低下を招く悪循環に陥ります。 - 業務品質の低下リスク:
慣れない業務を急遽担当したり、時間に追われて作業したりすることで、ミスが起こりやすくなったり、仕事の質が低下したりする可能性があります。これは、個人の能力の問題ではなく、無理な状況が引き起こすリスクです。
チーム全体の生産性低下
個々のメンバーの負担増は、やがてチーム全体の生産性低下へと繋がります。
- プロジェクトの遅延:
誰か一人が欠けることで、チーム全体の仕事のスピードが落ち、プロジェクトの納期に影響が出ることがあります。特に、その人がキーパーソンである場合は、影響はより深刻になります。 - 意思決定の停滞:
会議に不在だったり、必要な情報共有が滞ったりすることで、重要な意思決定が遅れることがあります。迅速な判断が求められる場面では、これが致命的になることもあります。 - 新しい取り組みへの停滞:
日々の業務に追われるようになると、新しい企画を考えたり、業務改善に取り組んだりする余裕がなくなります。これにより、チームや組織の成長が妨げられる可能性があります。
職場の雰囲気悪化と人間関係への影響
仕事のしわ寄せが続くと、職場の雰囲気にも悪影響が出てきます。
- 不満や不公平感の蔓延:
「なぜ自分ばかりがこんなに大変な思いをしなければならないのか」という不満や、「休んでいる人は楽をしている」といった不公平感が職場に広がります。 - コミュニケーションの悪化:
負担を感じているメンバーと、頻繁に休むメンバーとの間に溝ができ、コミュニケーションがギクシャクすることがあります。必要な情報共有も円滑に行われなくなるかもしれません。 - モチベーションの低下:
頑張っても報われない、負担ばかりが増えるという状況は、メンバーの仕事に対するモチベーションを著しく低下させます。最悪の場合、優秀な人材の離職に繋がることも考えられます。
このように、「仕事のしわ寄せ」は単に業務量が増えるというだけでなく、チームの機能不全や職場の雰囲気悪化など、多岐にわたる深刻な影響を及ぼす可能性があるのです。この問題を放置することは、企業にとっても大きな損失となりかねません。
「よく休む人」の行動が個人の評価や信頼にどう繋がるのか
職場において、「よく休む人」というレッテルは、その人の評価や周囲からの信頼に少なからず影響を与える可能性があります。たとえ休む理由が正当なものであったとしても、頻度が高ければ、どうしてもネガティブな印象を持たれやすくなるのが現実です。
責任感やコミットメントへの疑念
最も大きく影響するのは、仕事に対する責任感や組織へのコミットメント(関与度合い)に対する評価でしょう。
- 仕事への意欲が低いと見なされる可能性:
頻繁に休むことで、「仕事よりもプライベートを優先している」「仕事に対する熱意が低いのではないか」と周囲に解釈されてしまうことがあります。本人の意図とは異なっていても、行動がそのように受け取られやすいのです。 - 重要な仕事を任せにくいという判断:
上司や同僚は、「この人に重要な仕事を任せても、また休んでしまうのではないか」という不安を感じるようになります。結果として、責任のある仕事や新しいプロジェクトのメンバーから外されるなど、キャリアアップの機会を逃すことに繋がる可能性があります。 - チームへの貢献度が低いという評価:
チームで成果を出すためには、各メンバーがそれぞれの役割を果たすことが求められます。休みが多いと、どうしてもチームへの貢献度が低いと見なされがちです。これは、人事評価におけるマイナスポイントとなることもあります。
安定性や継続性への不安感
ビジネスの世界では、安定してパフォーマンスを発揮できる人材が求められます。
- 計算できない戦力という印象:
いつ休むか分からない人は、チームの戦力として計算しづらい存在と見なされることがあります。特に繁忙期や重要な局面で不在になることが多いと、その印象はさらに強まります。 - キャリアの停滞リスク:
昇進や昇格の際には、これまでの実績だけでなく、今後の安定的な貢献も期待されます。休みが多いことが、将来的な成長への期待値を下げてしまう可能性があります。
周囲との信頼関係構築の難しさ
信頼関係は、日々の積み重ねによって築かれます。
- コミュニケーション不足による誤解:
前述の通り、休みが多いと周囲とのコミュニケーションの機会が減り、相互理解が深まりにくくなります。これが誤解や憶測を生み、信頼関係の構築を難しくします。 - 「頼りにならない」というレッテル:
いざという時に頼りにならない、という印象が一度ついてしまうと、それを払拭するのは容易ではありません。周囲からのサポートも得にくくなる可能性があります。
もちろん、これらはあくまで一般的な傾向であり、休む理由や職場の文化、個人のコミュニケーション能力などによって、評価への影響度は大きく変わります。例えば、事前にしっかりと引き継ぎを行い、復帰後に誠実に対応することで、ネガティブな影響を最小限に抑えることも可能です。
しかし、一般論として、「よく休む」という行動は、本人の意図に関わらず、評価や信頼という側面で不利に働く可能性を秘めていることを理解しておく必要があるでしょう。
体調不良でよく休む人と、そうでない場合の印象の違いはある?
同じ「よく休む」という状況でも、その理由によって周囲の受け止め方や印象は大きく異なることがあります。特に、「体調不良でよく休む人」と、そうでない(例えば、私用や理由が不明確な)休みが多い人とでは、印象に違いが生じるのが一般的です。

「体調不良でよく休む人」に対する印象
体調不良が原因で頻繁に休む場合、周囲は一定の理解や同情を示すことが多いでしょう。誰しも病気になる可能性はあり、「お互い様」という意識が働きやすいからです。
- 同情や心配:
「つらいだろうな」「早く良くなるといいな」といった同情的な気持ちや、健康状態を心配する声が上がりやすいです。特に、普段から真面目に仕事に取り組んでいる人であれば、なおさらでしょう。 - やむを得ないという認識:
体調不良は本人の意思でコントロールできるものではないため、「仕方がない」「無理もない」と受け止められる傾向があります。 - ただし、懸念がゼロではない:
いくら同情の念があっても、休みが長期にわたったり、頻度があまりにも高かったりすると、業務への支障や将来的な就業継続への不安から、懸念の声が出てくることもあります。また、具体的な病状が不明な場合や、普段の不摂生が原因ではないかと思われる場合には、同情の度合いが薄れることもあり得ます。
理由が不明確、または私用などでの休みが多い人に対する印象
一方、体調不良以外の理由、あるいは理由がはっきりしない休みが多い場合は、より厳しい目が向けられやすくなります。
- 不信感や不公平感:
「本当に必要な休みなのか」「サボっているのではないか」といった疑念や、「自分たちだけが頑張っている」という不公平感が生まれやすいです。 - 責任感の欠如と見なされる可能性:
仕事に対する責任感が薄い、自己管理ができていない、とネガティブに評価されるリスクが高まります。 - コミュニケーション不足による憶測:
休む理由をきちんと説明しない場合、周囲は憶測で判断するしかなく、悪い方向に解釈されがちです。例えば、「遊びで休んでいるのでは」「他の仕事を探しているのでは」といった噂が立つこともあります。
印象の違いを生むポイント
このように印象が異なる背景には、いくつかのポイントがあります。
- 正当性と不可抗力:
体調不良は、一般的に「正当な理由」であり、かつ「不可抗力」と見なされやすいのに対し、他の理由はそうではない場合があります。 - 共感の度合い:
体調不良のつらさは多くの人が経験的に理解できるため共感しやすいですが、個人的な都合による休みに対しては、共感の度合いが低くなることがあります。 - 情報開示と説明責任:
体調不良の場合、ある程度の状況説明(例:「熱があるので休みます」)があれば納得されやすいですが、理由が不明確な場合は、説明責任を果たしていないと見なされることがあります。
ただし、重要なのは、外から見える情報だけで全てを判断するのは危険だということです。「体調不良」と一口に言っても、その背景には深刻な持病やメンタルヘルスの問題が隠れていることもあります。また、私用に見える休みが、実は家族の介護など、やむを得ない事情である可能性も否定できません。
したがって、周囲としては、個々の事情を軽々しく詮索するのではなく、まずは本人の言葉に耳を傾け、必要な配慮ができる体制を整えることが望ましいと言えるでしょう。そして、休む側も、可能な範囲で状況を伝え、周囲の理解を得る努力をすることが、無用な誤解を避けるためには大切です。
休みが多いことで「嫌われる」のではないかという不安の正体
「こんなに休んでばかりいたら、みんなに嫌われるんじゃないだろうか…」。休みが多いことで、職場の人から嫌われるのではないかと不安に感じる人は少なくありません。この不安は、単なる思い過ごしなのでしょうか。それとも、実際に起こり得るリスクなのでしょうか。その不安の正体を探ってみましょう。
「嫌われる」とは具体的にどういう状態か
まず、「嫌われる」という言葉が指す状態を具体的に考えてみましょう。これは、単に「好かれていない」というレベルを超えて、以下のようなネガティブな感情や行動を向けられることを意味することが多いです。
- 陰口や悪口を言われる:
本人がいないところで、「また休んでる」「仕事しないよね」といった否定的な噂話をされる。 - 無視されたり、避けられたりする:
挨拶をしても返事がない、会話の輪に入れてもらえない、意図的に距離を置かれる。 - 協力が得られにくくなる:
仕事で困っていても助けてもらえない、必要な情報が共有されない。 - 不当な評価を受ける:
能力や成果とは関係なく、休みが多いという理由だけで低い評価をつけられる。 - 孤立感を感じる:
職場で自分の居場所がないように感じ、精神的に追い詰められる。
このような状況は、働く上で非常につらく、モチベーションの低下はもちろん、心身の健康にも悪影響を及ぼしかねません。
なぜ「嫌われる」不安が生じるのか
休みが多いことでこのようなネガティブな反応を恐れる背景には、いくつかの心理的な要因が考えられます。
- 罪悪感と負い目:
「他の人に迷惑をかけている」「自分だけが楽をしているのではないか」という罪悪感や負い目が、周囲からの非難を想像させ、不安を増幅させます。特に責任感の強い人ほど、この傾向が強いかもしれません。 - 集団からの疎外への恐れ:
人間は社会的な生き物であり、自分が所属する集団から受け入れられたいという欲求を持っています。頻繁に休むことで、チームの一員として認められず、疎外されることへの本能的な恐れが、「嫌われる」という不安に繋がります。 - 評価への懸念:
前述の通り、休みが多いことは人事評価に影響する可能性があります。「嫌われる」という感情的な問題だけでなく、自身のキャリアや待遇が悪くなることへの現実的な不安も含まれています。 - 過去の経験や見聞きした話:
過去に自分が似たような状況でネガティブな扱いを受けた経験があったり、同僚や友人がそのような目に遭っているのを見聞きしたりすると、「自分も同じように扱われるのではないか」と不安になりやすいです。
「嫌われる」リスクは現実にあるのか
残念ながら、休みが多いことで実際に周囲からネガティブな感情を抱かれたり、不利益な扱いを受けたりするリスクはゼロではありません。特に、以下のような場合には、そのリスクが高まる可能性があります。
- コミュニケーション不足:
休む理由や状況をきちんと伝えず、周囲に憶測や不信感を抱かせてしまう場合。 - 感謝や配慮の欠如:
自分の代わりに仕事をしてくれている同僚への感謝の気持ちを示さなかったり、復帰後に迷惑をかけたことへの配慮が見られなかったりする場合。 - 職場の雰囲気や文化:
休みに対して不寛容な職場文化であったり、助け合いの精神が薄い職場であったりする場合。 - 休む頻度やタイミング:
あまりにも頻繁に休んだり、繁忙期や重要な会議の日に限って休んだりするなど、周囲に与える影響が大きい場合。
しかし、重要なのは、休みが多いからといって必ずしも嫌われるわけではないということです。むしろ、誠実なコミュニケーションを心がけ、周囲への感謝と配慮を忘れず、可能な範囲で仕事への貢献意欲を示すことで、理解や協力を得られるケースも多くあります。
「嫌われるかもしれない」という不安に苛まれるのではなく、なぜそう感じるのかを客観的に見つめ、自分にできる前向きな行動をとることが、不安を軽減し、より良い職場環境を築くための一歩となるでしょう。
よく休む人が信用出来ない…仕事のしわ寄せ問題と職場の誤解を解消するには
「よく休む人は信用出来ない」と感じてしまう気持ちや、それによって生じる「仕事のしわ寄せ」は、職場にとって大きな課題です。しかし、この問題を個人の責任として片付けてしまうだけでは、根本的な解決には繋がりません。

大切なのは、なぜそのような状況が生まれるのかを理解し、チーム全体で協力して誤解を解き、より働きやすい環境を作っていくことです。この項目では、具体的な対処法や、職場全体の意識改革に向けたヒントを探っていきましょう。
「仕事のしわ寄せ」にどう対処する?チームで乗り越える工夫
誰かが休んだ際に発生する「仕事のしわ寄せ」は、残されたメンバーにとって大きな負担となります。しかし、これを個人の頑張りだけで解決しようとすると、いずれ限界が訪れます。大切なのは、チーム全体でこの問題に取り組み、負担を分散し、乗り越えていくための工夫をすることです。
情報共有と業務の標準化・見える化
まず基本となるのは、誰かが休んでも業務が滞らないようにするための準備です。
- 業務マニュアルの作成と更新:
特定の人しか分からない「属人的な業務」を減らすために、業務の手順やノウハウをマニュアル化し、常に最新の状態に保ちましょう。これにより、他の人が代理で業務を行う際のハードルが下がります。 - 情報共有ツールの活用:
チャットツール、プロジェクト管理ツール、共有フォルダなどを活用し、業務に関する情報をリアルタイムで共有できる体制を整えます。誰が何を担当し、進捗状況はどうなっているのかを「見える化」することで、急な休みにも対応しやすくなります。 - 定期的な業務内容の共有会:
チーム内で、お互いの業務内容や進め方について共有する機会を設けましょう。これにより、いざという時に「何をどうすれば良いのか分からない」という状況を防ぎ、スムーズな業務の引き継ぎが可能になります。
業務のローテーションと多能工化
特定の業務が一人の担当者に集中していると、その人が休んだ時の影響は甚大です。
- ジョブローテーションの導入:
定期的に担当業務を入れ替えることで、複数のメンバーがさまざまな業務を経験できるようにします。これにより、誰かが休んでも他の人がカバーできる体制を築きやすくなります。 - 多能工化の推進:
一人が複数の業務スキルを身につける「多能工化」をチーム全体で目指しましょう。研修機会の提供やOJT(オンザジョブトレーニング)を通じて、メンバーのスキルアップを支援します。
負担を分散するためのルール作りと協力体制
実際に誰かが休んだ際に、どのように業務を分担するのか、あらかじめルールを決めておくことも重要です。
- 代理担当者の明確化:
各業務について、主担当者だけでなく、副担当者や代理担当者を決めておきましょう。これにより、急な休みが発生した場合でも、誰が対応すべきかが明確になります。 - 業務の優先順位付け:
休んだ人の業務全てを完璧にカバーしようとすると、残されたメンバーの負担が過大になります。緊急度の高い業務、重要度の高い業務を優先し、そうでない業務は一時的に保留するなど、優先順位を明確にするルールを設けることが大切です。 - 「お互い様」の精神の醸成:
誰でも病気になったり、急な用事で休んだりする可能性はあります。「困ったときはお互い様」という意識をチーム全体で共有し、自然に助け合える雰囲気を作ることが、しわ寄せ問題を乗り越えるための最も重要な土壌となります。
上司・管理職の役割
チームでしわ寄せ問題に対処するためには、上司や管理職の適切なマネジメントが不可欠です。
- 業務量の適切な配分:
日頃からメンバーの業務量を把握し、特定の個人に負担が偏らないように調整する責任があります。 - メンバーのスキル育成支援:
情報共有や多能工化を推進するための環境整備や、必要な研修機会の提供などを行います。 - 公平な評価と配慮:
他のメンバーの業務をカバーした人に対しては、その貢献を正当に評価し、感謝の意を示すことが重要です。また、頻繁に休むメンバーに対しても、その背景にある事情を理解しようと努め、必要なサポートを提供することも求められます。
「仕事のしわ寄せ」は、誰か一人の問題ではなく、チーム全体で取り組むべき課題です。これらの工夫を通じて、お互いにサポートし合える、より強靭なチームを作っていくことが大切です。
「よく休む人」とのコミュニケーションで誤解を生まないポイント
「よく休む人」に対して、知らず知らずのうちにネガティブな感情を抱いてしまったり、それが態度に出てしまったりすることは、人間関係を悪化させ、職場の雰囲気を悪くする原因となります。誤解を避け、建設的な関係を築くためには、コミュニケーションの取り方に工夫が必要です。
まずは相手の状況を理解しようと努める
人は誰でも、見えない事情を抱えている可能性があります。表面的な行動だけで判断せず、相手の状況を理解しようとする姿勢が大切です。
- 決めつけや憶測を避ける:
「どうせサボっているんだろう」「やる気がないんだ」といった決めつけは禁物です。何か事情があるのかもしれない、という前提で接するように心がけましょう。 - 話を聞く姿勢を持つ:
もし相手が休む理由や状況について話してきたら、まずはじっくりと耳を傾けましょう。批判的な態度や遮るような態度は避け、相手が安心して話せる雰囲気を作ることが重要です。ただし、プライベートなことに過度に踏み込むのは避け、相手が話せる範囲で尊重しましょう。 - 体調を気遣う言葉をかける(ただし過度にならないように):
体調不良で休んでいる場合は、「お大事にしてください」「無理なさらないでくださいね」といった気遣いの言葉は、相手の気持ちを和らげることがあります。ただし、あまりしつこく聞いたり、診断するようなことを言ったりするのは避けましょう。
伝えるべきことは、客観的かつ具体的に
業務上の支障が出ている場合や、改善を求めたいことがある場合は、感情的に伝えるのではなく、客観的な事実に基づいて具体的に伝えることが大切です。
- 感情的な非難は避ける:
「いつも迷惑している」「いい加減にしてほしい」といった感情的な言葉は、相手を委縮させたり反発させたりするだけで、問題解決には繋がりません。 - 「私」を主語にして伝える(アイメッセージ):
「あなたが休むと、私が(私たちが)〇〇という状況になり困っています」というように、「私」を主語にして、自分やチームがどのような影響を受けているのかを具体的に伝えましょう。「あなたはいつも〇〇だ」という「あなた」を主語にする言い方(ユーメッセージ)は、相手を責めているように聞こえがちです。 - 具体的な事実と影響を伝える:
「〇月〇日の会議にあなたが不在だったため、△△の決定が遅れました」というように、いつ、何が起きて、どのような影響が出たのかを具体的に伝えましょう。漠然とした不満ではなく、具体的な事実を伝えることで、相手も問題を認識しやすくなります。 - 期待する行動を明確に伝える(提案の形で):
「今後は、事前に分かっているお休みは早めに共有していただけると助かります」「もし可能であれば、〇〇の業務については、事前に引き継ぎ資料を作成していただけるとありがたいです」というように、どうしてほしいのかを具体的に、そして提案の形で伝えると、相手も受け入れやすくなります。
普段からのコミュニケーションを大切にする
休みが多い人とそうでない人の間に限らず、日頃からの良好なコミュニケーションは、誤解を防ぎ、いざという時の協力をスムーズにするために不可欠です。
- 挨拶や日常会話を欠かさない:
基本的なことですが、日々の挨拶やちょっとした声かけは、お互いの心理的な距離を縮めます。 - 感謝の気持ちを伝える:
些細なことでも、助けてもらったり、協力してもらったりした際には、「ありがとう」という感謝の言葉をきちんと伝えましょう。 - チームミーティングなどを活用する:
定期的なチームミーティングなどで、お互いの状況や考えていることを共有する機会を持つことも有効です。
誤解は、コミュニケーション不足から生まれることがほとんどです。相手を尊重し、誠実な対話を心がけることが、「よく休む人」との間に生じがちな壁を取り払い、より良い職場関係を築くための第一歩となるでしょう。
体調不良でよく休む人を理解し、サポートする職場の体制づくり
体調不良でよく休む人がいる場合、その人個人を責めるのではなく、職場全体としてどのように理解し、サポートしていくかを考えることが重要です。安心して休養でき、また、無理なく復帰できるような体制を整えることは、本人のためだけでなく、周囲のメンバーの負担軽減や、職場全体の生産性向上にも繋がります。
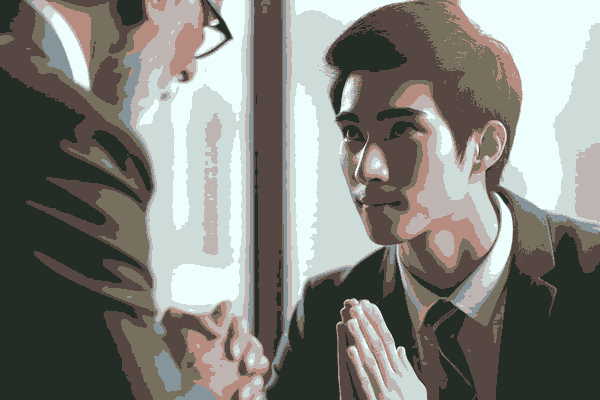
安心して休める文化の醸成
まず大切なのは、「体調が悪い時は無理せず休んで良い」という文化を職場に根付かせることです。
- 「休むことは権利」という認識の共有:
有給休暇の取得は労働者の権利であり、体調不良時に休むことも当然のことであるという認識を、経営層から一般社員まで全員が共有することが基本です。 - 上司や同僚からのプレッシャーをなくす:
「休んだら迷惑がかかる」「評価が下がるかもしれない」といったプレッシャーを感じさせない雰囲気づくりが重要です。上司が率先して休暇を取得したり、体調不良のメンバーを気遣う言動を心がけたりすることが効果的です。 - 病気に対する偏見をなくす:
特にメンタルヘルスの不調などは、周囲に理解されにくいことがあります。病気の種類に関わらず、誰もが安心して療養に専念できるような、偏見のない職場環境を目指しましょう。
柔軟な働き方の導入と業務調整
体調に合わせて働き方を調整できる制度があれば、本人の負担を軽減し、就業継続をサポートできます。
- テレワーク(在宅勤務)制度の活用:
通勤の負担がなく、自分のペースで仕事ができるテレワークは、体調が万全でない時に有効な選択肢となります。 - フレックスタイム制度の導入:
体調の良い時間帯に集中して働き、調子が悪い時は休憩を取るなど、柔軟な勤務時間を選べるフレックスタイム制も効果的です。 - 短時間勤務制度や業務量の調整:
一時的に勤務時間を短縮したり、担当する業務量を調整したりすることで、無理なく仕事を続けられるように配慮します。上司は、本人の状況をヒアリングしながら、適切な業務配分を行う必要があります。
情報共有とバックアップ体制の強化
誰かが休んでも業務が円滑に進むように、日頃から情報共有とバックアップ体制を強化しておくことが不可欠です。
- 業務の標準化とマニュアル整備:
前述の通り、誰でも業務を代替できるように、マニュアルの整備や業務プロセスの標準化を進めます。 - 複数担当制の導入:
一つの業務を複数の担当者で共有する体制を作ることで、一人が休んでも他のメンバーがカバーしやすくなります。 - 定期的な進捗共有と引き継ぎルールの明確化:
日頃から業務の進捗状況をチーム内で共有し、急な休みが発生した場合の引き継ぎルールを明確にしておくことで、混乱を最小限に抑えられます。
産業医や専門機関との連携(企業として)
企業として、産業医や外部の専門機関と連携し、社員の健康管理をサポートする体制を整えることも重要です。
- 産業医面談の機会提供:
体調に不安がある社員が、気軽に産業医に相談できる機会を提供します。 - メンタルヘルスケアの充実:
ストレスチェックの実施や、カウンセリング窓口の設置など、メンタルヘルス不調の予防と早期対応に努めます。 - 復職支援プログラムの整備:
長期休養後の社員がスムーズに職場復帰できるよう、段階的な業務再開や、周囲の理解促進をサポートするプログラムを用意します。
体調不良でよく休む人をサポートする体制づくりは、その人個人のためだけではなく、チーム全体の負担を軽減し、結果として働きやすい職場環境を実現するために不可欠です。個々の事情に配慮しつつ、組織として支え合う文化を育てていくことが求められます。
休む側も知っておきたい、周囲への配慮と信頼回復のためにできること
体調不良ややむを得ない事情で休みが多くなってしまう場合、本人が一番つらい思いをしていることも少なくありません。しかし、同時に周囲に負担をかけているという現実も受け止め、できる限りの配慮を心がけることが、無用な誤解を防ぎ、信頼関係を維持・回復するために大切です。
事前の連絡と状況説明(可能な範囲で)
休むことが事前に分かっている場合はもちろん、急な休みの場合でも、できるだけ早く、適切な方法で連絡を入れることが基本マナーです。
- 早めの連絡を心がける:
当日の朝になってからではなく、前日までに分かる場合は、その時点で連絡しましょう。体調不良の場合も、朝起きて「無理そうだ」と感じたら、速やかに連絡します。 - 連絡手段と相手を適切に選ぶ:
職場のルール(電話、メール、チャットなど)に従い、直属の上司やチームリーダーなど、伝えるべき相手に確実に連絡しましょう。無断欠勤は絶対に避けるべきです。 - 休む理由と期間の見込みを伝える(可能な範囲で):
「体調不良のため、本日は休ませていただきます。明日には出社できる見込みです」というように、具体的な理由と、いつ頃復帰できそうかの見込みを伝えられると、周囲も対応しやすくなります。プライベートな詳細まで話す必要はありませんが、業務への影響を最小限にするための情報は伝えるようにしましょう。 - 引き継ぎ事項があれば伝える:
急ぎで対応が必要な業務や、他の人に依頼したいことがある場合は、連絡の際に具体的に伝えましょう。「〇〇の件は、△△さんにお願いできますでしょうか」「□□の資料は、共有フォルダの××に入っています」など、具体的な指示があると助かります。
業務の引き継ぎと情報共有の徹底
自分が休んでいる間も業務が滞りなく進むように、日頃から準備しておくこと、そして休む際にしっかりと引き継ぎを行うことが重要です。
- 普段から業務の「見える化」を意識する:
自分の担当業務の進捗状況や関連資料は、個人で抱え込まず、チームメンバーがアクセスできる場所に整理しておく習慣をつけましょう。 - マニュアルや手順書を作成・更新しておく:
自分がいなくても他の人が業務を代行できるように、分かりやすいマニュアルや手順書を作成し、常に最新の状態に保っておくことが理想です。 - 休む前には丁寧な引き継ぎを:
事前に休むことが分かっている場合は、担当業務の進捗、懸念事項、対応が必要なことなどをリストアップし、口頭だけでなく書面でも引き継ぎを行いましょう。代理で対応してくれる人への感謝の言葉も忘れずに。
復帰後の誠実な対応と感謝の表明
休み明けに出社した際には、周囲への感謝の気持ちを伝え、業務に真摯に取り組む姿勢を示すことが信頼回復に繋がります。
- 感謝の言葉を伝える:
「休んでいる間、ご迷惑をおかけしました。サポートしていただき、ありがとうございました」と、まずは上司や同僚に感謝の気持ちを伝えましょう。 - 休んでいた間の状況を把握する:
メールやチャットの履歴を確認したり、同僚に状況を聞いたりして、休んでいた間に何があったのか、どのような業務が進んでいたのかを速やかに把握しましょう。 - 溜まっている業務に積極的に取り組む:
体調が許す範囲で、溜まっている自分の仕事に積極的に取り組み、遅れを取り戻そうとする姿勢を見せることが大切です。 - 同じことを繰り返さないための努力を示す(もし改善可能な場合):
もし休んだ原因が自身の生活習慣などにあった場合、それを改善しようと努力している姿勢を見せることも、周囲の理解を得る上で効果的な場合があります。
周囲とのコミュニケーションを大切にする
誤解や不信感は、コミュニケーション不足から生まれることが多いです。日頃から良好な関係を築く努力をしましょう。
- 挨拶や声かけを積極的に:
基本的なことですが、普段から明るく挨拶をしたり、積極的に声をかけたりすることで、親しみやすい雰囲気を作ることができます。 - チームの一員としての意識を持つ:
飲み会や社内イベントなど、業務外のコミュニケーションの場にも、無理のない範囲で参加することも、チームの一体感を高めるのに役立ちます。 - 相談できる相手を見つける:
職場に一人でも良いので、自分の状況を理解してくれ、気軽に相談できる相手を見つけておくと、精神的な支えになります。
休みが多いことで肩身の狭い思いをすることもあるかもしれませんが、誠実な対応と周囲への感謝の気持ちを忘れなければ、きっと理解してくれる人はいるはずです。自分にできることから一つひとつ丁寧に行動していくことが、信頼回復への道となるでしょう。
「信用出来ない」から「理解できる」へ、職場全体の意識改革のヒント
「よく休む人は信用出来ない」という一方的な見方から、「なぜ休むのか」「どうすればサポートできるのか」という理解へと、職場全体の意識を変えていくことは、一朝一夕にできることではありません。しかし、継続的な働きかけによって、より協力的で働きやすい環境を築くことは可能です。そのためのヒントをいくつかご紹介します。

経営層・管理職からのメッセージ発信と率先垂範
意識改革は、トップダウンで進めることが効果的です。
- 多様な働き方への理解と受容を明言する:
経営層や管理職が、社員の健康やワークライフバランスの重要性を認識し、さまざまな事情で休みが必要な社員がいることを受容する姿勢を明確にメッセージとして発信します。 - 休暇取得を奨励する:
「休むことは悪いことではない」という雰囲気を醸成するために、管理職自身が率先して有給休暇を取得したり、部下に休暇取得を促したりすることが重要です。 - ハラスメント防止への取り組み:
休みが多いことを理由とした不当な扱いや陰口などが起こらないよう、ハラスメント防止研修を実施するなど、具体的な対策を講じます。
オープンなコミュニケーションの促進
お互いの状況を理解し合うためには、風通しの良いコミュニケーションが不可欠です。
- 1on1ミーティングの定期的な実施:
上司と部下が定期的に1対1で話す機会を設け、業務上の課題だけでなく、体調面やプライベートな悩みについても(本人が話せる範囲で)相談しやすい関係性を構築します。 - チーム内での情報共有と相互理解の場:
チームミーティングなどで、個々の業務状況だけでなく、お互いの事情(例えば、子育て中、介護中など)を理解し合い、協力体制を築くための話し合いの場を設けます。 - 匿名で意見や悩みを伝えられる仕組み:
直接は言いにくい意見や悩みを匿名で伝えられる目安箱のような仕組みを導入することも、本音を引き出し、問題の早期発見に繋がる場合があります。
制度の整備と周知徹底
安心して働ける環境を作るためには、制度的なサポートも重要です。
- 柔軟な勤務制度の導入・拡充:
テレワーク、フレックスタイム、短時間勤務など、社員の状況に合わせて柔軟に働ける制度を整備し、それらの制度が実際に利用しやすいように周知徹底します。 - 休暇制度の充実と利用促進:
病気休暇、慶弔休暇、リフレッシュ休暇など、さまざまなニーズに対応できる休暇制度を充実させ、取得しやすい雰囲気を作ります。 - 相談窓口の設置と機能強化:
体調面やメンタルヘルスの問題、ハラスメント被害などについて、安心して相談できる社内外の窓口を設け、その存在と利用方法を周知します。
成功事例の共有とポジティブな雰囲気づくり
実際に休みを取得しながらも活躍している社員の事例や、チームで協力して困難を乗り越えた経験などを共有することで、ポジティブな雰囲気を醸成します。
- ロールモデルの提示:
育児や介護と仕事を両立している社員、病気治療をしながら働いている社員など、さまざまな状況で活躍しているロールモデルを紹介することで、「自分も大丈夫だ」という安心感を与えます。 - 助け合いの文化を称賛する:
困っている同僚をサポートした社員や、チームワークを発揮して成果を上げた部署などを表彰するなど、助け合いの文化を称賛し、奨励します。
継続的な教育と啓発活動
意識改革は一度で終わるものではありません。継続的な教育と啓発活動を通じて、徐々に組織文化を変えていく必要があります。
- ダイバーシティ&インクルージョン研修:
多様な価値観や背景を持つ人々が、互いに尊重し合い、能力を発揮できる職場環境の重要性について学ぶ機会を提供します。 - メンタルヘルス研修:
メンタルヘルス不調のサインや、不調を抱える同僚への適切な対応方法などについて学ぶことで、早期発見・早期対応に繋げます。
これらのヒントは、すぐに効果が出るものばかりではないかもしれません。しかし、一つひとつ地道に取り組んでいくことで、「信用出来ない」という不信感が「お互い様」という理解と協力の精神へと変わり、誰もが安心して、そして最大限に能力を発揮できる職場環境が育っていくはずです。
仕事休む人のフォローで疲れる…と感じた時のセルフケアと相談窓口
仕事で休む人のフォローが続くと、どんなに「お互い様」と思っていても、心身ともに疲弊してしまうことがあります。「また自分がやらなきゃいけないのか…」「いつまでこの状況が続くんだろう…」といったネガティブな感情が湧き上がり、モチベーションが低下してしまうこともあるでしょう。そんな時、自分自身を守るためのセルフケアと、状況を改善するための相談について考えてみましょう。
自分の感情と向き合い、受け止める
まず大切なのは、自分が「疲れている」「不満を感じている」という感情を否定せずに受け止めることです。
- 感情を認識する:
「イライラする」「しんどい」「不公平だ」といった感情を、そのまま認めてあげましょう。無理にポジティブに考えようとしたり、感情に蓋をしたりする必要はありません。 - 何が負担になっているのかを具体的にする:
漠然とした疲れや不満ではなく、「〇〇さんの業務を代行することで、自分の▲▲の仕事が進まないのがつらい」「休憩時間が取れないのが身体的にきつい」など、何が具体的な負担になっているのかを書き出してみるのも有効です。
適切な休息とリフレッシュを心がける
心身の疲労を溜め込まないためには、意識的な休息とリフレッシュが不可欠です。
- 質の高い睡眠を確保する:
睡眠不足は、判断力や集中力の低下、気分の落ち込みに繋がります。寝る前のカフェイン摂取を避ける、寝室の環境を整えるなど、質の高い睡眠をとる工夫をしましょう。 - 休憩時間をきちんと取る:
忙しくても、意識して短い休憩を挟むようにしましょう。席を立って軽くストレッチをする、窓の外を眺めるだけでも気分転換になります。昼休みはしっかりと確保し、食事だけでなくリラックスする時間も持ちましょう。 - 趣味や好きなことで気分転換する:
仕事以外の時間で、自分が心から楽しめることやリラックスできること(運動、音楽鑑賞、読書、友人とのおしゃべりなど)に時間を使うようにしましょう。 - バランスの取れた食事を心がける:
忙しいと食事が疎かになりがちですが、栄養バランスの取れた食事は、心身の健康を維持するための基本です。
上司や同僚に状況を相談する
一人で抱え込まず、信頼できる上司や同僚に現状の負担感や困っていることを相談してみましょう。
- 具体的な状況と自分の気持ちを伝える:
感情的に不満をぶつけるのではなく、「〇〇さんのフォロー業務が続いており、自分の業務に支障が出ています。正直、精神的にも疲れてきています」というように、客観的な状況と自分の率直な気持ちを伝えましょう。 - 具体的な解決策を一緒に考えてもらう:
「このままでは厳しいので、業務分担を見直していただけないでしょうか」「一時的にでもサポートメンバーを増やしていただけないでしょうか」など、具体的な要望や解決策のアイデアがあれば、それも合わせて伝えてみましょう。 - 相談する相手を選ぶ:
直属の上司が話しにくい場合は、さらに上の役職の人や、人事部、あるいは信頼できる先輩社員など、状況に応じて相談相手を選びましょう。
社内外の相談窓口を活用する(企業として整備されている場合)
企業によっては、従業員のメンタルヘルスサポートやハラスメント相談などのための窓口が設置されている場合があります。
- 人事・労務担当部署:
業務量の偏りや職場環境に関する問題について相談できます。 - 産業医・カウンセラー:
精神的なつらさやストレスについて、専門的なアドバイスを受けることができます。秘密は守られるので、安心して相談してみましょう。 - ハラスメント相談窓口:
もし休みが多い人への不満が、特定の個人への過度な負担強要や不公平な扱いに繋がっている場合は、ハラスメントに該当する可能性もあります。そのような場合は、専門の相談窓口に相談することを検討しましょう。また、働く人のメンタルヘルスに関する総合的な情報や相談窓口の案内は、厚生労働省の「こころの耳:働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト」でも得ることができます。
仕事で誰かをフォローすることは、チームワークの一環として大切なことです。しかし、それが過度な負担となり、自分自身の心身の健康を損なってしまっては元も子もありません。自分の限界を認識し、適切にSOSを出す勇気も必要です。「疲れた」と感じたら、それは休息や助けを求めるサインかもしれません。自分を大切にしながら、より良い働き方を見つけていきましょう。
まとめ:「よく休む人は信用出来ない」から「共に働く仲間」へ
「よく休む人は信用出来ない」という感情は、仕事のしわ寄せやコミュニケーション不足から生まれる、誰にでも起こりうる自然な反応かもしれません。この記事では、その心理的な背景や、休みが多いことが職場に与える影響、そしてその状況を改善するための具体的な方法について考えてきました。
大切なのは、一方的に誰かを責めるのではなく、なぜそのような状況が生まれるのかを多角的に理解しようと努めることです。頻繁に休む背景には、体調不良や家庭の事情など、目に見えない困難が隠れているかもしれません。また、仕事のしわ寄せは個人の問題だけでなく、チーム全体の業務分担や情報共有のあり方を見直すきっかけにもなり得ます。
この記事で提案したように、日頃からのオープンなコミュニケーション、業務の標準化や多能工化、そして何よりも「お互い様」という気持ちを持って協力し合う職場文化を育むことが、誤解や不信感を解消し、より働きやすい環境を作るための鍵となります。休む側も、周囲への感謝と配慮を忘れず、可能な範囲で情報共有を心がけることが、信頼関係の維持に繋がるでしょう。
「信用出来ない」という壁を取り払い、お互いの状況を理解し、支え合うことで、誰もが安心して能力を発揮できる職場を目指していきましょう。この記事が、その一助となれば幸いです。



