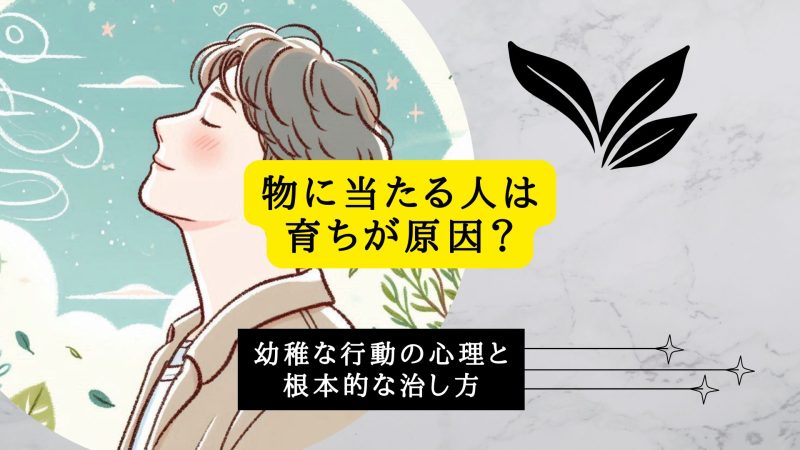カッとなって、つい物に当たってしまう。
そんな自分の行動に後悔したり、大切なパートナーの行動に恐怖を感じたりしていませんか。
その衝動的な行動の根っこには、実はあなたがこれまで歩んできた「物に当たる」という行為と人の育ちが、深く関係しているのかもしれません。

この記事では、なぜ物に当たってしまうのか、その行動の裏に隠された心理的な背景を、あなたの心に優しく寄り添いながら解き明かしていきます。
そして、その苦しい連鎖を断ち切り、穏やかな心を取り戻すための具体的な方法を、一つひとつ丁寧に解説します。
この記事を読み終える頃には、あなた自身やあなたの大切な人が、なぜそのような行動をとってしまうのかを深く理解し、未来へ向けた確かな一歩を踏み出せるはずです。
物に当たる人の育ちに見られる5つの特徴と心理的背景
なぜ、ある人は感情が揺さぶられたときに、物に当たってしまうのでしょうか。
その行動の背景には、本人の性格だけでなく、幼少期の経験や育った家庭環境が深く影響していることが少なくありません。
ここでは、物に当たるという行動につながりやすい、育ちに見られる特徴と、その裏に隠された心理について紐解いていきます。
愛情不足が原因?自己肯定感が低い人のSOSサイン
物に当たるという行動の根底には、低い自己肯定感が隠れているケースが非常に多く見られます。
そして、その自己肯定感の低さは、幼少期の愛情不足が原因となっている可能性があります。
条件付きの愛情で育った環境
子供の頃、テストで良い点を取った時だけ褒められたり、「良い子」でいる時だけ優しくされたりといった経験はありませんか。
このように、何かを達成したり、親の期待に応えたりした時にだけ愛情が与えられる環境を「条件付きの愛情」と呼びます。
こうした環境で育つと、「ありのままの自分では愛されない」「価値のある人間でなければならない」という考えが無意識のうちに刷り込まれてしまいます。
その結果、大人になってからも常に他人の評価を気にし、少しでも否定されたり、思い通りにいかなかったりすると、自分の存在価値そのものが脅かされたように感じてしまうのです。
その強い不安や恐怖が、行き場のない怒りとなり、物に向けられてしまうことがあります。
歪んだSOSサインとしての行動
自己肯定感が低い人は、自分の感情や欲求を素直に言葉で表現することが苦手な傾向があります。
「助けてほしい」「苦しい気持ちを分かってほしい」という切実な思いを抱えていても、「そんなことを言ったら迷惑がられる」「弱い人間だと思われたくない」という恐れが先に立ち、うまく伝えられません。
その結果、物に当たるという破壊的な行動を通して、「自分はこんなに苦しんでいるんだ!」という心の叫び(SOS)を発信している場合があります。
それは、本人も無意識のうちに行っている、不器用で歪んだコミュニケーションの形なのかもしれません。
物に当たるのは幼稚な行動?感情コントロールが苦手な背景
物に当たるという行為は、客観的に見れば幼稚な行動と映るかもしれません。
しかし、そのように感情のコントロールが苦手になってしまった背景にも、育った環境が関係している可能性があります。
感情表現を学ぶ機会の欠如
私たちは、成長の過程で、親や周囲の大人との関わりの中から、自分の感情をどのように扱い、どう表現すれば良いのかを学んでいきます。
しかし、親自身が感情の起伏が激しく、すぐに怒鳴ったり、物に当たったりする姿を日常的に見て育った場合、子供はそれが「怒りの表現方法」なのだと学習してしまいます。
これを心理学では「モデリング」と呼び、親の行動が無意識のうちに子供の行動パターンとして刷り込まれてしまうのです。
感情の抑圧が招く突然の爆発
一方で、「男の子は泣くもんじゃない」「わがままを言ってはいけない」というように、感情を表現すること自体を親から禁じられて育った人もいます。
このような環境では、子供は自分のネガティブな感情を「悪いもの」と認識し、心の中に無理やり押し込めるようになります。
しかし、抑圧された感情が消えてなくなるわけではありません。
心のコップに少しずつ溜まっていき、ある日、些細な出来事をきっかけに許容量を超え、ダムが決壊するように、溜め込んだ感情が爆発的な怒りとなって物に向けられるのです。
これは、自分の感情と健全に向き合う方法を知らないまま大人になってしまったがゆえの、苦しい表現方法と言えるでしょう。
周囲に「怖い」「ダサい」と思われる行動の裏にある心理とは?
物に当たる行動は、周囲の人に「怖い」という恐怖心や、「みっともない」「ダサい」といった嫌悪感を抱かせます。
しかし、その激しい行動とは裏腹に、本人の心の中は無力感や焦燥感で満ち溢れていることが少なくありません。
無力感を打ち消すための万能感
仕事で失敗した、パートナーに意見を否定されたなど、自分の力ではどうにもならない状況に直面したとき、人は強い無力感を覚えます。
この無力感は、自己肯定感が低い人にとっては耐え難い苦痛です。
その苦痛から逃れるための一時的な手段として、「物を破壊する」という行為が選択されることがあります。
硬いものを壊したり、大きな音を立てたりすることで、あたかも自分が状況をコントロールできたかのような錯覚(万能感)を抱き、傷ついた自尊心を一時的に回復させようとしているのです。
相手の反応をうかがう「試し行動」
特に、パートナーや家族など、親しい間柄で物に当たる場合、それは相手の愛情を確かめるための「試し行動」である可能性があります。
これは、幼少期に親の関心を引くために問題行動を起こした経験の延長線上にある行動です。
物に当たることで相手がどれだけ心配してくれるか、自分のことを見捨てないか、その反応を見て自分への愛情の深さを測ろうとしているのです。
しかし、この行動は相手を疲弊させ、関係を悪化させる危険な賭けであることに、本人は気づいていないことが多いのです。
女性で物に当たる人もいる?男女で異なるストレスの原因と特徴
一般的に「物に当たる」と聞くと、男性をイメージする人が多いかもしれません。
しかし、この問題は決して男性だけのものではなく、悩んでいる女性も少なくありません。
ただし、その引き金となるストレスの原因や、行動の現れ方には男女で異なる傾向が見られます。
性別によるストレス原因の違い
男性の場合、仕事上のプレッシャー、社会的な立場やプライドを傷つけられたことへの怒り、目標を達成できない焦りなどが、物に当たる行動の引き金になりやすいと言われています。
一方で女性の場合は、パートナーとの関係、育児の悩み、友人関係のもつれといった、人間関係における共感の欠如や孤独感が強いストレスとなり、感情の爆発につながることがあります。
また、ホルモンバランスの乱れが感情の起伏に影響を与え、衝動的な行動につながりやすい時期があることも特徴です。
物への当たり方の傾向
行動の現れ方にも違いが見られることがあります。
男性は、壁を殴る、ドアを蹴るなど、よりダイナミックで大きな力を誇示するような形で物に当たることが多いのに対し、女性は、化粧品を叩きつける、スマートフォンの画面を割る、クッションを何度も殴るなど、自分の持ち物や比較的小さなものを対象とすることが多い傾向があります。
これは、社会的に女性が攻撃性を直接的に表現することへの抵抗感が強いことの表れかもしれません。
普段は優しい人が物に当たるのはなぜ?隠された二面性
「外ではすごく優しい人なのに、家に帰ると些細なことでキレて物に当たる」
このような二面性に、パートナーは深い混乱と恐怖を感じます。
普段の優しい姿を知っているからこそ、豹変した時の衝撃は計り知れません。
この現象の背景には、外での過剰なストレスの抑圧があります。
「良い人」でいることの反動
職場や友人関係において、常に「良い人」「できる人」であろうと努め、自分の本音やネガティブな感情を押し殺している人は少なくありません。
特に、幼少期に親の期待に応える「良い子」でいることを求められてきた「アダルトチルドレン」の傾向がある人は、他者に気を使い、自分の感情を抑圧することが当たり前になっています。
しかし、そのストレスは着実に心の中に蓄積されていきます。
そして、唯一気を許せる「安全基地」であるはずの家庭内で、溜まりに溜まったストレスが些細なことをきっかけに爆発してしまうのです。
本人にとっては、外で抑え込んでいる分、家では感情を解放しているという感覚かもしれませんが、向けられる側にとっては、それは予測不能な暴力であり、モラハラやDV(ドメスティック・バイオレンス)に他なりません。
この二面性は、関係性に深刻な亀裂を生む、非常に危険なサインなのです。
物に当たる人の育ちを乗り越えるための改善策と周囲の接し方
物に当たるという行動の背景にある、育ちや心理を理解した上で、次に大切なのは「これからどうしていくか」という未来に向けた具体的な行動です。
この苦しい連鎖を断ち切るために、当事者自身ができること、そしてパートナーや同僚など、周囲の人ができることの両面から、具体的な改善策と接し方を見ていきましょう。
【当事者向け】今日からできるアンガーマネジメントと治し方
もしあなたが、自身の物に当たる行動に悩んでいるのなら、それは変わるための大きな一歩を踏み出している証拠です。
怒りの感情自体は、誰にでもある自然なもの。
大切なのは、その怒りとどう付き合い、どう表現するかです。
そのための技術が「アンガーマネジメント」です。
衝動をコントロールする「6秒ルール」
カッとなった時の怒りのピークは、実は長くは続きません。
研究によると、長くても6秒程度と言われています。
つまり、この最初の6秒をやり過ごすことができれば、衝動的な行動を大きく減らすことができるのです。
- その場を離れる: 怒りを感じたら、すぐにその部屋や場所から物理的に離れましょう。トイレに行く、ベランダで空気を吸うなど、少し環境を変えるだけで冷静になれます。
- 深呼吸する: 「1、2、3」で鼻から息を吸い、「4、5、6、7、8」で口からゆっくりと吐き出す。これを数回繰り返すことで、興奮した神経を落ち着かせることができます。
- 数字を数える: 1から10まで、あるいは100から逆になど、頭の中でゆっくりと数を数えることに集中するのも効果的です。
考え方を変えるトレーニング
私たちの怒りは、出来事そのものではなく、「その出来事をどう解釈したか」によって生まれます。
特に、「~すべきだ」「~であるはずだ」という強い思い込み(コアビリーフ)は、怒りの温床になりがちです。
例えば、「パートナーは私の気持ちを察して動くべきだ」という思い込みがあると、相手が期待通りに行動しないたびに怒りを感じてしまいます。
まずは自分がどんな時に「~べき」と考えているかに気づくことから始めましょう。
そして、「~べき」ではなく、「~だと嬉しいな」「~してくれたら助かるな」というように、期待や願望の形に言い換える練習をすることで、怒りの感情を和らげることができます。
気持ちを言葉で伝える練習(アサーション)
物に当たるのではなく、自分の気持ちを言葉で相手に伝える練習をしましょう。
この時、相手を責める「YOUメッセージ(あなたは~だ)」ではなく、自分の気持ちを主語にする「Iメッセージ(私は~だ)」で伝えることがポイントです。
例えば、「なんで分かってくれないんだ!」と怒鳴る代わりに、「そう言われると、私は悲しい気持ちになる」「私はあなたの助けが必要だと感じている」と伝えるのです。
すぐにはできなくても、意識して続けることで、建設的なコミュニケーションが可能になります。
物に当たるのは病気のサイン?精神科やカウンセリングも視野に
物に当たるという行動が、どうしても自分の意志でコントロールできない、あるいはその頻度や激しさが増している場合、その背景に何らかの精神的な病気が隠れている可能性も考えられます。
考えられる精神的な背景
例えば、以下のようなケースが考えられます。
- 間欠性爆発性障害: 些細なきっかけで、釣り合わないほどの激しい攻撃性(言葉の暴力や物理的な破壊)が繰り返し爆発的に現れる状態です。
- ADHD(注意欠如・多動症): 特性の一つである「衝動性」が、感情のコントロールの難しさにつながり、カッとなりやすい傾向が見られることがあります。
- パーソナリティ障害: 他者との関係性の築き方や、感情のコントロール、自己イメージなどに著しい偏りが見られ、その結果として衝動的な行動が現れることがあります。
ただし、これらの判断は専門的な知識を持つ医師でなければできません。
インターネットの情報だけで「自分はこの病気かもしれない」と自己判断することは非常に危険です。
不正確な自己診断は、かえって不安を増大させたり、適切な対処から遠ざけたりする原因になります。
カウンセリングという選択肢
病気の診断とは別に、カウンセリングを利用することも非常に有効な手段です。
カウンセラーは、あなたの味方です。
安全な環境で、あなたがこれまで誰にも言えなかった、育った家庭環境での辛い経験や、親との関係で感じてきた苦しみをじっくりと聴いてくれます。
自分の過去と向き合い、傷ついたままの幼い自分(インナーチャイルド)を癒していくプロセスは、感情のコントロールを取り戻し、自己肯定感を育む上で大きな助けとなるでしょう。
職場で物に当たる人へのNG対応と、身を守るための対処法
家庭だけでなく、職場で物に当たる人に遭遇し、恐怖やストレスを感じている人もいるでしょう。
自分の身を守り、状況を悪化させないためには、適切な対処法を知っておくことが重要です。
まずは自分の安全確保を最優先に
職場で誰かが物に当たり始めたら、何よりもまず自分の安全を確保してください。
机の下に隠れる、その部屋から静かに出るなど、物理的に距離を取ることが第一です。
逆上した相手に「やめてください」と正面から立ち向かうのは非常に危険です。
やってはいけないNG対応
- 一緒になって騒ぐ・同調する: 「大変ですね」「気持ち分かります」などと安易に同調すると、相手は「この行動は認められた」と勘違いし、行動をエスカレートさせる可能性があります。
- 過度に怯えた態度を見せる: 相手は、人が怖がる様子を見て、自分が優位に立ったと感じ、さらに威圧的な行動を強めることがあります。
- 見て見ぬふりをする: 無視を続けると、問題が放置され、ハラスメントが常態化してしまう危険性があります。
具体的な対処法のステップ
- 記録を取る: いつ、どこで、誰が、何に対して、どのように物に当たったか、具体的な状況を日時と共にメモしておきましょう。これは後に会社へ相談する際の客観的な証拠となります。
- 信頼できる上司や人事部に相談する: 一人で抱え込まず、必ず第三者に相談してください。この行動は、業務の安全配慮義務違反やパワーハラスメントに該当する可能性があります。会社として対応してもらうことが重要です。
- 冷静な時に伝える(Iメッセージで): もし可能であれば、相手が落ち着いている時に「先日の〇〇の件ですが、大きな音がして、私はとても怖く感じました。業務に集中できなくなるので、控えていただけると助かります」というように、あくまで「私」を主語にして、自分の気持ちと業務への影響を冷静に伝えましょう。
「人に当たるよりマシ」は本当?その考えが危険な理由
物に当たる当事者の中には、「人に当たるよりマシだ」と考え、自分の行動を正当化しようとする人がいます。
一見、その理屈は通っているように聞こえるかもしれません。
しかし、この考え方は非常に危険であり、根本的な問題から目をそらす言い訳に過ぎません。
行動がエスカレートする危険性
物への破壊行動は、繰り返すうちにだんだんと慣れが生じ、より強い刺激を求めるようになります。
最初は小物を投げるだけだったのが、やがて壁を殴るようになり、高価な家電を壊すようになり…と、行動がどんどんエスカレートしていく危険性があります。
そして、その矛先がいつか人に向かう可能性はゼロではありません。
物への暴力と人への暴力は、地続きなのです。
精神的なDV(ドメスティック・バイオレンス)に他ならない
たとえ相手の身体に直接触れなくても、目の前で物に当たる行為は、相手を恐怖で支配し、精神的に追い詰める紛れもない暴力(精神的DV、モラハラ)です。
大きな音を立てて威嚇したり、大切なものを壊したりすることで、「言うことを聞かないと、次はお前に危害が及ぶかもしれない」という無言のメッセージを相手に送りつけているのです。
被害者は常に緊張を強いられ、心は深く傷つき、やがては「自分が悪いから相手を怒らせてしまうんだ」と自分を責めるようになってしまいます。
「人に当たるよりマシ」という考えは、この精神的暴力の深刻さを見過ごしており、この考えを持つ限り、自分の行動が相手をどれだけ深く傷つけているかに気づくことはできません。
パートナーや家族が物に当たる場合の適切な距離感と接し方
最も身近な存在であるパートナーや家族が物に当たる場合、その対応は非常に難しく、深刻な悩みを抱えている方も多いでしょう。
相手を思いやる気持ちと、自分自身の心と安全を守ることのバランスが重要になります。
冷静な時に気持ちを伝える
相手が物に当たっている最中に、何を言っても火に油を注ぐだけです。
話をするのは、必ずお互いが冷静な時を選びましょう。
その際、相手を責めるのではなく、「この前のことだけど、あなたが物に当たるのを見ると、私はとても悲しくて、怖い気持ちになるんだ」「あなたのことが大切だから、すごく心配している」というように、愛情や心配をベースに、自分の気持ち(Iメッセージ)を正直に伝えることが大切です。
許容できないライン(境界線)を明確にする
優しさや愛情だけでは、状況が改善しないこともあります。
時には、自分を守るために毅然とした態度で「境界線」を引くことが必要です。
「私は、この家で安心して暮らしたい。だから、もし次にあなたが物に当たるようなことがあれば、私は自分の心と安全を守るために、この家を一時的に離れます」
このように、「もしあなたが〇〇をしたら、私は△△します」という形で、許容できない行動と、その際に自分が取る行動を明確に伝えます。
これは相手を脅すためではなく、自分の尊厳を守り、相手に問題の深刻さを理解してもらうための重要なステップです。
相手の問題と自分の問題を切り分ける
「私がもっとうまくやれば、彼(彼女)を怒らせずに済むはずだ」
「私が支えてあげなければ、この人はダメになってしまう」
このように、相手の問題をすべて自分が背負い込んでしまうことを「共依存」と言います。
あなたは、相手の感情の責任を負う必要はありません。
物に当たるという問題は、根本的には相手自身が自分の育ちや過去と向き合い、乗り越えるべき課題なのです。
過度に干渉しすぎず、相手が自分の問題として認識し、変わろうと努力するのを見守る姿勢も時には必要です。
そして何より、あなた自身の心のケアを忘れないでください。
信頼できる友人に話を聞いてもらったり、必要であれば公的な相談機関などを利用したりして、一人で抱え込まないことが大切です。
もし、あなたがパートナーからの暴力によって心や身体の安全に不安を感じているなら、一人で抱え込まずに専門の相談窓口を頼ってください。
内閣府が運営する「DV相談+(プラス)」では、24時間いつでも専門の相談員に電話やチャットで無料相談ができます。
まとめ:「物に当たる人」の「育ち」との関連性を理解し、未来へ踏み出す
物に当たるという行動は、単なる性格の問題ではなく、その人の育ちや幼少期の経験と深く結びついている可能性があります。
愛情不足が招いた自己肯定感の低さや、感情をコントロールする方法を学ぶ機会がなかった家庭環境が、大人になってからの苦しみとして表れているのかもしれません。
この問題は、幼稚な行動と一言で片付けられるものではなく、その裏には本人も気づいていないSOSサインが隠されています。
もしあなたが当事者であるなら、アンガーマネジメントを学び、自分の気持ちを言葉で伝える練習を始めることが、この苦しい連鎖を断ち切るための大きな一歩となります。
また、あなたの周りの大切な人がこの問題で苦しんでいるなら、相手を非難するのではなく、冷静に自分の気持ちを伝え、安全な境界線を引くことが、あなた自身と相手の両方を守ることにつながります。
過去の育ちを変えることはできませんが、これからの未来を穏やかに築いていくことは、今この瞬間から可能なのです。