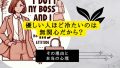職場で隣の席の同僚がこっくりこっくり…、会議中にウトウトしている上司…。
真面目に仕事に取り組んでいる自分からすると、仕事中に寝てる人を見ると、ついイライラしてしまいますよね。
「どうして自分だけがこんなに頑張っているんだろう」「給料をもらっているのにプロ意識がないのでは?」そんな不満や疑問が湧いてくるのも無理はありません。
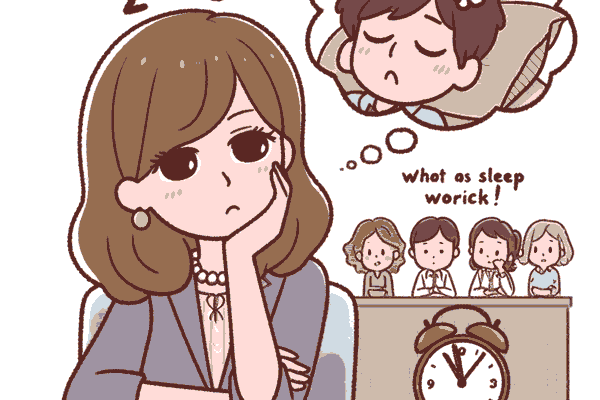
この記事では、なぜ仕事中に寝ている人を見るとイライラしてしまうのか、その心理的な背景を探るとともに、寝てしまう人側の心理や考えられる原因、そして私たちがどのように対処していけば良いのか、そのヒントを一緒に考えていきましょう。
このイライラを少しでも解消し、より良い職場環境を目指すための一歩となるはずです。
仕事中寝てる人にイライラ…その心理と根本的な原因とは?
職場で誰かが寝ている姿を目にすると、多くの方が少なからずネガティブな感情を抱くのではないでしょうか。そのイライラの背景には、私たちのどのような心理が働いているのでしょうか。また、寝てしまう人にはどのような事情があるのかもしれません。ここでは、まずその根本的な部分を探っていきましょう。

なぜ?仕事中に寝てる人を見るとイライラしてしまう心理的背景
「自分はこんなに一生懸命やっているのに…」仕事中に寝ている人を見たとき、このように感じてしまうのは自然なことです。このイライラの根底には、いくつかの心理的な要因が考えられます。
- 公平性の侵害による不満: 最も大きな理由は、「不公平感」ではないでしょうか。同じように給料をもらい、同じ時間を職場で過ごしているにもかかわらず、一方が真面目に業務に取り組んでいるのに対し、もう一方が寝ているという状況は、努力が正当に評価されていない、あるいは自分だけが損をしているという感覚を引き起こします。この不公平感は、仕事のモチベーション低下にも繋がりかねません。
- 業務への支障と負担増への懸念: 寝ている人がいることで、その人の分の業務が滞ったり、周囲がカバーしなければならなくなったりする可能性があります。特にチームで仕事を進めている場合、一人の非協力的な態度は全体の進捗に影響を与え、他のメンバーの負担増に直結します。このような状況は、当然ながらストレスの原因となります。
- 職場の規律や雰囲気の悪化への危機感: 職場には一定の規律があり、その中で協力して業務を遂行することが求められます。仕事中に堂々と居眠りをする行為は、その規律を乱し、職場の雰囲気を悪化させる可能性があります。「あの人が寝ていても許されるなら…」と、他の社員のモチベーション低下や規律の緩みに繋がることを懸念する人もいるでしょう。
- プロ意識への疑問と理解不能感: 「仕事とは責任を持って取り組むべきもの」という価値観を持つ人にとっては、仕事中に寝るという行為はプロ意識に欠けると映り、理解しがたいものです。なぜそのような行動をとるのかが理解できないために、余計にイライラが増幅されることもあります。
- 過去の自分の経験との比較: 自分が新人時代に必死で仕事を覚えようと努力していた経験や、忙しい時期に寝る間も惜しんで働いた経験などがあると、「自分はあんなに頑張ったのに、なぜあの人は…」と、過去の自分と相手を比較してしまい、より強い不満を感じることもあります。
これらの心理的背景が複雑に絡み合い、仕事中に寝てる人に対するイライラという感情を生み出しているのです。
実は複雑?仕事中に寝てしまう人の隠された心理パターン
一方で、仕事中に寝てしまう人には、どのような心理が働いているのでしょうか。単純に「やる気がない」「怠けている」と片付けてしまう前に、その背景にあるかもしれない心理パターンを考えてみましょう。
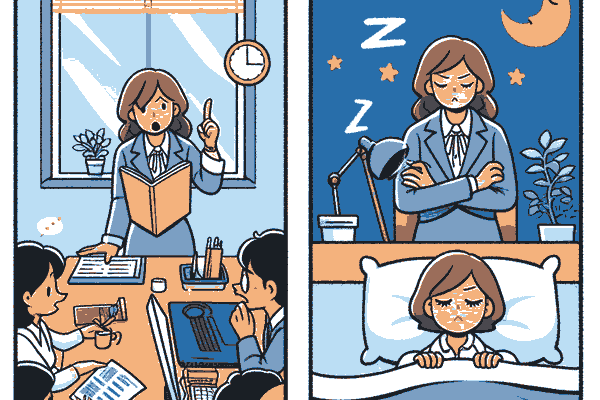
- 仕事への無気力・諦め:
- 仕事内容への不満やミスマッチ: 現在の仕事内容に興味が持てなかったり、自分の能力と合わないと感じていたりする場合、仕事への意欲が低下し、無意識のうちに眠気という形で現れることがあります。
- 努力が報われないと感じる: 頑張っても評価されない、昇進や昇給の機会がないなど、将来への希望が見いだせない状況では、仕事に対するモチベーションを維持することが難しくなり、諦めの感情から無気力状態に陥ることがあります。このモチベーション低下する社員の問題は、本人だけの責任とは言えない場合もあります。
- 現実逃避としての睡眠:
- 職場の人間関係のストレス: 上司との関係がうまくいかない、同僚からのプレッシャーを感じるなど、職場の人間関係に悩んでいる場合、そのストレスから逃れるために睡眠に逃避してしまうことがあります。
- 過度なプレッシャーやノルマ: 達成困難な目標や厳しいノルマに常にさらされていると、精神的に追い詰められ、現実から目を背けたいという心理が働くことがあります。
- 緊張感の欠如・慣れによる気の緩み:
- 単調なルーティンワーク: 毎日同じ作業の繰り返しで刺激が少ない場合、仕事に対する緊張感が薄れ、集中力が低下しやすくなります。
- 「見つからなければ大丈夫」という甘え: これまで寝ていても特に注意されなかった経験があると、「少しくらいならバレないだろう」という安易な考えから、居眠りが習慣化してしまうことがあります。
- 助けを求められない心理:
- プライドの高さや周囲への遠慮: 責任感が強い人やプライドが高い人ほど、自分の弱みや困難な状況を周囲に相談できず、一人で抱え込んでしまうことがあります。その結果、心身の疲労が限界に達し、眠気として現れることも考えられます。
- 「相談しても無駄」という諦め: 過去に相談しても解決しなかった経験があると、誰にも頼ることができず、問題を深刻化させてしまうことがあります。
このように、仕事中に寝てしまう背景には、本人の怠慢だけでなく、仕事や職場環境に対する何らかのサインが隠れている可能性も考慮する必要があります。
単なる怠慢だけじゃない?仕事中に眠くなる様々な原因
仕事中の眠気は、本人の意思とは関係なく襲ってくることもあります。その原因は多岐にわたり、単純に「怠けているから」と決めつけられないケースも少なくありません。

睡眠の質の低下や慢性的な睡眠不足
最も直接的な原因は、やはり睡眠不足です。
- プライベートでの夜更かし: スマートフォンやゲーム、動画視聴などで夜遅くまで起きている生活が習慣化していると、日中の眠気に直結します。
- 睡眠の質の低下: ストレスや不規則な生活、寝る前のカフェイン摂取や飲酒などが原因で、睡眠時間が十分でも眠りが浅く、疲れが取れていないことがあります。
- 育児や介護など家庭の事情: 小さな子供の夜泣き対応や、家族の介護などで、まとまった睡眠時間を確保できない場合もあります。
生活習慣の乱れ
日々の生活習慣も、日中のパフォーマンスに大きく影響します。
- 食生活の偏り: 血糖値の急激な変動を招く食事(例:糖質の多い食事の後の眠気)や、栄養バランスの悪い食事は、倦怠感や眠気を引き起こすことがあります。
- 運動不足: 適度な運動は血行を促進し、脳の活性化にも繋がりますが、運動不足は体力低下を招き、疲れやすさや日中の眠気を感じやすくさせます。
- 不規則な勤務形態: シフト勤務や夜勤など、生活リズムが不規則になりがちな仕事は、体内時計が乱れやすく、日中に強い眠気を感じることがあります。
仕事内容や職場環境
意外かもしれませんが、仕事内容や職場の環境も眠気を誘発する要因となり得ます。
- 単調な作業の連続: 同じ作業を長時間続けていると、脳への刺激が少なくなり、集中力が低下して眠気を感じやすくなります。
- 静かすぎる、または騒がしすぎる環境: あまりにも静かな環境はリラックスしすぎて眠気を誘い、逆に騒がしすぎる環境は集中力を削ぎ、疲労から眠気に繋がることがあります。
- 室温や換気の問題: 暖房が効きすぎた暖かい部屋や、二酸化炭素濃度が高い換気の悪い部屋も、眠気を引き起こしやすいと言われています。
心身の疲労とストレス
見過ごされがちですが、心身の疲労も大きな原因です。
- 長時間労働や過度な業務量: 連日の残業や休日出勤などで肉体的な疲労が蓄積すると、日中の集中力維持が困難になります。
- 精神的なストレス: 仕事上のプレッシャー、人間関係の悩み、将来への不安などが続くと、自律神経のバランスが乱れ、質の高い睡眠が得られにくくなったり、日中に強い倦怠感や眠気を感じたりすることがあります。この仕事中 寝てる人 ストレスの問題は、周囲だけでなく本人にとっても深刻です。
これらの原因を理解することで、寝ている人に対して少し違った視点を持つことができるかもしれません。
もしかして病気のサイン?注意すべき居眠りとその可能性
ほとんどの居眠りは、前述したような生活習慣や一時的な疲労が原因ですが、中には何らかの病気が原因で仕事中に寝てしまうケースも考えられます。特に、十分な睡眠時間を取っているはずなのに日中の眠気が異常に強い、自分ではコントロールできないほどの眠気に襲われる、といった場合は注意が必要です。
- 睡眠時無呼吸症候群(SAS): 睡眠中に何度も呼吸が止まったり浅くなったりする病気です。これにより睡眠の質が著しく低下し、日中に強い眠気や倦怠感、集中力の低下などを引き起こします。大きないびきや起床時の頭痛なども特徴的な症状です。
- ナルコレプシー: 日中に突然、場所や状況を選ばずに耐え難い眠気に襲われて眠り込んでしまう神経系の病気です。感情が高ぶったときに体の力が抜ける「情動脱力発作」などを伴うこともあります。
- その他の睡眠障害: むずむず脚症候群や周期性四肢運動障害など、夜間の睡眠を妨げる病気が原因で日中の眠気を引き起こすこともあります。
- 精神疾患の症状として: うつ病や双極性障害などの精神疾患では、過眠の症状が現れることがあります。意欲の低下や気分の落ち込みなど、他の症状も伴うことが多いです。
- 内科系の疾患や薬の副作用: 貧血や甲状腺機能低下症などの病気や、服用している薬の副作用で眠気が出やすくなることもあります。
もし同僚の居眠りが「ひどい」と感じるレベルで、本人が辛そうにしていたり、明らかに異常な眠気を訴えていたりするような場合は、単なる怠慢と決めつけず、何らかの健康上の問題を抱えている可能性も視野に入れる必要があるかもしれません。ただし、他人の健康状態について憶測で判断したり、無責任な発言をしたりすることは避けるべきです。心配な場合は、本人に体調を気遣う言葉をかける程度に留め、専門的な判断は医療機関に委ねるのが適切です。
仕事中寝てる人へのイライラを解消!具体的な対処法と注意点
仕事中に寝ている人を目にすると、イライラしたり、どう対応すべきか悩んだりしますよね。しかし、感情的に注意したり、放置したりするだけでは、問題の解決には繋がりません。ここでは、寝ている人への具体的な対処法や、注意する際のポイント、そして自分自身のイライラと上手に付き合うためのヒントをご紹介します。
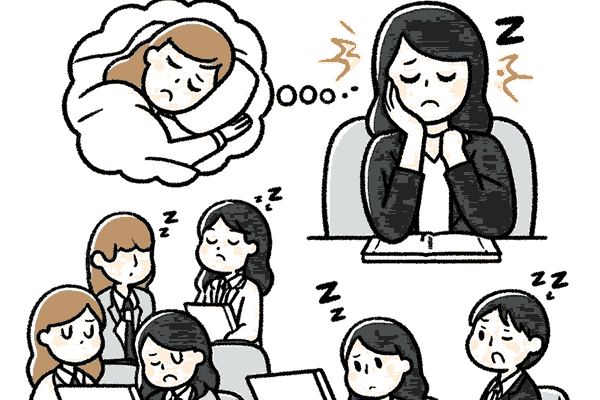
いきなり注意はNG?寝てる人へのスマートな起こし方と伝え方
寝ている人に気づいたとき、いきなり大声で注意したり、周囲に聞こえるように非難したりするのは避けたいものです。相手を不必要に刺激し、職場の雰囲気を悪化させるだけでなく、逆効果になる可能性もあります。では、どのように対応するのがスマートなのでしょうか。
状況の確認と声かけのタイミング
まずは、本当に寝ているのか、それとも体調が悪くてうつむいているのかなど、状況を少し観察しましょう。明らかに熟睡しているようであれば、起こす必要があるかもしれません。声をかける際は、相手のプライバシーに配慮し、できるだけ周囲に人がいないタイミングや場所を選ぶのが理想的です。
心配する気持ちを伝える起こし方
高圧的な態度ではなく、相手を気遣う言葉を選ぶことが大切です。
- 「〇〇さん、大丈夫ですか?少し顔色が悪いように見えますが…」
- 「疲れているみたいだけど、何か手伝えることある?」
- 「ちょっと肩を叩いてみるね。〇〇さん、起きてる?」
このように、心配する気持ちを前面に出すことで、相手も素直に状況を受け入れやすくなります。
具体的な仕事の話で自然に起こす
直接的に「寝てますよ」と指摘しにくい場合は、仕事に関連する用件で声をかけるのも一つの方法です。
- 「〇〇さん、すみません、先ほどの△△の件で少し確認したいことがあるのですが…」
- 「〇〇さん、お忙しいところ申し訳ないのですが、この資料について教えていただけますか?」
このように、あくまで業務上の必要性から声をかけたという形をとれば、相手も気まずさを感じにくく、自然に目を覚ますきっかけになります。
注意する際の言葉選びと伝え方のポイント
もし、どうしても注意が必要だと判断した場合でも、伝え方には細心の注意を払いましょう。
- 穏やかな口調で、感情的にならない: イライラした気持ちをそのままぶつけるのではなく、冷静に、落ち着いたトーンで話すことが重要です。
- 具体的に、客観的な事実を伝える: 「いつも寝ていますよね」といった曖昧な表現ではなく、「先日の会議中や、今日の午前中にもお見受けしましたが」のように、具体的な状況を伝える方が、相手も問題を認識しやすくなります。
- 影響を伝える(ただし、責める口調は避ける): 「〇〇さんが寝ていると、チームの士気に関わるかもしれないと心配しています」や「業務が滞ってしまうと、周りにも影響が出る可能性があります」など、個人的な感情ではなく、周囲への影響を伝える形が良いでしょう。
- 改善を期待する言葉を添える: 「もし何か事情があるなら聞かせてほしいですし、一緒に改善していけたらと思っています」のように、前向きな姿勢を示すことも大切です。
重要なのは、相手を追い詰めるのではなく、問題解決に向けたコミュニケーションを心がけることです。
改善が見られない…上司に相談する際のポイントと伝え方のコツ
一度や二度声をかけたり、注意したりしても改善が見られない場合や、あまりにも居眠りがひどく業務に支障が出ている場合は、上司に相談することも検討しましょう。しかし、告げ口と捉えられないように、伝え方には工夫が必要です。
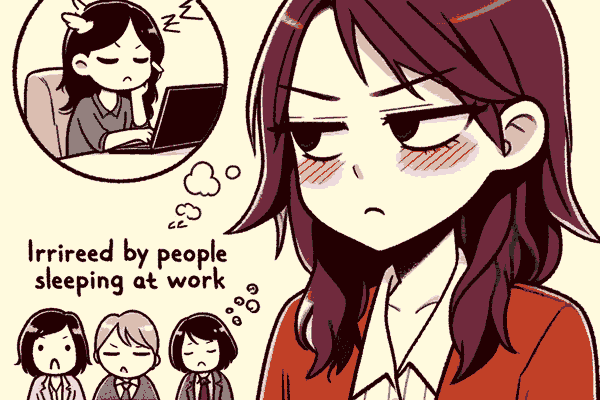
相談前の準備:客観的な記録
上司に相談する前に、感情的に訴えるのではなく、客観的な事実を整理しておくことが重要です。
- いつ、どこで、どのくらいの頻度で寝ているのか: 具体的な日時や状況を記録しておくと、説明がしやすくなります。(例:〇月〇日の会議中、〇月〇日の午後〇時頃デスクで、など)
- 業務への具体的な影響: 実際にどのような支障が出ているのか、具体的に伝えられるように準備します。(例:電話応対ができていない、締め切りに間に合わないことがある、周囲の社員がその分をカバーしている、など)
- これまでにとった対応(もしあれば): 本人に声をかけたことがあるか、その時の相手の反応はどうだったかなども伝えると、状況がより正確に伝わります。
上司への伝え方のポイント
- 相談というスタンスで: 「〇〇さんのことで困っているので、どうすれば良いかご相談したいのですが」というように、あくまでも助言を求める姿勢で話しましょう。一方的に非難したり、罰則を求めたりするような態度は避けるべきです。
- 個人的な感情ではなく、組織の問題として: 「私がイライラするから」ではなく、「チームの生産性が下がっている」「他の社員のモチベーションに影響が出ている」など、組織全体の問題として提起することで、上司も状況を重く受け止めやすくなります。
- 具体的な事実を淡々と伝える: 感情的にならず、準備した記録に基づいて、具体的な事実を冷静に伝えましょう。憶測や噂話は避け、あくまで自分が直接見聞きした範囲で話すことが大切です。
- 解決に向けた前向きな姿勢を示す: 「職場環境をより良くしたい」「チームとして成果を上げていきたい」という前向きな気持ちを伝えることで、建設的な話し合いに繋がりやすくなります。
上司に相談することは、決してネガティブなことではありません。職場環境の改善のための一つの手段であり、問題を抱え込まずに適切な対応を求めることは重要です。「仕事中寝てる人を上司に相談」と悩んでいる方は、これらのポイントを参考にしてみてください。
仕事中に寝るとクビになる?気になる処遇と法的な側面
「仕事中に寝てしまうのはクビになりますか?」という疑問は、寝ている本人だけでなく、周囲の社員にとっても気になるところでしょう。結論から言うと、一度や二度の居眠りで即座に解雇(クビ)になるケースは稀です。
就業規則の確認
まず基本となるのは、会社の就業規則です。多くの会社では、職務専念義務や服務規律に関する規定があり、仕事中の居眠りがこれらの義務に違反すると判断される可能性があります。就業規則には、違反行為に対する懲戒処分の種類(けん責、減給、出勤停止、解雇など)が定められています。
懲戒処分のプロセス
一般的に、企業が従業員を懲戒処分する際には、段階を踏むことが多いです。
- 注意・指導: まずは口頭や文書で注意・指導が行われます。
- 始末書の提出: 改善が見られない場合、始末書の提出を求められることがあります。
- 軽い懲戒処分: けん責(厳重注意)や減給などの処分が科されることがあります。
- 重い懲戒処分: 度重なる違反や、業務への重大な支障、改善の見込みがないと判断された場合に、出勤停止や諭旨解雇、懲戒解雇といった重い処分が検討されます。
つまり、いきなり解雇ということは少なく、改善の機会が与えられるのが一般的です。ただし、居眠りの頻度や時間、業務への影響度、本人の態度などによっては、より厳しい処分が下される可能性もゼロではありません。
「仕事中に寝ると給料はもらえませんか?」という疑問
労働契約において、労働者は労働力を提供する義務があり、使用者はその対価として賃金を支払う義務があります。これを「ノーワーク・ノーペイの原則」と言い、働いていない時間に対しては給料を支払う義務がないというのが基本的な考え方です。そのため、仕事中に寝ていた時間が労働時間として認められず、その分の給与がカットされる可能性は理論上あり得ます。しかし、実際にどの程度厳密に運用されるかは、会社の規定や状況によります。
処遇について不安を感じているかもしれませんが、まずは就業規則を確認し、会社がどのような対応をとる可能性があるのかを理解しておくことが大切です。
職場の空気を悪化させない!イライラとの上手な付き合い方とストレスケア
仕事中に寝ている人を見てイライラしてしまうのは、ある程度仕方のないことです。しかし、そのイライラに振り回されて自分自身が疲弊してしまったり、職場の雰囲気を悪くしてしまったりするのは避けたいものです。ここでは、自分の感情と上手に付き合い、ストレスを軽減するためのヒントをご紹介します。
自分の感情を客観的に見つめる
なぜ自分はこんなにイライラするのだろう?と、一度立ち止まって自分の感情を客観的に見つめてみましょう。「不公平だと感じるから」「仕事が増えるのが嫌だから」「サボっているように見えるのが許せないから」など、イライラの根源が見えてくるかもしれません。自分の感情を理解することは、コントロールするための第一歩です。
短期的な気分転換を取り入れる
イライラを感じ始めたら、その場から少し離れて気分転換を図るのも有効です。
- 短い休憩を取る: トイレに立つ、給湯室でお茶を入れるなど、数分間だけでも仕事から離れてみましょう。
- 深呼吸をする: ゆっくりと深呼吸をすることで、高ぶった神経を落ち着かせる効果が期待できます。
- 軽いストレッチをする: 同じ体勢で長時間作業をしていると、体も心も凝り固まってしまいます。肩を回したり、背伸びをしたりするだけでもスッキリします。
自分の仕事に集中する
他人の行動を変えることは難しいですが、自分の意識をコントロールすることは可能です。寝ている人が気になっても、「自分は自分の仕事に集中しよう」と意識を切り替える努力をしてみましょう。自分のタスクに没頭することで、イライラを感じる暇がなくなるかもしれません。
信頼できる人に話を聞いてもらう
一人で抱え込まず、信頼できる同僚や上司、友人や家族などに話を聞いてもらうのも良い方法です。必ずしも解決策が見つからなくても、誰かに話すだけで気持ちが楽になることはよくあります。ただし、愚痴がエスカレートして悪口にならないよう、話す相手や内容は慎重に選びましょう。
問題の切り分けと割り切りも大切
仕事中に寝ている人がいるという問題は、果たして自分一人の力で解決できる問題でしょうか? 場合によっては、個人の努力だけではどうにもならない組織的な問題や、本人の個人的な事情が深く関わっていることもあります。「これは自分の問題」「これは相手の問題」「これは会社が対応すべき問題」と、ある程度問題を切り分けて考え、自分ではどうにもできないことに対しては、「仕方がない」と割り切ることも、時には必要です。
ストレスマネジメントを意識する
日頃からストレスを溜め込まないように、自分なりのストレス解消法を見つけておくことも大切です。趣味に没頭する時間を作る、適度な運動をする、質の高い睡眠を心がけるなど、心身のバランスを整えることを意識しましょう。アンガーマネジメントのテクニックを学んでみるのも良いかもしれません。
もし、職場のストレスが深刻で、自分だけでは抱えきれないと感じたり、周囲の人の様子が心配だったりする場合には、厚生労働省の「こころの耳」のような専門機関の情報を参考にしてみるのも一つの方法です。一人で悩まず、適切なサポートを得ることも考えてみましょう。
仕事中に寝てる人へのイライラは、誰にでも起こりうる感情です。大切なのは、その感情に飲み込まれず、建設的な対処法を見つけ出し、自分自身の心の健康も守ることです。
まとめ:仕事中寝てる人へのイライラと向き合い、より良い職場環境へ
この記事では、「仕事中寝てる人にイライラ」という多くの方が抱える悩みをテーマに、その心理的な背景や寝てしまう人の側の事情、そして具体的な対処法について掘り下げてきました。
仕事中に寝ている人を見るとイライラしてしまうのは、不公平感や業務への支障、職場の規律への懸念など、様々な心理が働くためです。一方で、寝てしまう側にも、仕事への無気力や現実逃避、あるいは睡眠不足や健康上の問題といった、単純な怠慢とは言えない原因が隠されている可能性も理解しておく必要があります。
イライラを解消し、状況を改善するためには、まず感情的に注意するのではなく、相手を気遣う言葉でスマートに起こしたり、仕事の話で自然に気づかせたりすることが大切です。それでも改善が見られない場合は、客観的な事実を整理した上で上司に相談することも有効な手段となります。その際、個人的な感情ではなく、組織の問題として提起することがポイントです。
また、「仕事中に寝るとクビになるのか」という疑問については、就業規則に基づき段階的な指導や処分が行われるのが一般的であり、即座に解雇となるケースは稀ですが、状況によっては厳しい判断が下される可能性も理解しておく必要があります。
最も重要なのは、寝ている人への対応だけでなく、自分自身のイライラと上手に付き合い、ストレスを溜め込まないことです。気分転換を図ったり、信頼できる人に話を聞いてもらったりしながら、自分の仕事に集中する意識を持つことも大切です。
仕事中に寝ている人がいるという問題は、個人の問題だけでなく、職場環境や組織全体の課題が関係していることも少なくありません。この記事でご紹介した視点や対処法が、皆さんのイライラを少しでも和らげ、より働きやすい職場環境を築くための一助となれば幸いです。一方的な見方にとらわれず、建設的なコミュニケーションを心がけることで、問題解決の糸口が見つかるかもしれません。