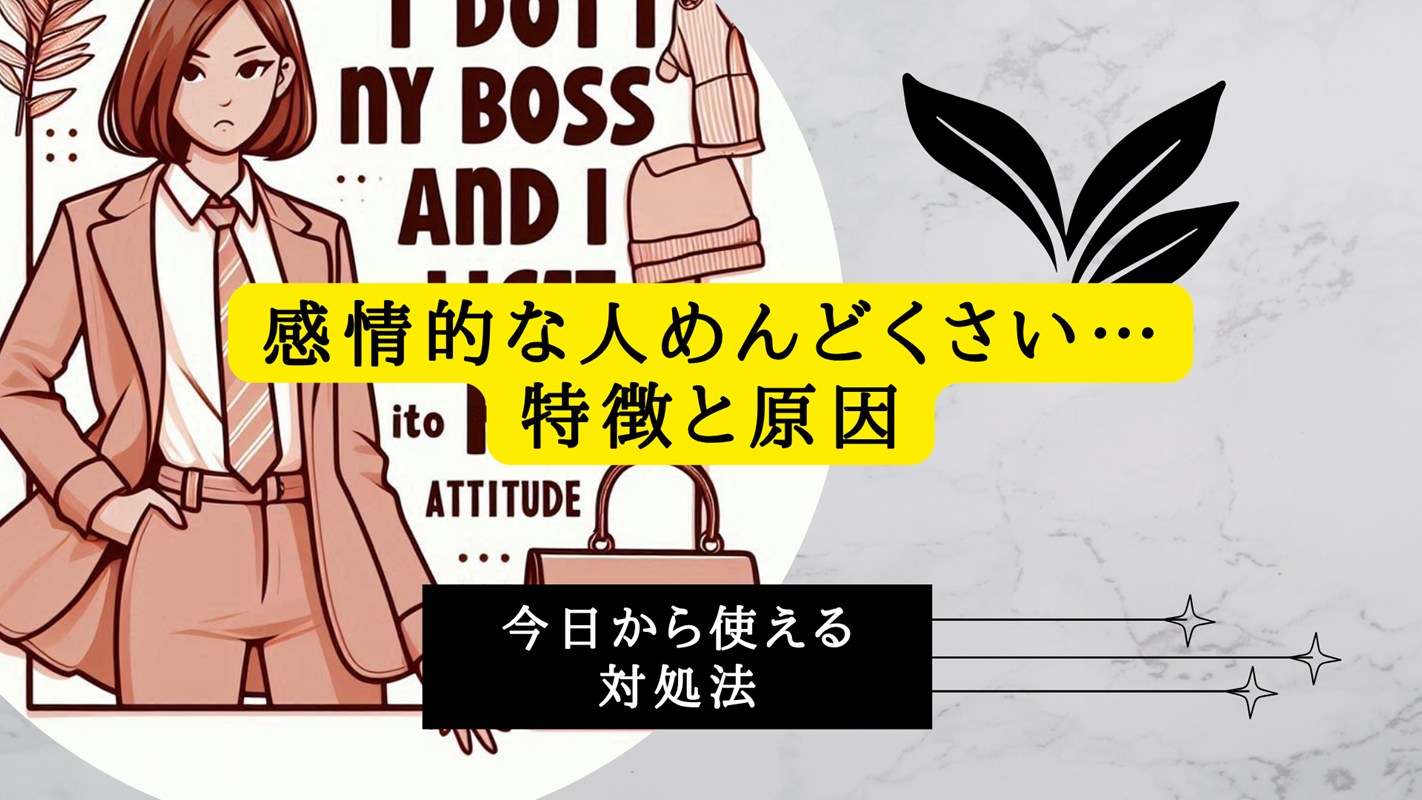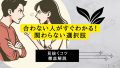「感情的な人との関わりって、なんだかすごく疲れる…」
「どうしてあんなに感情的なんだろう?」
そう感じて、ため息をついているあなたへ。
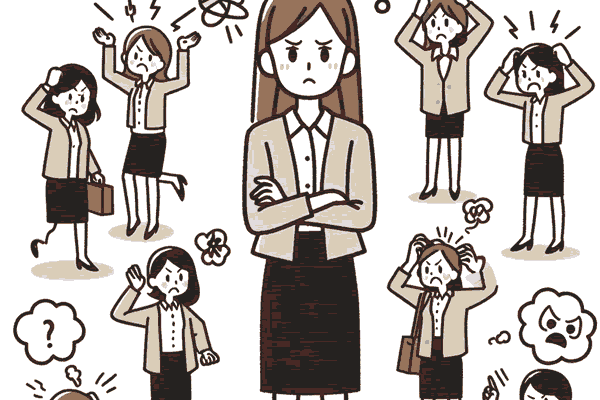
この記事は、そんなあなたの悩みに寄り添い、感情的な人に「めんどくさい」と感じる理由と、明日から少しでも楽に関われるようになるための具体的な対処法を分かりやすく解説します。
この記事を読めば、なぜあなたが疲れてしまうのかが分かり、具体的なヒントが見つかるはずです。
もう一人で悩まず、一緒に解決策を探していきましょう。
なぜ?感情的な人がめんどくさいと感じる主な理由と特徴
「また始まった…」「こっちはそんなつもりじゃないのに…」感情的な人の言動に、うんざりしたり、困惑したりすることは誰にでもあるかもしれません。ここでは、多くの人が「感情的な人ってめんどくさいな」と感じてしまう具体的な理由や、そういった人たちに見られる特徴について、もう少し詳しく見ていきましょう。

あるある?「感情的な人がめんどくさい」と感じる瞬間
日常生活や職場で、思わず「あー、この人、感情的でめんどくさいな…」と感じてしまう瞬間はありませんか? 例えば、こんな時です。
- 些細なことで大騒ぎする時: ちょっとしたミスや意見の食い違いに対して、まるで世界の終わりのように騒ぎ立てられると、こちらも冷静ではいられませんよね。「そんなに怒ること?」と戸惑ってしまいます。
- 話が通じない、聞く耳を持たない時: こちらがいくら論理的に説明しようとしても、感情が先走ってしまい、全く話が通じないことがあります。自分の意見や感情を一方的にぶつけられると、コミュニケーションでのストレスを感じずにはいられません。
- 気分によって態度がコロコロ変わる時: さっきまで機嫌が良かったのに、急に不機嫌になったり、怒り出したり。相手の感情の起伏に振り回されて、どう接していいか分からなくなることも、「めんどくさい」と感じる大きな原因です。人間関係に疲れると感じる典型的なパターンかもしれません。
- 過去のことを何度も持ち出して責める時: 何か問題が起こるたびに、昔のことを掘り返してきてネチネチと責められると、うんざりしてしまいます。まるで、いつまでも終わらないループにはまっているような感覚です。
- 周りの迷惑を考えない言動が多い時: 大きな声で怒鳴ったり、人前で泣き出したり。感情をコントロールできず、周囲への配慮が欠けている行動は、見ているだけでも疲弊します。
これらの瞬間は、多くの人が共感できる「感情的な人、めんどくさい」と感じるあるあるな状況ではないでしょうか。
ここが困る!感情的な人の具体的な特徴とは?
では、具体的にどのような特徴を持つ人が「感情的でめんどくさい」と思われやすいのでしょうか。いくつか代表的な特徴を挙げてみましょう。
- 感情の起伏がジェットコースター並みに激しい: 喜び、怒り、哀しみ、楽しみといった感情の振り幅が大きく、予測不可能なタイミングで感情が爆発することがあります。安定したコミュニケーションを取るのが難しいと感じさせます。
- 自己中心的で、自分の感情を最優先する: 周りの状況や他人の気持ちをあまり考慮せず、自分の感情を押し通そうとする傾向があります。「自分がこう感じているから、あなたもそうすべき」といった論理が展開されることも。
- 被害妄想が強く、ネガティブ思考に陥りやすい: ちょっとした出来事でも、「自分は攻撃されている」「馬鹿にされている」などとネガティブに捉えがちです。自己肯定感を高めることが苦手な場合もあります。
- 白黒つけたがる、0か100か思考: 物事を柔軟に捉えるのが苦手で、「好きか嫌いか」「敵か味方か」といった極端な判断をしがちです。中間の意見や曖昧さを受け入れにくい傾向があります。
- 他人の評価を過剰に気にする: 周りからどう見られているかを非常に気にするため、些細な言動にも敏感に反応し、感情的になることがあります。
- 論理的な思考よりも感情が先行する: 何か問題が起きた時、事実やデータに基づいて冷静に考えるよりも先に、感情的な反応が表に出てしまいます。そのため、建設的な話し合いが難しくなることがあります。
これらの特徴が複数当てはまる場合、周囲の人は「関わると疲れる」「めんどくさい」と感じやすくなるのかもしれません。
関わると疲れる…その心理的な背景を解説
感情的な人と関わると、どっと疲れを感じてしまうのはなぜでしょうか。それには、いくつかの心理的な理由が考えられます。

まず、相手の強い感情に「巻き込まれてしまう」ことが挙げられます。人間の脳には、相手の感情に共感する「ミラーニューロン」という神経細胞があると言われています。そのため、相手が怒りや悲しみを強く表現すると、無意識のうちにこちらも同じような感情を抱いてしまい、精神的に消耗してしまうのです。まるで、感情のジェットコースターに無理やり乗せられているような感覚に近いかもしれません。
次に、常に相手の顔色をうかがい、「気を遣いすぎてしまう」ことも大きな原因です。感情の起伏が激しい人に対しては、「いつ機嫌が悪くなるか分からない」「何を言ったら怒らせてしまうか」と、常にアンテナを張って気を遣うことになります。このような緊張状態が続くと、精神的なエネルギーがどんどん奪われていきます。境界線を引く方法を知らないと、相手の感情の波に飲み込まれやすくなります。
さらに、「正論が通じない」ことによる無力感も疲れに繋がります。こちらがどんなに筋道を立てて説明しても、相手が感情的になっていると、なかなか理解してもらえません。まるで壁に向かって話しているような徒労感は、精神的な疲弊感を増大させます。
そして、「自分だけが我慢している」という不公平感も無視できません。相手は感情を自由に表現しているのに、自分はそれを受け止め、耐えなければならないという状況は、ストレス以外の何物でもありません。アサーティブコミュニケーション、つまり自分も相手も尊重するコミュニケーションが取れないと、一方的に負担を強いられているように感じてしまうのです。
これらの心理的な負担が積み重なることで、「感情的な人と関わると疲れる」という感覚に繋がっていくのです。
感情に振り回される人の口癖や発言パターンの傾向
感情的になりやすい人には、特有の口癖や発言パターンが見られることがあります。これらを知っておくことで、相手が感情的になりかけているサインを早めに察知できるかもしれません。
- 「なんで私ばっかり!」 「どうしていつもこうなるの!」 (被害者意識が強く、不満を他者や状況のせいにしがち)
- 「絶対こうに違いない!」 「普通はこうでしょ!」 (自分の考えや価値観が唯一正しいと信じ込み、他者の意見を受け入れにくい)
- 「もういい!」「勝手にすれば!」 (感情が高ぶると、話し合いを放棄したり、投げやりな態度を取ったりする)
- 「だって」「でも」「どうせ」 (言い訳や否定的な言葉が多く、建設的な会話になりにくい)
- 大げさな表現や感情的な形容詞の多用: 「ありえない!」「信じられない!」「ひどすぎる!」など、感情を強調する言葉を頻繁に使います。
- 過去のネガティブな出来事を何度も持ち出す: 今の問題と関係ない過去の不満や怒りを蒸し返し、話をすり替えようとすることがあります。
- 早口になったり、声が大きくなったりする: 感情が高ぶるにつれて、話し方にも変化が現れます。
これらの口癖や発言パターンは、相手が感情に支配され、冷静な判断が難しくなっているサインかもしれません。感情的な人の口癖を覚えておくと、無用な衝突を避けるヒントになるでしょう。
「もしかして頭悪い?」と思われがちなワケ
感情的な人に対して、「もしかして、この人頭悪いのでは?」と内心思ってしまうことがあるかもしれません。しかし、これは必ずしも「知能が低い」という意味ではありません。
感情的な人が「頭悪い」と誤解されがちなのは、感情が思考を妨げてしまい、論理的で冷静な判断ができなくなっているように見えるからです。怒りや不安といった強い感情に支配されると、脳の前頭前野(理性的思考や判断を司る部分)の働きが一時的に低下すると言われています。その結果、
- 話の筋道が通らない
- 客観的な視点が持てない
- 自分の感情をコントロールできない
- 建設的な解決策を考えられない
といった状態になりやすく、それが「頭が回っていない」「話が通じない」という印象を与えてしまうのです。つまり、感情的になる人は頭悪いのではなく、感情のコントロールが苦手なために、本来持っているはずの思考力や判断力をうまく発揮できていない状態と言えるでしょう。
もちろん、本当に理解力や思考力が低いケースもゼロではありませんが、「感情的=頭が悪い」と短絡的に結びつけるのは早計です。むしろ、感情の波に飲み込まれやすい繊細さを持っている場合もあります。
なぜか女性に多いと感じる?その傾向と理由
「感情的な人って、なんとなく女性に多い気がする…」と感じる人もいるかもしれません。実際に、そのような印象を持つ人がいる背景には、いくつかの要因が考えられます。ただし、これはあくまで一般的な傾向や社会的なイメージの話であり、全ての女性が感情的だという意味でも、男性は感情的でないという意味でもありません。
一つには、コミュニケーションスタイルの違いが挙げられます。一般的に、女性は感情や共感を重視したコミュニケーションを好む傾向があり、自分の気持ちをストレートに表現することが多いと言われています。これが、感情豊か、あるいは感情的と捉えられる一因かもしれません。
また、社会的な役割期待やステレオタイプの影響も考えられます。「女性は感情的であってもある程度許容される」といった無意識の思い込みが社会にあると、女性自身も感情を表現しやすくなったり、周囲も女性の感情的な側面をより強く認識したりする可能性があります。
さらに、女性ホルモンの影響を指摘する声もありますが、科学的な根拠が明確でない部分も多く、一概には言えません。
重要なのは、性別で一括りにするのではなく、個人としてその人を理解しようとすることです。「女性だから感情的」と決めつけるのではなく、なぜその人が感情的になっているのか、その背景にあるものに目を向けることが大切です。感情の表現の仕方は人それぞれであり、性別だけで判断するのは避けるべきでしょう。
もう疲れない!感情的な人がめんどくさい時の賢い対処法
感情的な人に振り回されて「もう疲れた…」と感じているなら、具体的な対処法を知って、少しでも楽になりたいですよね。ここでは、職場やプライベートで実践できる、賢い関わり方のヒントをご紹介します。今日から試せることから始めてみましょう。

まず試したい!基本的な関わり方3つのコツ
感情的な人とのコミュニケーションで、まず心がけたい基本的なコツが3つあります。これらを意識するだけで、あなたの負担は少し軽くなるかもしれません。
- 相手の感情を一旦受け止める(ただし同意はしない)
感情的になっている人は、まず自分の気持ちを分かってほしいと思っています。「そうか、そんな風に感じているんだね」「それはつらかったね」など、相手の感情を否定せずに、言葉として受け止める姿勢を見せましょう。ただし、相手の意見や主張に全て「同意する」必要はありません。「あなたはそう感じているんですね」と、あくまで相手の感情を認知したことを伝えるのがポイントです。これだけでも、相手は少し落ち着きを取り戻すことがあります。感情的に話す人への苦手意識を少しでも和らげる第一歩です。 - 物理的・心理的な距離を適切に保つ
感情の波に飲み込まれないためには、適切な距離感が非常に重要です。物理的に少し離れる、会話を早めに切り上げる、メールやチャットなどワンクッション置けるコミュニケーション手段を選ぶ、といった工夫が有効です。また、心理的にも「これは相手の感情の問題であり、自分の問題ではない」と境界線を引くことを意識しましょう。相手の感情に過度に同調しすぎないことが大切です。 - 冷静さを保ち、感情で返さない
相手が感情的に攻撃してきたとしても、こちらも感情的になってしまっては、火に油を注ぐようなものです。深呼吸をするなどして、できる限り冷静さを保つように心がけましょう。相手の土俵に乗らず、落ち着いたトーンで、事実に基づいて話すことが重要です。難しいかもしれませんが、「自分は冷静に対応する」と意識するだけでも、状況の悪化を防ぐことに繋がります。アンガーマネジメントの考え方も役立つかもしれません。
これらの基本的なコツは、あらゆる場面で応用できます。まずは意識することから始めてみましょう。
【職場編】感情的な同僚・上司への対処法7選
職場に感情的な人がいると、仕事の効率も下がり、精神的にも大きなストレスになりますよね。ここでは、特に職場での感情的な人への対処法を7つご紹介します。
- 報告・連絡・相談は簡潔に、事実ベースで: 感情的な人は、些細な言葉尻を捉えて感情的になることがあります。報告や連絡は、余計な修飾語を避け、事実だけを淡々と、結論から伝えるようにしましょう。メールなどの記録に残る形でのやり取りも有効です。
- 相手の感情が落ち着くまで待つ: 明らかに感情的になっている時は、何を言っても逆効果になることが多いです。可能であれば、少し時間や場所を改めて、相手が冷静さを取り戻してから話すようにしましょう。「今は少しお時間をおいてもよろしいでしょうか」と提案するのも一つの手です。
- 「はい」「いいえ」で答えられる質問をする: 感情的になっている相手に長々と説明を求めると、さらに感情がエスカレートすることがあります。「〇〇ということでしょうか?」「△△でよろしいですか?」など、簡潔に答えられる質問で、少しずつ状況を整理していくのが有効です。
- 共感の言葉は慎重に、しかし無視はしない: 「お気持ちは分かりますが…」と前置きしつつ、こちらの意見を伝えるなど、相手の感情に配慮する姿勢は見せましょう。ただし、過度な共感は相手を増長させる可能性もあるため、バランスが重要です。完全に無視すると、さらに感情をこじらせることもあります。
- 第三者を交えて話し合う: 当事者同士では感情的なぶつかり合いになってしまう場合、信頼できる上司や同僚など、冷静な第三者を交えて話し合いの場を設けるのも有効な手段です。客観的な意見が入ることで、状況が整理されやすくなります。
- 記録を取っておく: あまりにも理不尽な要求や感情的な言動が続く場合は、日時、場所、具体的な言動などを記録しておきましょう。これは、万が一、ハラスメントなどの問題に発展した場合の証拠となり得ます。
- 仕事と割り切り、プライベートに持ち込まない: 職場の人間関係は、ある程度「仕事だから」と割り切ることも大切です。感情的な人に振り回されたとしても、そのストレスをプライベートまで引きずらないように、オンとオフの切り替えを意識しましょう。メンタルヘルスケアの観点からも重要です。
これらの対処法を参考に、少しでも働きやすい環境を作っていきましょう。
【プライベート編】友人・家族が感情的な時の接し方
職場だけでなく、友人や家族など、プライベートな関係においても、感情的な人との関わり方に悩むことはあります。近しい関係だからこそ、より深く影響を受けてしまうことも。そんな時の接し方のポイントを見ていきましょう。

- 話を聞く姿勢を見せるが、深入りしすぎない: 親しい間柄だと、つい相手の感情に寄り添いすぎてしまうことがあります。話を聞くことは大切ですが、相手のネガティブな感情に引きずり込まれないように、適度な距離感を保ちましょう。「大変だったね」と共感しつつも、問題解決にまで踏み込みすぎないように注意が必要です。
- 「私はこう思う」と自分の意見も伝える(ただし冷静に): 相手が感情的になっていても、自分の意見や気持ちを伝えることは大切です。ただし、相手を否定したり、論争になったりしないように、「私はこう感じるな」「私だったらこうするかな」と、あくまで「I(アイ)メッセージ」で、穏やかに伝えるようにしましょう。
- 一時的に距離を置く勇気も必要: あまりにも感情的な言動が続き、自分自身が疲弊してしまうようなら、一時的に連絡を控えたり、会う頻度を減らしたりすることも考えてみましょう。大切な関係だからこそ、お互いにとって良い距離を見つけることが重要です。境界線を引く方法の一つです。
- 相手の「良い面」にも目を向ける: 感情的な面ばかりが目につくと、その人の全てが嫌になってしまうこともあります。しかし、誰にでも良い面はあるはずです。少し冷静になって、相手の良いところや、楽しかった思い出などを意識的に思い出してみるのも、関係性を見直すきっかけになるかもしれません。
- 自分自身の感情のケアを怠らない: 近しい人が感情的だと、こちらも精神的に大きな影響を受けます。自分の好きなことをする時間を作ったり、信頼できる別の人に話を聞いてもらったりして、自分自身の心のバランスを保つようにしましょう。
友人や家族との関係は、職場とはまた違った難しさがありますが、お互いを尊重し合える関係性を目指せると良いですね。
相手を少し落ち着かせるかもしれない「魔法の言葉」
感情的になっている相手に対して、何か少しでも状況を好転させる「魔法の言葉」があれば…と思いますよね。残念ながら、どんな相手にも必ず効く万能な言葉はありません。しかし、相手の興奮を少し鎮め、冷静さを取り戻すきっかけになるかもしれない言葉はあります。
- 「そうだったんですね」「そんなことがあったんですね」
まずは相手の言いたいことを受け止める、というサインになります。話を遮らずに聞く姿勢を示すことで、相手は「聞いてもらえている」と感じ、少し落ち着くことがあります。 - 「(相手の名前)さん、少し深呼吸しませんか?」
直接的に「落ち着いて」と言うよりも、行動を促す方が受け入れられやすい場合があります。相手の名前を呼ぶことで、少し我に返るきっかけになることも。 - 「何か私にできることはありますか?」
相手が困っている、助けを求めているように見える場合に有効です。ただし、無理な要求に応える必要はありません。あくまで「できる範囲で」というスタンスで。 - 「話してくれてありがとう」
感情的になりながらも、何かを伝えようとしてくれていることに対して感謝を示すことで、相手の気持ちが少し和らぐことがあります。
これらの言葉は、あくまで「きっかけ」を作るものです。大切なのは、言葉そのものよりも、相手を気遣う誠実な態度です。そして、これらの言葉を使っても効果がない場合は、無理にコミュニケーションを続けようとせず、距離を置く判断も必要です。
どうしても無理な時の最終手段:上手な距離の置き方
いろいろ試してみたけれど、どうしても感情的な人との関わりが辛い、改善が見られない…。そんな時は、自分を守るために「距離を置く」という選択も非常に重要です。罪悪感を感じる必要はありません。
- 物理的な距離を置く:
- 会う頻度を減らす: 可能であれば、直接会う機会を減らしましょう。
- 席を離れる・部署移動を願い出る(職場の場合): 常に顔を合わせる環境が辛いなら、物理的に離れる工夫を。
- 連絡手段を制限する: 電話には出ず、メールやLINEの返信も時間を置く、既読スルーをするなど、コンタクトを取る頻度を減らします。
- 心理的な距離を置く:
- 相手の言動を真に受けない: 「この人はこういう人なんだ」と割り切り、いちいち相手の言葉に傷ついたり、深く考え込んだりしないようにします。
- 期待しない: 相手が変わることを期待しすぎると、裏切られた時の失望感が大きくなります。「人は簡単には変わらない」と理解しておくことも大切です。
- 自分の感情と思考を優先する: 相手の感情に振り回されず、「自分はどうしたいか」「自分はどう感じるか」を大切にしましょう。
- 関わる時間を最低限にする: どうしても関わらなければならない場合は、挨拶だけにする、用件だけを伝えてすぐに離れるなど、接触時間を極力短くします。
距離を置くことは、決して「逃げ」ではありません。自分の心と体の健康を守るための、賢明な判断です。ストレスマネジメントの一環として、自分にとって最適な距離感を見つけていきましょう。
論理的な人と感情的な人、思考の違いを理解する
「なんでこんなに話が通じないんだろう?」と感じるのは、もしかしたらあなたと相手の思考タイプが違うからかもしれません。一般的に、物事を判断する際に「論理」を重視する人と、「感情」を重視する人がいます。

- 論理的な人の思考:
- 事実やデータに基づいて客観的に判断しようとする
- 筋道を立てて、冷静に問題を分析する
- 感情よりも合理性や効率性を優先する傾向がある
- 結論や解決策を求める
- 感情的な人の思考:
- 自分の気持ちや直感を大切にする
- 共感や人との繋がりを重視する
- 論理性よりも、その時の感情が判断に大きく影響する
- 気持ちを理解してほしい、共感してほしいと願う
どちらが良い悪いというわけではありません。ただ、この思考の出発点が違うと、同じ出来事を見ても解釈が異なり、コミュニケーションがすれ違いやすくなります。
感情的な人をめんどくさいと感じやすいのは、論理的な思考をする人から見ると、感情的な人の言動が「非合理的」「理解不能」に見えるからかもしれません。逆に、感情的な人から見ると、論理的な人の言動が「冷たい」「思いやりがない」と感じられることもあります。
この違いを理解しておくだけでも、「なぜ相手はあのような反応をするのか」と、少し客観的に相手を見られるようになるかもしれません。感情的な人と論理的な人、それぞれの思考のクセを知ることは、コミュニケーションのヒントになります。
自分を守る!コミュニケーションストレスを溜めない方法
感情的な人との関わりは、大きなコミュニケーションストレスを生みます。そのストレスを溜め込まず、上手に発散し、自分自身を守る方法を知っておきましょう。
- 信頼できる人に話を聞いてもらう: 溜め込んだ感情や愚痴は、信頼できる友人、家族、同僚などに話すだけでもスッキリすることがあります。ただし、相手を選び、悪口大会にならないように注意しましょう。
- 自分なりのストレス解消法を見つける: 趣味に没頭する、運動する、好きな音楽を聴く、美味しいものを食べる、ゆっくりお風呂に入るなど、自分がリラックスできること、楽しめることを見つけて実践しましょう。
- 十分な睡眠と休息を取る: 心と体は繋がっています。睡眠不足や疲労は、ストレスへの耐性を弱めます。質の高い睡眠を心がけ、意識的に休息を取りましょう。
- 物事の捉え方を変えてみる(リフレーミング): 例えば、「あの人は感情的で困る」という捉え方を、「あの人は自分の感情に正直な人なんだな(でも自分は距離を置こう)」というように、少し視点を変えてみることで、気持ちが楽になることがあります。
- セルフケアの時間を大切にする: どんなに忙しくても、自分のためだけの時間を持つようにしましょう。短時間でも、自分が心地よいと感じることをするだけで、心のエネルギーがチャージされます。メンタルヘルスケアは日々の積み重ねが大切です。
- 「ノー」と言う勇気を持つ: 無理な要求や、自分にとって負担の大きい関わり方に対しては、はっきりと「ノー」と言うことも必要です。アサーティブコミュニケーションを意識し、自分を大切にする選択をしましょう。
ストレスをゼロにすることは難しいかもしれませんが、上手にコントロールする方法を身につけることで、心の負担を軽減できます。
もし、ご自身だけでは抱えきれないほどのストレスを感じたり、気分の落ち込みが長く続いたりするようなら、専門的な情報を得ることも大切です。厚生労働省のウェブサイト「こころの耳」では、こころの健康に関する様々な情報や相談窓口が紹介されていますので、参考にしてみてください。
感情的な相手にも「自覚」はあるのか?
「あの人、自分がどれだけ周りを振り回しているか、分かっているのかな?」と疑問に思うこともありますよね。感情的な人自身に、自分の言動に対する「自覚」はあるのでしょうか。
これは、人によって大きく異なります。
- 自覚があるケース:
- 本当は感情的になりたくないのに、コントロールできずに後で後悔している。
- 自分の感情の起伏の激しさに自分自身も悩んでいる。
- 「またやってしまった」と自己嫌悪に陥っている。
このような場合は、本人も苦しんでいる可能性があります。
- 自覚がない、または薄いケース:
- 自分の感情表現が「普通」だと思っている。
- 周りが自分に合わせてくれるのが当然だと考えている。
- 感情的に振る舞うことで、自分の要求が通ってきた経験がある。
- 自分の言動が他人にどう影響しているか、想像力が及ばない。
この場合、周囲がいくら困っていても、本人は問題意識を持っていないため、改善は難しいかもしれません。
相手に自覚があるかどうかを見極めるのは難しいですが、もし自覚があるように見えるなら、少しだけ寄り添う余地があるかもしれません。しかし、自覚がない相手に対して、無理に「あなたは感情的だ」と指摘するのは、逆効果になる可能性が高いので注意が必要です。
いずれにしても、相手に自覚があるかないかにかかわらず、あなたが自分の心を守るための対処法を実践することが最も重要です。
まとめ:「感情的な人、めんどくさい…」への対処法
この記事では、「感情的な人、めんどくさい…」と感じる理由とその特徴、そして具体的な対処法について解説してきました。
感情的な人に振り回されてしまうのは、相手の強い感情に巻き込まれたり、常に気を遣いすぎたり、正論が通じない無力感を感じたりするからです。そして、感情的な人には、気分の浮き沈みが激しい、自己中心的、被害妄想が強いといった特徴が見られることがあります。
そんな相手と少しでも楽に関わるためには、まず「相手の感情を一旦受け止める(同意はしない)」「適切な距離を保つ」「冷静さを保ち感情で返さない」という3つの基本を意識することが大切です。職場やプライベートの場面に応じた具体的な対処法も参考に、今日からできることを試してみてください。
どうしても辛い時は、無理せず物理的・心理的に距離を置くことも、自分を守るための立派な選択です。そして、コミュニケーションストレスを溜め込まないように、自分なりのリフレッシュ方法を見つけて、セルフケアを大切にしてくださいね。
感情的な人との関わり方は、一朝一夕には改善しないかもしれません。でも、この記事でお伝えしたヒントを少しずつ試していくことで、あなたの心が少しでも軽くなり、より穏やかな日々を送れるようになることを願っています。あなたは一人ではありません。