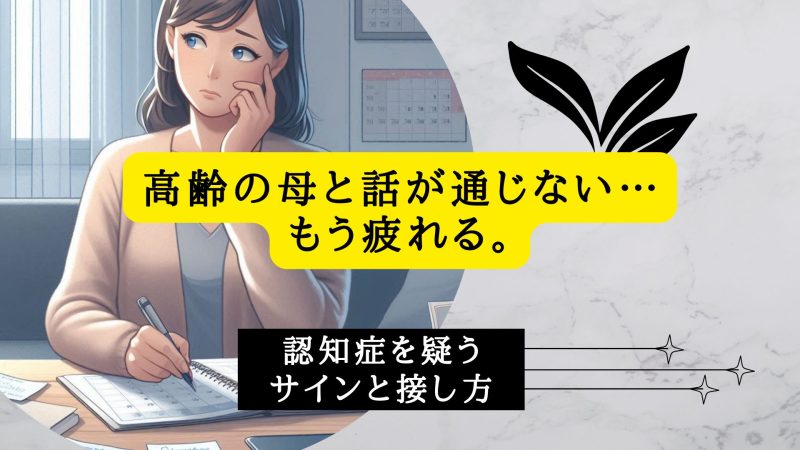「最近、なんだか高齢の母と話が通じない…」。
そんな風に感じることが増えて、言いようのない不安や疲れを感じていませんか。
何度も同じことを聞かれたり、話が噛み合わなかったりすると、ついイライラしてしまうこともあるかもしれません。

しかし、そのお悩みは、決してあなた一人だけのものではありません。
この記事では、なぜ会話が成り立たないのか、その原因と認知症の可能性、そして何よりも、あなたがこれ以上疲れ切ってしまわないための具体的な接し方や相談先について、分かりやすく解説していきます。
この記事を読めば、お母様への理解が深まり、あなたの心の負担を軽くするヒントがきっと見つかるはずです。
- なぜ高齢の母と話が通じない?疲れる原因と認知症のサイン
- 話が通じない高齢の母に疲れる…心を守る対処法と相談先
なぜ高齢の母と話が通じない?疲れる原因と認知症のサイン
大切なお母様との会話が、以前のようにスムーズにいかない。
そんな時、私たちは戸惑い、そして深く疲れてしまいます。
「どうして分かってくれないの?」という気持ちと、「もしかして何かの病気なのでは?」という不安が入り混じり、心が休まらない日々を過ごしている方も多いのではないでしょうか。
このパートでは、まず「なぜ話が通じないのか」という根本的な原因を探っていきます。
それは単なる老化現象なのか、それとも認知症の始まりなのか。
考えられる様々な可能性を知ることで、冷静に状況を理解し、次の一歩を踏み出すための準備を整えましょう。

年寄りと話が通じないのは、なぜ?考えられる5つの原因
高齢の親と話が噛み合わないと感じる時、その背景には一つだけでなく、複数の原因が複雑に絡み合っていることが少なくありません。
「話が通じない」と一括りにせず、その原因を一つひとつ紐解いていくことが、理解への第一歩となります。
1. 認知機能の低下(認知症の可能性)
最も心配されるのが、認知症をはじめとする病気による認知機能の低下です。
記憶力や理解力、判断力が少しずつ失われていくことで、会話の内容をすぐに忘れてしまったり、話の文脈を掴めなくなったりします。
これは本人の意思とは関係なく、脳の機能的な変化によって引き起こされる症状なのです。
2. 加齢による聴力の低下(難聴)
意外と見落とされがちなのが、聴力の問題です。
年を重ねると、誰でも少しずつ耳が遠くなることがあります。
本人は聞こえているつもりでも、実は会話の一部が正確に聞き取れておらず、結果としてトンチンカンな返答をしてしまうケースは少なくありません。
「話を聞いてない」と感じたら、まずは聞こえの問題を疑ってみることも大切です。
3. 価値観や時代の変化によるジェネレーションギャップ
病気や身体的な衰えだけでなく、長年生きてきた中で培われた価値観の違いが、会話の壁になることもあります。
親世代が「常識」としてきたことと、現代の私たちの考え方との間には、大きな隔たりがあることも。
お互いの「当たり前」が違うため、話が平行線をたどってしまうのです。
4. 老人性うつなどの精神的な不調
高齢期には、心の問題も会話に影響を及ぼします。
例えば「老人性うつ」になると、物事への興味や関心が薄れ、思考力が低下することがあります。
その結果、会話に集中できなかったり、返事が曖昧になったりして、「話が通じない」という印象を与えてしまうことがあるのです。
5. プライドの高さや性格的な問題
元々の性格が、年齢を重ねることでより強く表に出てくることもあります。
特にプライドが高い人の場合、自分の間違いを認めたがらなかったり、人の意見に耳を貸さなくなったりする傾向が見られます。
「自分は正しい」という思い込みが、円滑なコミュニケーションを妨げているのかもしれません。
母親と話が通じないのは病気のサイン?認知症の初期症状とは
「もしかして認知症なのでは?」という不安は、ご家族にとって最も大きな心配事の一つでしょう。
単なる物忘れと認知症のサインは、どう見分ければよいのでしょうか。
ここでは、認知症を疑う場合に現れやすい初期症状のいくつかをご紹介します。
当てはまるものが複数ある場合は、注意が必要かもしれません。
同じ話を何度もする
認知症の代表的な症状の一つが、記憶障害です。
特に、数分前や数時間前といった、ごく最近の出来事を忘れてしまう傾向があります。
そのため、食事をしたばかりなのに「ご飯はまだ?」と聞いたり、同じ質問を何度も繰り返したりすることが増えてきます。
本人は話したこと自体を忘れているため、悪気は全くありません。

直前のことを忘れる(約束や食事の内容など)
新しいことを記憶する力が衰えるため、約束の時間や内容をすっかり忘れてしまったり、今日の予定が分からなくなったりします。
これは、体験した出来事そのものが記憶から抜け落ちてしまう「エピソード記憶」の障害によるものです。
「うっかり忘れた」というレベルではなく、出来事自体がなかったことになっているのが特徴です。
時間や場所の感覚が不確かになる
今日が何月何日なのか、今が朝なのか夕方なのかといった、時間の感覚が曖昧になることがあります。
これを「見当識障害」と呼びます。
症状が進むと、慣れているはずの場所で道に迷ったり、自分のいる場所が分からなくなったりすることもあります。
物事の段取りが悪くなる(料理や買い物など)
これまで当たり前にできていた作業が、うまくこなせなくなるのもサインの一つです。
例えば、料理の手順が分からなくなって味付けがおかしくなったり、買い物の際に何を買うべきか計画を立てられなくなったりします。
これは、複数の作業を同時に考え、順序立てて実行する能力(実行機能障害)が低下するために起こります。
人柄が変わったように感じる(怒りっぽくなる、疑い深くなるなど)
認知症は、記憶だけでなく感情のコントロールにも影響を及ぼすことがあります。
以前は穏やかだった人が、ささいなことで怒りっぽくなったり、急に不安になったり、あるいは「物を盗られた」などと家族を疑うような被害妄想が見られたりすることも。
このような人柄の変化は、脳の機能低下が原因で起こる症状の可能性があります。
年寄りの親との会話がなぜこんなに疲れるのか、その理由
話が通じない親とのコミュニケーションは、精神的に大きな負担を伴います。
「どうしてこんなに疲れるんだろう」と感じるのは、決してあなただけではありません。
その疲れの裏には、いくつかの心理的な理由が隠されています。
気持ちを分かってもらえない徒労感
一生懸命に説明しても、全く理解してもらえない。
心配する気持ちが伝わらず、むしろ怒られたり拒絶されたりする。
こうした経験が積み重なると、「何を言っても無駄だ」という深い徒労感に襲われます。
心と心が通い合わない寂しさが、疲れを一層深くするのです。

何度も同じ説明をする忍耐力の消耗
同じ質問に何度も答え、同じ注意を何度も繰り返す。
それは、まるで終わりのないマラソンのようです。
最初は我慢できても、毎日続くと忍耐力は少しずつすり減っていきます。
自分の時間や感情が、常に親のペースに振り回されているような感覚に陥り、精神的に消耗してしまうのです。
親の変化に対する悲しみや不安
かつては頼りになり、何でも分かってくれていた親が、少しずつ変わっていく姿を目の当たりにすることは、子供にとって非常に辛いことです。
「あの頃のお母さんじゃない」という悲しみや、「これからどうなってしまうのだろう」という将来への漠然とした不安が、常に心の底に重くのしかかります。
感情的な反応(怒りや被害妄想)への対応
話が通じないだけでなく、怒りや被害妄想といった感情的な反応をぶつけられると、こちらも冷静でいるのは難しくなります。
理不尽な言葉に傷つき、反論したくてもできないストレスが溜まっていきます。
いつ爆発するか分からない相手に気を遣い続ける緊張感が、心身を疲弊させる大きな原因となります。
認知症だけじゃない!話が噛み合わない他の病気や加齢の影響
会話が噛み合わない原因は、アルツハイマー型認知症だけとは限りません。
他の病気や、加齢に伴う様々な変化が影響している可能性も十分に考えられます。
正しい対応をするためには、多様な可能性を知っておくことが重要です。
軽度認知障害(MCI)
軽度認知障害(MCI)は、健常な状態と認知症の中間にあたる段階です。
記憶力の低下などの症状は見られるものの、日常生活への支障はまだそれほど大きくないのが特徴です。
しかし、MCIを放置すると、高い確率で認知症に移行すると言われています。
早期に発見し、適切な対策を講じることで、進行を遅らせることができる可能性があります。

老人性うつ
高齢者のうつ病は、若い世代のうつ病とは少し異なり、気分の落ち込みよりも、頭痛や食欲不振といった身体的な不調や、「頭が働かない」「物事を考えられない」といった思考力の低下が目立つことがあります。
この思考力の低下が、会話の遅れや内容のズレにつながり、話が通じないように見えることがあるのです。
せん妄
せん妄とは、薬の影響や脱水、発熱、環境の変化などがきっかけで、一時的に意識が混濁する状態のことです。
急に興奮したり、幻覚を見たり、辻褄の合わないことを言ったりします。
症状は一日の中でも変動し、夜間に悪化することが多いのが特徴です。
原因を取り除けば改善することが多いため、認知症と決めつけず、急な変化には注意が必要です。
レビー小体型認知症
レビー小体型認知症は、認知症の中でも特徴的な症状を示します。
実際にはいない人が見える「幻視」や、現実と夢の区別がつかなくなるような状態、そして日によって頭がはっきりしている時とぼんやりしている時の差が激しい「認知機能の変動」などが挙げられます。
パーキンソン症状(手の震えや歩きにくさ)を伴うこともあります。
難聴
先にも触れましたが、難聴はコミュニケーションにおける非常に大きな障壁です。
本人が難聴を自覚していなかったり、認めたがらなかったりすることも少なくありません。
大きな声で話しても、言葉の細かい部分が歪んで聞こえている可能性もあります。
まずは聴力検査を受けてみるなど、客観的な評価が解決の糸口になることもあります。
もしかして被害妄妄想や作り話?危険なサインを見逃さないで
会話の中で、明らかに事実と異なる発言や、人を疑うような言動が見られると、家族は非常に困惑します。
これらは、認知症の症状として現れることがある「被害妄想」や「作話」かもしれません。
「財布を盗られた」などの被害妄想
認知症による記憶障害が背景にあります。
例えば、自分で財布をしまい込んだ場所を忘れてしまい、「誰かに盗られたに違いない」と思い込んでしまうのです。
本人にとってはそれが真実であり、強く確信しているため、否定されると余計に興奮したり、不安になったりします。
最も身近にいる家族が疑いの対象にされやすく、対応する側にとっては非常につらい状況です。

記憶の隙間を埋める「作り話(作話)」
作り話、専門的には「作話(さくわ)」と呼ばれますが、これは意図的に嘘をついているわけではありません。
記憶が抜け落ちてしまった部分を、辻褄が合うように無意識のうちに別の話で補ってしまう脳の働きによるものです。
本人には、その話が作り話であるという自覚はありません。
そのため、「嘘をつかないで」と責めるのは逆効果です。
本人の尊厳を傷つけ、混乱を深めてしまうだけです。
このようなサインが見られた時は、病気の症状である可能性を念頭に置き、冷静に対応することが何よりも大切になります。
話が通じない高齢の母に疲れる…心を守る対処法と相談先
お母様とのコミュニケーションに疲れ果て、心が折れそうになっていませんか。
原因が分かってきても、日々の対応は本当に大変です。
しかし、少し接し方を変えたり、頼れる場所を知ったりするだけで、あなたの心の負担は大きく変わることがあります。
このパートでは、あなたが自分自身を守りながら、お母様と穏やかに関わっていくための具体的な対処法や、一人で抱え込まずに済むための相談先について詳しくお伝えします。
あなたの心が少しでも軽くなるヒントが、きっとここにあります。

話の通じない親へのNG対応と、今日からできる対処法
良かれと思ってしている対応が、実はお母様の混乱を招き、状況を悪化させていることがあります。
まずは、ついやってしまいがちなNG対応を知り、それを避けることから始めましょう。
その上で、お互いが穏やかでいられるための接し方のコツを身につけていきましょう。
やってはいけない!NG対応リスト
- 間違いを厳しく指摘する、問い詰める: 「違うでしょ!」「さっきも言ったでしょ!」と間違いを正そうとすることは、本人のプライドを傷つけ、不安や怒りを煽るだけです。
- 論理で説得しようとする: 認知機能が低下している相手に、正論や理屈で説得を試みても通じません。かえって混乱させてしまいます。
- 感情的に言い返す: 相手のイライラに付き合って、「こっちだって大変なんだ!」と感情的に応戦しても、何の解決にもなりません。お互いに傷つくだけです。
- 無視する: どうせ話しても無駄だと諦めて無視をすると、本人は見捨てられたと感じ、孤独感や不安を深めてしまいます。
今日からできる!心の距離が縮まる対処法
- まずは共感。「そうなんだね」と受け止める: たとえ話の内容が事実と違っていても、まずは「そうなんだね」「大変だったね」と、相手の気持ちに寄り添い、話を受け止めてあげましょう。安心感が生まれます。
- 話を合わせ、相手の世界観を否定しない: 被害妄想などに対しては、真っ向から否定するのではなく、「それは心配だね。一緒に探してみようか」と、本人の世界観に一度寄り添う姿勢を見せることが有効な場合があります。
- 短く、分かりやすい言葉で話す: 一度にたくさんの情報を伝えようとせず、「ご飯にする?」「お茶を飲む?」のように、質問は一つずつ、シンプルで短い言葉で話しかけましょう。
- 視線を合わせ、穏やかな表情で接する: 言葉だけでなく、非言語的なコミュニケーションも大切です。優しい眼差しで、穏やかな口調で話すことで、安心感を与えることができます。
- 話題を変えて気分転換を促す: 話が堂々巡りになったり、興奮したりしている時は、無理に話を続けず、「あら、綺麗な花が咲いているね」「好きだった歌でも聴こうか」など、本人が好きそうなことへ話題を転換してみましょう。
つい高齢の母にイライラする…感情をコントロールする方法
毎日続くコミュニケーションの壁に、イライラしてしまうのは当然の感情です。
決してあなたが冷たい人間だからではありません。
大切なのは、そのイライラとどう向き合い、自分自身の心を守るかです。
自分を追い詰めないための、感情コントロールのヒントをご紹介します。
その場を一旦離れる(物理的に距離を取る)
感情が爆発しそうになったら、まずはその場から静かに離れましょう。
「ちょっとトイレに行ってくるね」などと伝え、別の部屋へ移動して数分間だけでも一人になる時間を作ります。
物理的に距離を取ることで、クールダウンするきっかけになります。

深呼吸をする
イライラしている時、人の呼吸は浅く速くなりがちです。
意識的に、ゆっくりと深く息を吸い込み、さらに時間をかけて息を吐き出す「深呼吸」を数回繰り返してみましょう。
副交感神経が優位になり、高ぶった神経を鎮める効果が期待できます。
「これは病気の症状なのだ」と割り切る
お母様の言動は、あなたを困らせようとしているわけではなく、「病気がそうさせているのだ」と客観的に捉えることも大切です。
人格そのものではなく、症状に対して向き合っているのだと考えることで、少し冷静に受け止められるようになります。
信頼できる友人やパートナーに話を聞いてもらう
溜め込んだストレスや愚痴は、誰かに聞いてもらうだけでも心が軽くなります。
介護の経験がある友人や、あなたの気持ちを理解してくれるパートナーなど、安心して話せる相手に思いの丈を吐き出す時間を作りましょう。
自分のための時間を作る
介護に追われる毎日の中でも、意識して「自分のためだけの時間」を確保することが不可欠です。
たとえ短い時間でも、好きな音楽を聴く、趣味に没頭する、美味しいものを食べるなど、自分が心からリラックスできることをして、すり減ったエネルギーを充電しましょう。
高齢の母に優しくできない…そんな自分を責めないで
「もっと優しく接しなければいけないのに、できない」。
そうやって自分を責めてしまう方は、本当に多いです。
しかし、その罪悪感は、あなたをさらに苦しめるだけかもしれません。
優しくできないのは、あなたが疲れ切っているサインです。
自分を責める前に、なぜそう感じてしまうのかを理解しましょう。
長期間にわたる介護やコミュニケーションのストレスは、心身に大きな負担をかけます。

これは「介護者バーンアウト(燃え尽き症候群)」にもつながる深刻な問題です。
エネルギーが枯渇した状態で、人に優しくし続けることは誰にもできません。
だからこそ、まずは「頑張っている自分」を認めてあげてください。
毎日、大変な状況の中で、お母様と向き合っている。
それだけでも、本当に素晴らしいことなのです。
自分自身にも思いやりを向ける「セルフコンパッション」の考え方を取り入れ、完璧ではない自分を許してあげることが、結果的にお母様とのより良い関係につながっていきます。
高齢の母親との関係に疲れる前に。限界を感じた時の相談窓口
「もう限界かもしれない」。
そう感じたら、それは一人で抱え込まず、外部の助けを求めるべきサインです。
幸い、今の日本には、介護や高齢者の問題について相談できる専門の窓口が整備されています。
どこに相談すればいいか分からないという方のために、主な相談先をご紹介します。
地域包括支援センター
介護に関する最も身近で頼りになる相談窓口が、この「地域包括支援センター」です。
お住まいの市区町村ごとに設置されており、保健師、社会福祉士、ケアマネジャーなどの専門職が無料で相談に乗ってくれます。
「何に困っているか、うまく説明できない」という段階でも大丈夫です。
現状を話すだけで、必要な情報を提供してくれたり、適切なサービスや機関につないでくれたりします。
まさに「介護の総合案内所」のような場所です。

かかりつけ医
まずは日頃からお母様の健康状態を把握してくれている、かかりつけの医師に相談してみるのも良いでしょう。
認知症の初期症状なのか、あるいは別の身体的な病気が隠れていないかなど、医学的な観点からアドバイスをもらえます。
必要であれば、専門の医療機関への紹介状を書いてもらうことも可能です。
物忘れ外来・精神科・心療内科
認知症の診断や治療を専門的に行っているのが、これらの医療機関です。
「物忘れ外来」という名称の専門外来を設けている病院もあります。
何科を受診すればよいか迷う場合は、まずは電話で問い合わせてみたり、地域包括支援センターに相談したりして、どの医療機関が適切かを確認するとスムーズです。
親と上手に距離を置くコツと、介護保険サービスの活用法
お母様との関係を良好に保つためには、時には意識して「距離を置く」ことも非常に重要です。
罪悪感を感じる必要はありません。
適度な距離は、お互いの心に余裕を生み、結果としてより良い関係を築くための大切なステップなのです。
そして、その距離を作るために非常に役立つのが「介護保険サービス」です。
心理的な距離と物理的な距離
上手に距離を置くとは、親を見捨てることではありません。
例えば、これまで毎日電話していたのを数日に一回にする、訪問の回数を調整するなど、少しずつ関わる時間をコントロールすることから始めてみましょう。
そして、その空いた時間を自分のために使うことで、心の余裕を取り戻すことができます。

介護保険サービスという心強い味方
介護保険サービスは、高齢者が自宅で自立した生活を送れるよう支援するための公的な制度です。
これらを活用することで、家族の介護負担を大幅に軽減することができます。
まずは市区町村の窓口で「要介護認定」の申請を行うことから始まります。
認定を受けると、ケアマネジャーが本人や家族の状況に合わせたケアプランを作成してくれます。
具体的なサービスの例
- デイサービス(通所介護): 日中に施設へ通い、食事や入浴、レクリエーションなどのサービスを受けられます。お母様にとっては社会との交流の場となり、家族にとっては日中のまとまった自由時間が生まれます。
- ショートステイ(短期入所生活介護): 短期間、施設に宿泊することができるサービスです。家族が旅行や冠婚葬祭で家を空ける時や、休息を取りたい時などに利用できます。
- ホームヘルプサービス(訪問介護): ヘルパーが自宅を訪問し、食事や排泄の介助といった「身体介護」や、掃除や買い物などの「生活援助」を行ってくれます。
これらのサービスを上手に組み合わせることで、あなたは介護の全てを一人で背負う必要がなくなります。
プロの手を借りることは、決して悪いことではありません。
むしろ、お母様にとっても、専門的なケアを受けられるという大きなメリットがあるのです。
あなた自身の心と体を守り、お母様と穏やかな関係を続けていくために、ぜひこれらの選択肢を検討してみてください。
まとめ:高齢の母と話が通じない…疲れを感じたら
「高齢の母と話が通じない…」と感じる日々は、心身ともに大きな負担となり、疲れ果ててしまうのは当然のことです。
その原因は、認知症のサインである場合もあれば、難聴や加齢による心の変化など、様々な要因が考えられます。
大切なのは、一方的に突き放すのではなく、その背景に何があるのかを理解しようと努めることです。
記事でご紹介したように、間違いを正さずに共感を示したり、短い言葉で伝えたりといった接し方の工夫は、お互いのストレスを和らげる助けになります。
そして何よりも、一人で抱え込まないでください。
「優しくできない」と自分を責める必要は全くありません。
それは、あなたが助けを必要としているサインです。
地域包括支援センターや専門の医療機関、介護サービスなど、頼れる場所はたくさんあります。
まずはあなた自身の心を守ることを最優先に、利用できるサポートを積極的に活用し、お母様との穏やかな時間を取り戻すための一歩を踏み出してください。