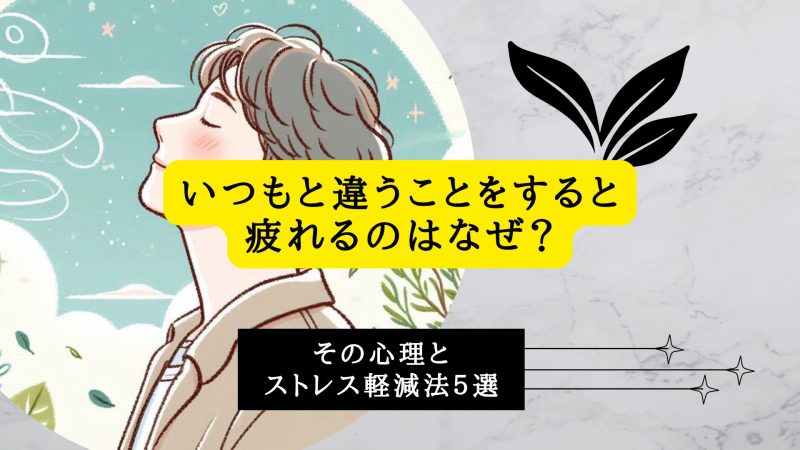新しいことに挑戦した日や、いつもと違う休日を過ごした後、なぜかどっと疲れてしまった経験はありませんか?
「楽しかったはずなのに、なぜか体が重い…」と感じるのは、決してあなただけではありません。
実は、いつもと違うことをすると疲れるのには、私たちの脳の仕組みや心理状態が深く関わっています。

この記事では、その疲れの裏に隠された科学的な理由を分かりやすく解き明かします。
さらに、明日からすぐに試せる具体的なストレス軽減法を5つ厳選してご紹介しますので、ぜひ最後まで読んで、心と体を上手にいたわるヒントを見つけてください。
- いつもと違うことをすると疲れるのはなぜ?隠された心理と脳の仕組み
- いつもと違うことをして疲れる悩みを解消!今日からできる5つのセルフケア
いつもと違うことをすると疲れるのはなぜ?隠された心理と脳の仕組み
旅行や新しい趣味、転職や引越しといった環境の変化。
これらはワクワクする一方で、想像以上の疲労感を伴うことがよくあります。
「楽しいはずなのに、どうしてこんなに疲れるんだろう?」と不思議に思う方も多いかもしれません。
その答えは、私たちの脳と心の中に隠されています。
ここでは、いつもと違う行動がなぜ疲れにつながるのか、その根本的な原因を脳科学や心理学の視点から、一つひとつ丁寧に紐解いていきましょう。
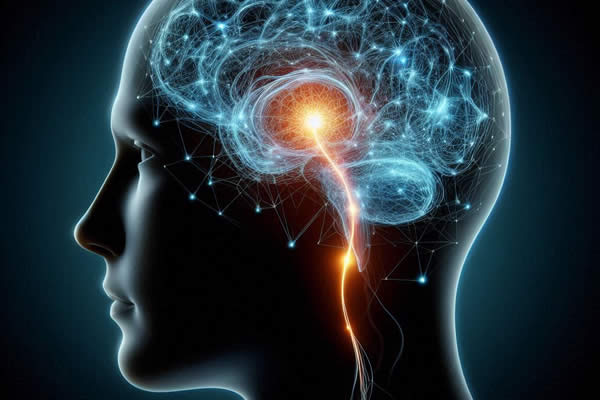
原因は脳にあり?いつもと違うことをする脳の仕組みと恒常性
私たちの行動や感情を司る「脳」。
実はこの脳こそが、いつもと違うことをした時に疲労を感じる大きな原因となっています。
脳が持つ、ある基本的な性質について知ることで、疲れの正体が見えてきます。
脳は「省エネ」が大好き
私たちの脳は、体重のわずか2%程度の重さしかありません。
しかし、驚くべきことに、体全体のエネルギー消費量の約20%を占める大食漢なのです。
そのため、脳は常に「できるだけエネルギーを使いたくない」と考える、いわば究極の省エネ志向を持っています。
毎日同じ時間に起き、同じ道を通り、同じような仕事をする。
こうした「いつも通り」の行動、つまりルーティンは、脳にとってほとんどエネルギーを使わない「自動操縦モード」で処理できます。
いちいち「次は何をしよう?」と考えなくても体が勝手に動くのは、脳が学習して行動をパターン化し、省エネ運転をしている証拠なのです。
体の状態を一定に保つ「恒常性(ホメオスタシス)」とは?
この省エネ志向と深く関わっているのが、「恒常性(ホメオスタシス)」という体の仕組みです。
少し難しい言葉に聞こえるかもしれませんが、これは「体の状態を常に一定に保とうとする働き」のことです。
例えば、暑い時には汗をかいて体温を下げ、寒い時には体を震わせて熱を生み出しますよね。
これも恒常性の一種です。
この働きは、体温や血糖値といった物理的な状態だけでなく、私たちの心理的な状態、つまり「心の安定」にも作用します。
脳は、慣れ親しんだ安心できる状態を「正常」と判断し、その状態を維持しようとします。
いつもと違うことをする、というのは、この心の安定という「いつも通り」を乱す行為に他なりません。
すると脳は、「異常事態だ!」と判断し、多大なエネルギーを使って元の安定した状態に戻ろうと必死に働きます。
この、元の状態に戻ろうとする働きこそが、疲労感の大きな原因となるのです。
「いつもと違う」は脳にとっての非常事態
脳にとって、いつもと違う行動や環境は、予測不能な「非常事態」です。
新しい場所、初めて会う人、慣れない作業。
これらは全て、脳が過去のデータを持っていない未知の情報です。
そのため、脳は「危険はないか?」「どう対処すればいい?」と、フル回転で情報を処理し、安全を確認しようとします。
この常にアンテナを張り巡らせている「アラートモード」の状態は、脳に大きな負荷をかけ続けます。
楽しんでいる間はアドレナリンなどが出ているため気づきにくいですが、活動が終わり、一人になって安心した瞬間に、蓄積された脳の疲れがどっと押し寄せてくるのです。
普段しないことをする時に働く心理とは?無意識の緊張と情報過多
脳の仕組みだけでなく、私たちの「心」の働きも、疲れに大きく影響しています。
普段しないことに挑戦する時、私たちは意識している以上に、様々な心理的な影響を受けているのです。

見えない鎧をまとっている?無意識の緊張
「新しい職場でうまくやらなきゃ」「初めてのデートで失敗したくない」「プレゼンを成功させないと」。
普段しないことに取り組む時、私たちは無意識のうちに「ちゃんとやらなければ」というプレッシャーを感じています。
この心理的なプレッシャーは、自分でも気づかないうちに心と体に緊張をもたらします。
肩に力が入り、呼吸は浅くなり、全身の筋肉がこわばる。
まるで、見えない鎧をまとっているかのような状態です。
この緊張状態が長時間続くと、血行が悪くなり、疲労物質が溜まりやすくなります。
「好きなことに挑戦しているはずなのに、なぜか肩が凝る」というのは、まさにこの無意識の緊張が原因かもしれません。
楽しいという気持ちと、うまくやりたいという緊張感が同時に存在することで、心と体のエネルギーがどんどん消耗されていくのです。
脳のメモリ不足?「ワーキングメモリ」と情報過多
私たちの脳には、「ワーキングメモリ」と呼ばれる、情報を一時的に記憶し処理するための機能があります。
これはよく「脳の作業台」に例えられます。
作業台が広ければ、たくさんの道具や材料を広げて効率よく作業ができますよね。
しかし、慣れない作業や新しい環境では、この作業台が情報で溢れかえってしまいます。
例えば、新しい職場なら、新しい業務内容、新しいシステムの使い方、同僚や上司の顔と名前、オフィスのどこに何があるか…など、処理しなければならない情報が一度に押し寄せます。
これは、脳の作業台に無数の道具や資料が散らかった「情報過多」の状態です。
脳は、この散らかった情報を整理し、必要なものと不要なものを仕分けるために必死に働きます。
この情報処理にワーキングメモリのリソースが大量に割かれることで、脳はエネルギーを激しく消耗し、いわゆる「脳疲労」を引き起こしてしまうのです。
【HSP・内向的な人向け】刺激に敏感で人より疲れやすい理由
もしあなたが、「他の人よりも疲れやすいかもしれない」と感じているなら、それは生まれ持った気質が関係している可能性があります。
特に、HSPや内向的といった特性を持つ人は、いつもと違うことをする際に、より多くのエネルギーを消費する傾向があるのです。

HSP(Highly Sensitive Person)とは?
HSPとは、「Highly Sensitive Person(ハイリー・センシティブ・パーソン)」の略で、「非常に感受性が強く、敏感な気質を持った人」のことを指します。
これは病気や障がいではなく、生まれ持った個性の一つです。
HSPには、主に4つの特徴があると言われています。
- D (Depth of processing): 物事を深く、多角的に考える
- O (Overstimulation): 刺激を過剰に受けやすく、疲れやすい
- E (Emotional reactivity and high Empathy): 感情の反応が強く、共感力が高い
- S (Sensitivity to Subtleties): ささいな刺激(光、音、匂いなど)を察知する
これらの頭文字をとって「DOES(ダズ)」と呼ばれます。
なぜHSPの人は疲れやすいのか
HSPの人は、そうでない人と比べて、同じ体験をしてもより多くの情報をキャッチし、それを深く処理しようとします。
例えば、カフェでお茶をするだけでも、店内のBGMの音量、隣の席の人の会話、店員さんの表情、照明の明るさ、コーヒーの香りなど、あらゆる情報を無意識のうちに詳細に受け取ってしまいます。
そのため、脳は常にフル稼働状態。
いつもと違う場所へ行ったり、初めての体験をしたりすることは、HSPの人にとって、まるで情報の洪水に飲み込まれるようなものです。
一つひとつの刺激が脳への大きな負担となり、エネルギーを激しく消耗するため、他の人よりも早く、そして深く疲労を感じてしまうのです。
内向的な気質とエネルギーの関係
HSPと混同されやすいですが、内向的な気質も疲れやすさと関連があります。
心理学では、エネルギーをどこから得るかによって「外向型」と「内向型」に分けられることがあります。
外向的な人は、人との交流や外部からの刺激によってエネルギーを得るのに対し、内向的な人は、一人の時間や自分の内なる世界からエネルギーを得ます。
そして、外部からの刺激、特に人との社交的な関わりによってエネルギーを消耗する傾向があります。
そのため、内向的な人にとって、いつもと違うことをする(特に大勢の人がいる場所へ行く、初対面の人と話すなど)のは、バッテリーを急速に消費するような行為です。
楽しかったとしても、活動が終わる頃にはエネルギーが空っぽになり、充電のために一人の時間や静かな環境が不可欠になるのです。
いつもと違うことをするのは、知らず知らずのうちにストレスになっている?
「新しい挑戦は成長のために良いことだ」とよく言われます。
それは事実ですが、同時に、その挑戦が知らず知らずのうちに心身へのストレスになっている可能性も忘れてはなりません。

コンフォートゾーンを抜けるということ
私たちには誰にでも、「コンフォートゾーン(快適な領域)」と呼ばれる心理的な安全地帯があります。
これは、慣れ親しんだ環境や人間関係、行動パターンなど、ストレスなく安心して過ごせる領域のことです。
いつもと違うことをする、というのは、このコンフォートゾーンから一歩踏み出す行為に他なりません。
コンフォートゾーンの外は、未知で予測不能な世界。
そこへ足を踏み入れることには、当然ながら不安や緊張、つまりストレスが伴います。
もちろん、このストレスは成長のために必要な「良いストレス(ユーストレス)」である場合も多いです。
しかし、ストレスはストレス。
コンフォートゾーンを抜けるという行為そのものが、私たちの心身に負荷をかけているという事実は変わりません。
「楽しい」と「ストレス」は両立する
ここで重要なのは、「楽しい」という感情と「ストレスを感じる」という反応は、矛盾することなく両立するということです。
例えば、海外旅行を考えてみましょう。
美しい景色を見たり、美味しいものを食べたりするのは、間違いなく楽しい体験です。
しかしその一方で、飛行機での長距離移動、慣れない言語でのコミュニケーション、予期せぬトラブルへの対処など、多くのストレス要因も同時に存在しています。
「楽しい」というポジティブな感情が、こうしたストレス反応を覆い隠してしまうため、旅行中は疲れに気づきにくいのです。
しかし、体や脳は正直です。
旅行から帰ってきて、安心できる日常に戻った瞬間に、蓄積されていたストレスが一気に表面化し、「どっと疲れた」と感じるわけです。
これは、仕事や趣味、人間関係など、あらゆる「いつもと違うこと」に当てはまります。
スピリチュアルな視点?いつもと違うことをする時の潜在意識の変化
これまで脳科学や心理学の視点から疲れの原因を探ってきましたが、少し違った角度からこの現象を捉える考え方もあります。
ここでは、スピリチュアルな観点から、いつもと違うことをする意味について触れてみましょう。
これは科学的な根拠とは異なりますが、心を軽くする一つのヒントになるかもしれません。

人生の転機や好転反応という捉え方
スピリチュアルな世界では、理由もなく「いつもと違うことをしてみたくなった」と感じる時、それは人生のステージが変わる前触れや、魂が新しい成長を求めているサインだと捉えることがあります。
そして、その新しい挑戦に伴う疲れや一時的な不調を、体が新しいエネルギーレベルに適応しようとしている過程で起こる「好転反応」と見るのです。
つまり、疲れは悪いものではなく、より良い方向へ進むために必要なプロセスだという考え方です。
こう考えると、今の疲れが未来へのポジティブな変化の一部だと思えて、少し気持ちが楽になるかもしれません。
潜在意識が変化を求めている?
私たちの意識には、自分で自覚できる「顕在意識」と、自覚できない無意識の領域である「潜在意識」があると言われています。
そして、日々の行動の9割以上は、この潜在意識によってコントロールされているという説もあります。
この考え方に基づけば、「いつもと違うことをしたい」という衝動は、あなたの潜在意識が「今のままではいけない」「もっと成長したい」と、現状からの脱却や変化を強く求めているサインだと解釈することもできます。
普段はコンフォートゾーンに留まろうとする意識の壁を越えて、潜在意識からのメッセージが行動に現れた結果、いつもと違うことをするのかもしれません。
その変化の過程で、古いエネルギーを手放し、新しいエネルギーを取り入れるために心身が働き、一時的に疲労を感じるのは、ごく自然なプロセスだと捉えることもできるでしょう。
いつもと違うことをして疲れる悩みを解消!今日からできる5つのセルフケア
いつもと違うことをすると疲れる原因が、脳や心の仕組みにあることがお分かりいただけたでしょうか。
原因が分かれば、次はいよいよ対策です。
「疲れるのは仕方ない」と諦める必要はありません。
ここでは、疲れを上手にコントロールし、新しい挑戦を心から楽しむために、今日からすぐに実践できる具体的なセルフケア方法を5つご紹介します。
自分に合った方法を見つけて、ぜひ試してみてください。

【軽減法1】例えばこんなことから!「いつもと違うこと」を少しずつ日常に取り入れる
大きな変化が脳にとってストレスになるなら、まずは脳が「変化した」と気づかないくらいの小さな変化から始めてみましょう。
大切なのは、「いつもと違うこと」への耐性を少しずつ養っていくことです。
なぜ「少しずつ」が重要なのか?
いきなり大きな挑戦をすると、脳は「非常事態だ!」と強い抵抗を示し、大量のエネルギーを消費してしまいます。
しかし、ほんの些細な変化であれば、脳はそれを「いつも通り」の範囲内だと認識しやすく、抵抗が少なくて済みます。
この小さな成功体験を繰り返すことで、脳は「いつもと違うこと=安全なこと」と学習していきます。
すると、これまでコンフォートゾーンの外側だった領域が、少しずつ内側に取り込まれ、快適に過ごせる範囲が広がっていくのです。
これを「慣れ」の効果と呼びます。
焦らず、スモールステップで脳を慣らしていくことが、疲れを軽減する一番の近道です。
日常でできる「小さな非日常」の具体例
難しく考える必要はありません。
例えば、以下のようなことから始めてみてはいかがでしょうか。
- 通勤・通学ルートを一本だけ変えてみる: 見慣れない景色が脳に新鮮な刺激を与えます。
- いつものカフェで、違う席に座ってみる: 視点が変わるだけで、気分も変わります。
- コンビニで、いつもは買わない飲み物を買ってみる: 新しいお気に入りが見つかるかもしれません。
- 歯を磨く順番を変えてみる: 無意識で行っている行動を、少しだけ意識的に変えてみましょう。
- 寝る前に5分だけ、普段聴かないジャンルの音楽を聴いてみる: 新しい世界への扉が開くきっかけになるかもしれません。
こうした「小さな非日常」は、脳にとって適度な負荷となり、変化に対応する良いトレーニングになります。
【軽減法2】挑戦のハードルを下げる「ベイビーステップ」思考法
何か新しいことを始めようとする時、「やらなきゃ」という気持ちが大きすぎて、行動する前から疲れてしまうことはありませんか?
そんな時は、目標を極限まで小さく分解する「ベイビーステップ」という考え方が非常に有効です。

「ベイビーステップ」とは?
ベイビーステップとは、その名の通り「赤ちゃんの一歩」のように、目標を達成不可能なほど小さなステップに細かく分解する思考法です。
あまりにも簡単で、「こんなことで意味があるの?」と思うくらいのレベルまでハードルを下げることがポイントです。
どんなに小さな一歩でも、踏み出せばゼロではなくなります。
この最初の一歩を踏み出すことの心理的抵抗を極限までなくすのが、ベイビーステップの狙いです。
具体的な分解の方法
例えば、「健康のために毎日30分ウォーキングする」という目標を立てたとします。
これを行動に移せない場合、ベイビーステップで以下のように分解してみましょう。
- Step 1: ウォーキングウェアに着替える
- Step 2: 玄関まで行く
- Step 3: 靴を履く
- Step 4: ドアを開けて、外に1分だけ出る
- Step 5:家の周りを5分だけ歩く
もしStep 1の「ウェアに着替える」ことさえできれば、その日は目標達成です。
この方法の素晴らしいところは、「やる気」という不確かなものに頼らずに行動を始められる点です。
行動を起こすと、脳の側坐核という部分が刺激され、やる気物質であるドーパミンが分泌されます。
つまり、「やる気があるから行動する」のではなく、「行動するからやる気が出る」のです。
このベイビーステップで行動への抵抗をなくし、脳を上手に乗せてあげましょう。
【軽減法3】「いつもと違うことをする」のは失敗してもOKと考える
いつもと違うことをする時に感じる疲れの原因の一つに、「失敗してはいけない」という無意識のプレッシャーがあります。
このプレッシャーから自分を解放するだけで、心は驚くほど軽くなります。

「完璧主義」が疲れを増幅させる
「せっかくやるなら完璧にこなしたい」「人に笑われたくない」。
こうした完璧主義的な思考は、挑戦に伴うストレスを何倍にも増幅させます。
常に100点を目指していると、行動する前から緊張し、小さなミスでひどく落ち込んでしまいます。
これでは、心身ともに疲弊してしまうのも当然です。
大切なのは、完璧主義を手放し、「60点で上出来」「できたらラッキー」くらいの気持ちで臨むことです。
100点を目指すから疲れるのであって、最初から60点を目指していれば、心に大きな余裕が生まれます。
挑戦の目的を「体験」にシフトする
結果や成果にこだわりすぎると、挑戦は苦しいものになってしまいます。
そこで、挑戦の目的そのものを「結果を出すこと」から「体験すること」へとシフトさせてみましょう。
「上手くやる」のではなく、「ただ、やってみる」。
「成功する」のではなく、「どんな感じか味わってみる」。
このように考えると、「失敗」という概念そのものがなくなります。
そこにあるのは、「こういう結果になった」というデータと、「こういうことを学べた」という経験だけです。
このマインドセットを持つことで、プレッシャーから解放され、プロセスそのものを純粋に楽しめるようになります。
結果として、余計な緊張による心身の消耗を防ぎ、疲れを大きく軽減することができるでしょう。
【軽減法4】いつもと違う自分に気づき、自分の「疲れのサイン」を理解する
疲れを上手にコントロールするためには、無理をしすぎる前に「あ、今疲れてきているな」と自分自身の状態に気づくことが何よりも重要です。
そのためには、自分を客観的に観察する視点を持つことが役立ちます。

「メタ認知」で自分を客観視する
メタ認知とは、自分自身の思考や感情、行動を、もう一人の自分が少し離れた場所から客観的に認識する能力のことです。
「なんだかイライラしてきたな」「集中力が切れてきたみたいだ」「人と話すのが億劫に感じているな」。
このように、自分の心や体の変化にリアルタイムで気づくことができれば、早めに対処することが可能になります。
いつもと違うことをしている最中に、時々ふっと立ち止まり、「今の自分、どんな感じ?」と心の中で問いかけてみる習慣をつけてみましょう。
あなただけの「疲れのサイン」を見つけよう
疲れのサインは、人によって様々です。
頭痛として現れる人もいれば、急に無口になる人もいます。
あなたが「疲れてきたな」と感じる時、心や体にどんな変化が現れるでしょうか。
自分だけの「疲れのサイン」を事前に知っておくことは、セルフケアにおいて非常に重要です。
以下に代表的なサインの例を挙げますので、自分に当てはまるものがないかチェックしてみてください。
- 身体的なサイン:
- 頭が重い、痛い
- 肩や首が凝る
- 目がしょぼしょぼする、かすむ
- 強い眠気を感じる
- 食欲がなくなる、または異常に食べたくなる
- 些細なことで動悸がする
- 精神的なサイン:
- イライラしやすくなる
- 集中力が続かない、ミスが増える
- 普段は気にならない物音が気になる
- 何もかもが面倒に感じる
- 人と話すのが億劫になる
これらのサインに気づいたら、それは心と体からの「少し休んで」というメッセージです。
そのサインを無視せず、次のステップでご紹介する休息を意識的に取り入れましょう。
より詳しくご自身のストレス状態をチェックしたい方は、厚生労働省の「こころの耳」で紹介されているセルフケアのページも参考にしてみてください。
【軽減法5】脳を休ませる意識的な休息とおすすめリフレッシュ方法
疲れた時には、ただ休むだけでなく、「脳を積極的に休ませる」という意識を持つことが大切です。
特に、いつもと違うことをして情報過多になっている脳には、質の高い休息が必要です。

休息も「攻め」の姿勢で!意識的な休息とは
疲れたからといって、ソファに寝転がってスマートフォンをだらだらと眺めていませんか?
実は、SNSやニュースサイトを次々と見ている間も、脳は情報を処理し続けており、本当の意味で休むことができていません。
「休息」とは、ただ何もしないことではありません。
脳への情報入力を意図的に遮断し、クールダウンさせる時間を作ること。
これが「攻めの休息」、つまり意識的な休息です。
新しい挑戦でフル回転した脳をいたわるために、効果的なリフレッシュ方法を生活に取り入れましょう。
おすすめのリフレッシュ方法
ここでは、脳を効果的に休ませるためのおすすめのリフレッシュ方法をいくつかご紹介します。
- デジタルデトックス:
寝る前の1時間や、休日の午前中など、時間を決めてスマートフォンやパソコン、テレビから意識的に離れてみましょう。
外部からの情報が遮断され、脳が静けさを取り戻します。 - 自然に触れる:
近くの公園を少し散歩したり、ベランダで空を眺めたり、観葉植物をぼーっと眺めるだけでも効果があります。
木々の緑や鳥のさえずり、風の音といった自然の刺激は、情報過多になった脳をリラックスさせてくれます。 - 軽い運動:
激しい運動はかえって体を疲れさせますが、ウォーキングやストレッチ、ヨガなどの軽い有酸素運動は、全身の血行を促進し、気分をリフレッシュさせるのに最適です。
特に、一定のリズムで行う運動は、幸せホルモン「セロトニン」の分泌を促すとも言われています。 - 睡眠の質を高める:
睡眠は、脳が情報を整理し、心身の疲労を回復させるための最も重要な時間です。
寝る前はリラックスできる音楽を聴いたり、ぬるめのお風呂にゆっくり浸かったりして、質の高い睡眠を心がけましょう。 - 何もしない時間を作る:
これが最もシンプルで、かつ効果的な脳の休息法かもしれません。
ソファや椅子に座り、何も考えず、ただぼーっと窓の外を眺める。
5分でも10分でも構いません。
意図的に「思考を止める」時間を持つことで、脳を本当に休ませてあげましょう。
いつもと違うことに挑戦するあなたは、とても素敵です。
その挑戦を心から楽しみ、長く続けていくために、ぜひ今回ご紹介したセルフケアを試してみてください。
自分を上手にいたわりながら、新しい世界の扉をどんどん開いていってくださいね。
まとめ:いつもと違うことをすると疲れるのは自然な反応!上手に乗りこなすヒント
今回は、いつもと違うことをすると疲れる根本的な原因と、その疲れを上手に乗りこなすための具体的なセルフケア方法について詳しく解説してきました。
新しい挑戦や慣れない環境でどっと疲れてしまうのは、決してあなたの気持ちが弱いからではありません。
むしろ、脳が変化から身を守ろうとする「恒常性」という仕組みや、無意識の緊張といった、ごく自然な心身の反応なのです。
特に、繊細な気質を持つHSPの方や内向的な方は、より多くの刺激を処理するため、疲れやすい傾向があることも理解できたかと思います。
重要なのは、この疲れを「悪いもの」と決めつけずに、自分の心と体が発しているサインとして受け止めることです。
そして、ご紹介した5つのセルフケアを試してみてください。
- 日常に「小さな非日常」を取り入れる
- 「ベイビーステップ」で行動のハードルを下げる
- 「失敗してもOK」と完璧主義を手放す
- 自分だけの「疲れのサイン」に気づく
- 「意識的な休息」で脳をクールダウンさせる
これらのヒントを参考に、自分を上手にいたわりながら、新しい挑戦を楽しんでいきましょう。
コンフォートゾーンを一歩踏み出すあなたの勇気は、間違いなくあなたを成長させてくれます。
その過程で感じる疲れと上手に付き合いながら、あなたらしいペースで、軽やかに未来へ進んでいってくださいね。