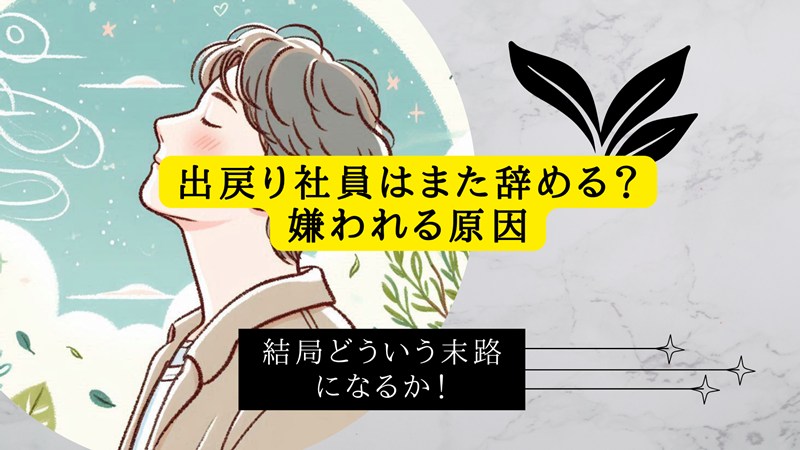一度は離れた会社に、再び戻ってきた出戻り社員。
しかし、残念ながら『出戻り社員はまた辞める』という話を耳にすることも少なくありません。
なぜ、彼らは再び退職の道を選んでしまうのでしょうか。
そして、周囲から『嫌われる』といったネガティブな印象を持たれてしまうこともあるのでしょうか。

この記事では、出戻り社員が早期に退職してしまう背景にある理由や、企業と社員双方が後悔しないための対策について、わかりやすく解説していきます。
- 出戻り社員はなぜまた辞める?嫌われると言われる背景や結局の理由
- 出戻り社員がまた辞めるのを防ぐ!定着のための対策と結局どうすべきか
出戻り社員はなぜまた辞める?嫌われると言われる背景や結局の理由
一度退職した会社へ戻る「出戻り」という選択。期待と不安が入り混じる中での再スタートですが、残念ながら長続きせずに再び退職してしまうケースも散見されます。「出戻り社員はまた辞める」と言われることもありますが、その背景にはどのような理由があるのでしょうか。また、周囲から「嫌われる」といったネガティブな感情を抱かれてしまうのは、一体なぜなのでしょうか。
ここでは、出戻り社員が再び会社を去る主な原因や、彼らが直面しがちな人間関係の問題、そして結局どのような状況に至りやすいのかを深掘りしていきます。
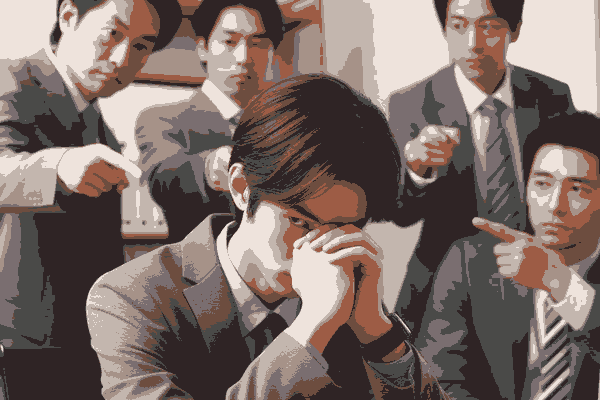
出戻り社員が結局また辞めてしまう主な理由とは?
出戻り社員が再び退職を選ぶ背景には、いくつかの共通した理由が見られます。一度会社を経験しているからこその期待と現実のギャップや、変化への適応の難しさが影響していることが多いようです。
以前の退職理由が解消されていなかった
最も大きな原因の一つは、以前退職した際の根本的な理由が、実は解消されていなかったというケースです。例えば、人間関係の悩み、評価制度への不満、キャリアアップの望めない環境などが挙げられます。会社側から「改善された」と説明を受けていたとしても、実際に働いてみると表面的な変化に過ぎず、本質的な問題は手つかずのままだったという状況です。
- 人間関係の再燃: 以前苦手だった上司や同僚がまだ在籍しており、関係性が改善されていない、あるいは新たな火種が生まれる。
- 業務内容のミスマッチ: 期待していた業務内容と異なり、結局以前と同じような不満を抱える。
- 企業文化への再不適応: 一度は受け入れようとした企業文化に、やはり馴染めないと感じる。
これらの問題が再燃すると、「やはりこの会社ではダメだった」という思いが強まり、早期の再退職へと繋がってしまいます。
入社前の期待と現実のギャップ
出戻り社員は、以前の在籍経験から「勝手知ったる」という安心感と同時に、会社や自身の成長に対する期待を抱いて再入社することが多いです。しかし、会社も社員も時間と共に変化します。
- 会社の変化についていけない: 会社の事業方針の転換、組織体制の変更、新しいツールの導入など、浦島太郎状態に陥り、変化への適応に苦労する。
- 自身のスキルや経験への過信: 以前の成功体験が通用せず、新しい環境で求められるスキルや成果を出せないことに焦りを感じる。
- 待遇面での不満: 再入社時の条件交渉がうまくいかず、給与や役職が期待していたものと異なり、モチベーションが低下する。
「こんなはずではなかった」というギャップは、出戻り社員の心に影を落とし、再び会社を離れる決断を後押しすることがあります。
新しい環境への適応の難しさ
一度退職しているという事実は、良くも悪くも周囲からの注目を集めます。新しい環境にスムーズに溶け込み、再び信頼関係を構築していく過程は、想像以上にエネルギーを要します。
- 周囲の目線へのプレッシャー: 「また辞めるのでは」「お手並み拝見」といった無言のプレッシャーを感じ、萎縮してしまう。
- 既存社員との溝: 自分がいなかった間に形成された人間関係や業務の進め方があり、疎外感を覚えてしまう。
- 新しいルールのキャッチアップ不足: 以前のやり方に固執してしまい、新しいルールやフローへの適応が遅れる。
これらの要因が複合的に絡み合い、結果として「やはりここではないのかもしれない」という結論に至り、出戻り社員が結局また辞めてしまうというケースが多く見受けられるのです。
出戻り社員が「嫌われる」と言われるのは本当?その原因を探る
「出戻り社員は嫌われる」という言葉を耳にすることがありますが、これは必ずしも全てのケースに当てはまるわけではありません。しかし、一部の出戻り社員が周囲からネガティブな印象を持たれてしまう背景には、いくつかの要因が考えられます。誤解やコミュニケーション不足が原因であることも少なくありません。

過去の退職理由や経緯への不信感
出戻り社員に対して、既存社員が過去の退職理由や会社を辞めた経緯に疑問や不信感を抱いている場合があります。
- 「なぜ辞めたのに戻ってきたの?」という素朴な疑問: 特に円満退社でなかった場合や、会社への不満を口にして辞めた場合、その真意を測りかねる社員もいます。
- 「またすぐに辞めるのでは?」という警戒心: 一度会社を離れたという事実は、「また同じように簡単に辞めてしまうのではないか」という不安を周囲に抱かせることがあります。
- 特別扱いされているのではという不公平感: もし出戻りに際して特別な条件が提示されていると噂された場合、既存社員が不公平感を抱き、それが嫌悪感に繋がることもあります。
これらの感情は、直接的な言葉として表現されなくても、態度や雰囲気として出戻り社員に伝わり、孤立感を深める原因となることがあります。
「昔取った杵柄」的な態度や言動
出戻り社員の中には、過去の在籍経験や知識を過度にアピールしたり、現在のやり方を批判したりするような、いわゆる「昔取った杵柄」的な態度を取ってしまう人がいます。
- 「私のいた頃はこうだった」発言: 会社の変化を理解せず、過去のやり方に固執し、新しい方法を学ぼうとしない姿勢は、周囲の反感を買います。
- 上から目線のアドバイス: 既存社員の努力や工夫を軽視するような、一方的なアドバイスや指摘は、人間関係を悪化させます。
- 変化への不適応を正当化する: 新しいルールやシステムに対して「分かりにくい」「効率が悪い」と不満を漏らし、自身の適応不足を棚に上げる態度は、協力的な関係を築く上で障害となります。
このような言動は、既存社員から「扱いにくい」「協調性がない」と見なされ、結果として「嫌われる」という状況を招きかねません。
周囲の期待と本人のパフォーマンスの乖離
出戻り社員に対して、会社や同僚は「即戦力」としての期待を抱きがちです。しかし、ブランクがあったり、会社の状況が大きく変わっていたりすると、期待されたほどのパフォーマンスをすぐに発揮できないことがあります。
- 期待外れによる失望感: 「経験者なのに仕事ができない」「以前はもっと活躍していたはず」といった失望感が、周囲の評価を下げてしまうことがあります。
- 過度なプレッシャーによる空回り: 周囲の期待を過剰に意識しすぎてしまい、焦りからミスを連発したり、本来の力を発揮できなかったりすることも。
- コミュニケーション不足による誤解: 成果が出ない理由や現状の課題について、周囲とのコミュニケーションが不足していると、誤解が生じやすくなります。
パフォーマンスが期待に満たない状態が続くと、出戻り社員自身も肩身の狭い思いをし、周囲も「なぜ再雇用したのか」という疑問を抱き始め、関係性が悪化する可能性があります。大切なのは、過度な期待をせず、現実的な目標設定と十分なコミュニケーションを図ることです。
出戻り後に「情けない」と感じる瞬間とメンタルの保ち方
出戻り転職は、新たなスタートであると同時に、過去の自分や環境と向き合う機会でもあります。その過程で、予期せぬ困難に直面し、「情けない」と感じてしまう瞬間もあるかもしれません。しかし、そのような感情は決して珍しいものではなく、適切に対処することで乗り越えられます。
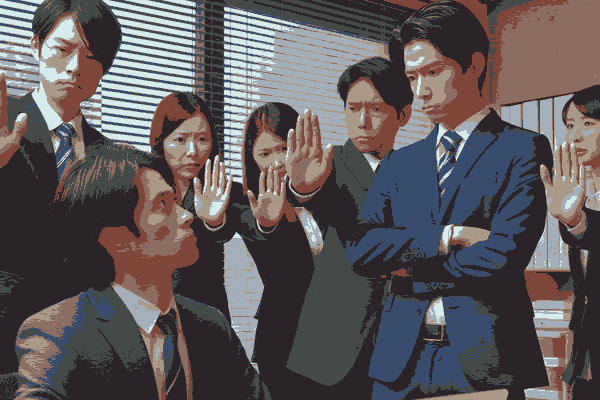
想像していたよりも評価されない
- 過去の実績が通用しない: 以前の部署やチームでは高く評価されていたスキルや経験が、新しい環境では思うように活かせず、期待した評価を得られないことがあります。特に、会社が大きく変化していたり、異なる部署に配属されたりした場合に起こりやすいです。
- 新しい上司や同僚との価値観のズレ: 評価基準や仕事の進め方について、新しい上司や同僚との間に認識のズレがあると、正当に評価されていないと感じてしまうことがあります。
- 「出戻りだから」という色眼鏡で見られる不安: 周囲から「出戻りだから大したことはないだろう」あるいは「出戻りだから当然できて当たり前」といった先入観で見られているのではないかと感じ、それが自己評価の低下に繋がることもあります。
このような時、「自分はこんなはずではなかった」「情けない」と感じてしまうかもしれません。しかし、大切なのは、過去の栄光に固執せず、現在の環境で求められている役割を理解し、新しいスキルを習得する謙虚さを持つことです。また、周囲とのコミュニケーションを密にし、期待値のすり合わせを行うことも重要です。
周囲の目が気になりすぎる
- 「また辞めるのでは」という視線への過敏さ: 一度退職した経験があるため、周囲から「またすぐに辞めてしまうのではないか」と疑われているように感じ、些細な言動にも気を遣いすぎて疲弊してしまうことがあります。
- 同僚との間に壁を感じる: 以前は親しかった同僚が、出戻り後はどこかよそよそしく感じたり、新しい人間関係の輪に入りづらかったりすると、孤独感や疎外感を覚え、「情けない」と感じることがあります。
- 失敗を過度に恐れる: 「出戻りなのに失敗できない」というプレッシャーから、新しい挑戦を避けたり、ミスを過度に恐れたりするようになり、本来の力を発揮できなくなることがあります。
周囲の目が気になるのは自然なことですが、過度に気にしすぎると精神的に追い詰められてしまいます。自分自身の目標に集中し、誠実に仕事に取り組む姿勢が、徐々に周囲の信頼を回復していく鍵となります。また、信頼できる人に相談したり、客観的な意見を聞いたりすることも、メンタルを保つ上で助けになります。
メンタルを保つための具体的な方法
出戻り後に「情けない」と感じる状況を乗り越え、健全なメンタルを保つためには、以下のような具体的な方法が考えられます。
- 小さな成功体験を積み重ねる: 大きな成果を急ぐのではなく、日々の業務の中で達成可能な小さな目標を設定し、それをクリアしていくことで自信を取り戻します。
- 客観的な視点を持つ: 状況を悲観的に捉えすぎず、何が問題で、どうすれば改善できるのかを客観的に分析します。必要であれば、上司や同僚にフィードバックを求め、現状認識のズレを修正します。
- 自分を過度に責めない: 誰にでもうまくいかない時期はあります。「情けない」と感じる自分を否定せず、そのような感情も受け入れた上で、前向きな行動に移すことが大切です。
- 社外に相談相手を見つける: 会社の人には話しにくい悩みや不安を、社外の友人や家族、あるいはキャリアコンサルタントなどに相談することで、客観的なアドバイスを得られたり、精神的な支えになったりします。
- オンとオフの切り替えを意識する: 仕事の悩みやストレスをプライベートに持ち込まないよう、趣味や休息の時間を大切にし、心身のリフレッシュを図ります。
出戻り後の環境で「情けない」と感じることは、成長の機会でもあります。その感情と向き合い、建設的な対処法を見つけることで、より強く、たくましく働くことができるようになるでしょう。
もし、仕事上の悩みやストレスで、どうしてもつらいと感じる場合は、一人で抱え込まずに専門機関に相談することも考えてみましょう。厚生労働省が運営する働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」では、ストレス対処法や相談窓口に関する様々な情報が提供されています。
短期間で再び退職?出戻り社員が一週間で辞めるケース
信じられないかもしれませんが、出戻り社員が再入社後、わずか一週間という短期間で再び退職を決意するケースも、稀ではありますが存在します。このような超早期退職は、企業側にとっても本人にとっても大きな痛手となります。一体どのような背景があるのでしょうか。
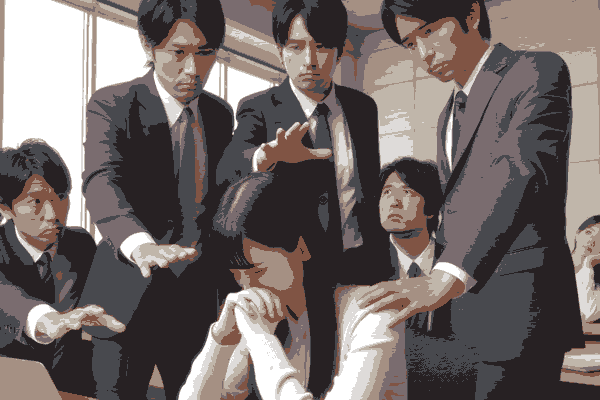
入社直後に判明する「聞いていた話と違う」
- 労働条件の相違: 面接時や内定時に提示された給与、勤務時間、休日などの労働条件が、入社初日に確認した雇用契約書の内容と異なっていた、あるいは口頭での説明と実態が大きくかけ離れていたというケースです。特に、曖昧な説明を受けていた部分が、入社して初めて明確になり、それが受け入れがたい内容だった場合、即座に退職を決意することもあります。
- 業務内容の大きな変更: 事前に聞かされていた業務内容と、実際に割り当てられた業務が全く異なっていた、あるいは、聞いていなかった困難な業務や責任をいきなり負わされた場合などです。「これなら以前の会社を辞める必要はなかった」「これでは自分のキャリアを活かせない」と感じ、早期の離脱に繋がります。
- 配属部署やチームの雰囲気の悪さ: 事前の職場見学などでは分からなかった、配属先の極端な人間関係の悪さや、ハラスメントが横行しているような劣悪な職場環境を目の当たりにし、精神的な苦痛から即座に退職を選ぶケースもあります。
このような「聞いていた話と違う」という状況は、会社への信頼を根底から揺るがし、「ここに居続けることはできない」という強い拒否感を生みます。
致命的なミスマッチの発覚
- 企業文化への決定的な不適合: 以前在籍していた頃とは企業文化が大きく変貌しており、どうしても受け入れられない価値観や働き方を強要された場合です。例えば、極端なトップダウンの指示系統や、個人の意見が全く尊重されない風土など、自身の働き方と根本的に相容れないと感じると、短期間での退職もやむなしと判断することがあります。
- スキルや経験が全く通用しない: 自分の持っているスキルや経験が、新しい環境では全く役に立たない、あるいは時代遅れであると痛感し、貢献できる見込みがないと感じた場合です。特に、即戦力として期待されていたプレッシャーと、現実のスキルギャップに打ちのめされ、自信を喪失してしまうこともあります。
- 深刻な人間関係のトラブル: 入社早々、上司や同僚との間で修復不可能なほどの人間関係のトラブルに巻き込まれたり、孤立してしまったりした場合です。特に、出戻りという立場が影響し、周囲から不当な扱いを受けたと感じた場合、早期に見切りをつけることもあります。
一週間という短期間での退職は、本人にとっても不本意な結果であることがほとんどです。入社前の情報収集や、企業側との認識合わせがいかに重要であるかを示唆しています。企業側も、受け入れ前の丁寧な説明と、入社後のフォローアップ体制を整えることが、このような不幸な事態を避けるために不可欠です。
会社への出戻りで後悔…よくあるミスマッチのパターン
会社への出戻りを決断する際、多くの人が「今度こそは」という期待を抱きます。しかし、実際に再入社してみると、思い描いていた理想と現実の間にギャップを感じ、後悔してしまうケースも少なくありません。ここでは、出戻り社員が陥りやすいミスマッチのパターンを見ていきましょう。

「昔の自分」と「今の自分」の認識のズレ
- 過去の成功体験への固執: 以前在籍していた時に成功したやり方や、評価された自分のイメージに固執してしまうパターンです。しかし、会社も市場も常に変化しています。過去のやり方が通用しなくなっていたり、求められる役割が変わっていたりすることに気づかず、周囲との間に摩擦が生じることがあります。「昔はこれでうまくいったのに」という思いが強すぎると、新しい環境への適応を妨げ、結果として「こんなはずではなかった」と後悔する原因になります。
- 自身の成長への過信または過小評価: 一度会社を離れて経験を積んだことで、「自分は成長した」と過信し、再入社後の職務内容や待遇に不満を感じるケースがあります。逆に、ブランクがあることで「自分はもう通用しないのではないか」と過小評価し、実力以下の仕事に甘んじてしまい、やりがいを感じられずに後悔することもあります。客観的な自己分析と、現在の会社が求める人物像とのすり合わせが重要です。
- 「出戻りだから」という甘えや遠慮: 「以前いたから大丈夫だろう」という甘えから、新しい情報やルールを積極的に学ぼうとしなかったり、逆に「出戻りだから迷惑をかけられない」と過度に遠慮してしまい、必要なコミュニケーションを取れなかったりするのもミスマッチの一因です。
会社の変化についていけない「浦島太郎状態」
- 組織文化や社風の変化: 数年ぶりに戻ってみると、経営陣が変わっていたり、企業理念が見直されていたりして、以前とは全く異なる組織文化になっていることがあります。かつての「アットホームな雰囲気」が「成果主義のドライな環境」に変わっていたりすると、戸惑いを感じ、馴染めずに孤立してしまうことも。「知っている会社」だと思っていたのに、実際は「全く新しい会社」に入ったような感覚に陥り、後悔につながります。
- 業務プロセスやシステムの進化: 業務で使うツールやシステムが刷新されていたり、仕事の進め方が大きく変わっていたりすることは珍しくありません。これらの新しいやり方を覚えるのに苦労したり、以前のやり方にこだわってしまったりすると、業務効率が上がらず、周囲に迷惑をかけてしまうこともあります。変化への柔軟な対応力と学習意欲が求められます。
- 人間関係の変化: 以前親しかった同僚が退職していたり、新しいメンバーが増えていたりして、人間関係が大きく変わっていることもあります。新たに信頼関係を築く努力が必要になりますが、それがうまくいかないと、「知っている人がいない」「居場所がない」と感じてしまい、出戻りを後悔する要因となります。
これらのミスマッチを防ぐためには、出戻りを決める前に、会社の現状について可能な限り情報収集を行うこと、そして自分自身も変化に対応していく覚悟を持つことが不可欠です。また、入社後も積極的にコミュニケーションを取り、ギャップを埋めていく努力が求められます。
出戻り転職を考え直す?以前の退職理由との向き合い方
出戻り転職は、ある意味で「再チャレンジ」の機会です。しかし、その決断をする前に、一度立ち止まって冷静に考えるべき重要なポイントがあります。それは、以前、その会社を辞めた本当の理由と、今、出戻りを考えている理由を深く掘り下げることです。ここを曖昧にしたままでは、再び同じ過ちを繰り返してしまう可能性があります。
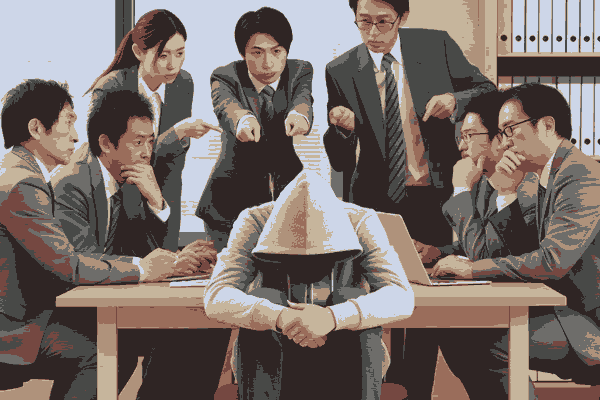
退職理由が「外的要因」だったのか「内的要因」だったのか
- 外的要因による退職:
- 会社の業績悪化、事業所の閉鎖、家庭の事情(家族の転勤、介護など)、やむを得ない人間関係のトラブル(ハラスメントなど、自身の努力ではどうにもならなかったもの)などがこれにあたります。
- もし、これらの外的要因が解消されているのであれば、出戻りを前向きに検討する余地はあるかもしれません。例えば、会社の業績が回復し安定している、問題のあった人物が異動・退職している、家庭の事情が落ち着いた、などです。
- ただし、外的要因であったとしても、その経験から会社に対してネガティブな感情が残っていないか、冷静に見つめ直す必要があります。
- 内的要因による退職:
- 仕事内容への不満、キャリアアップが見込めない、給与や待遇への不満、企業文化への不適合、自身のスキル不足を感じた、など、自分自身の価値観や能力、会社との相性に起因するものがこれにあたります。
- 内的要因で退職した場合、出戻りを検討する際にはより慎重な判断が必要です。その要因が、現在本当に解消されているのか、あるいは自分自身がその要因を受け入れられるように変化したのかを厳しく問い直す必要があります。
- 例えば、「仕事内容がつまらなかった」と感じていたなら、出戻り後に希望する業務に就ける保証はあるのか。「企業文化が合わなかった」のなら、その文化は変わったのか、あるいは自分がその文化に適応できるようになったのか、といった点です。
「なぜ今、出戻りたいのか」を明確にする
- 現状への不満からの逃避ではないか: 現在の職場や状況に不満があり、その解決策として安易に出戻りを考えていないでしょうか。「隣の芝生は青く見える」ということもあります。出戻りを考える前に、まずは現在の職場で状況を改善するための努力をしましたか?
- 過去の美化された記憶に頼っていないか: 人は過去の出来事を美化しがちです。退職した会社の良かった点ばかりを思い出していませんか? 実際に働いていた時の不満や苦労を忘れ、理想化してしまっている可能性があります。客観的に当時の状況を振り返ることが大切です。
- 具体的な目的や目標があるか: 「なんとなく居心地が良かったから」「知っている人がいるから安心」といった曖昧な理由ではなく、出戻りによって何を達成したいのか、どのようなキャリアを築きたいのか、具体的な目的や目標を持つことが重要です。それがなければ、また同じような不満を感じてしまうかもしれません。
以前の退職理由と真摯に向き合い、そして今なぜ出戻りたいのかを明確にすることで、出戻り転職が本当に自分にとって最善の選択なのかを見極めることができます。感情的な部分だけでなく、論理的かつ客観的な視点で判断することが、後悔しないための第一歩です。もし、以前の退職理由が解消されておらず、出戻りに対する明確な目的も見いだせない場合は、安易に出戻りを選択するのではなく、他の選択肢も視野に入れるべきでしょう。
出戻り社員がまた辞めるのを防ぐ!定着のための対策と結局どうすべきか
出戻り社員が再び退職してしまうという事態は、企業にとっても本人にとっても避けたいものです。一度は自社を選び、そして再び戻ってきてくれた人材を活かし、長く活躍してもらうためには、企業側の受け入れ体制の整備と、出戻り社員自身の心構えの双方が重要になります。
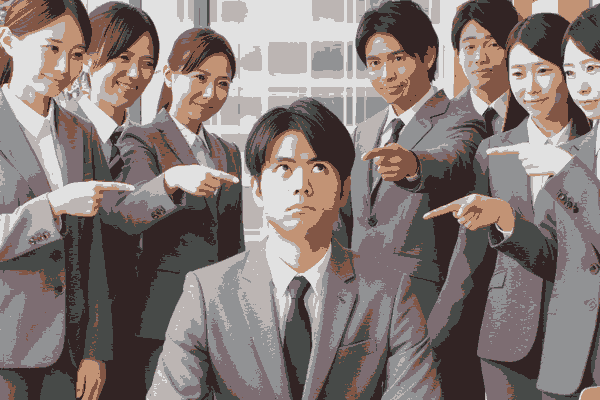
ここでは、出戻り社員の再退職を防ぎ、定着を促進するための具体的な対策と、最終的に企業と社員がどのような点に留意すべきかについて詳しく解説します。
出戻り社員の再退職を防ぐ!企業ができる具体的な対策
企業が出戻り社員を貴重な戦力として迎え入れ、その定着を促すためには、計画的かつ細やかな対応が求められます。単に「戻ってきてくれてありがとう」で終わらせず、彼らがスムーズに再スタートを切り、再び組織に貢献できるようサポートする体制づくりが不可欠です。
再入社前の丁寧なコミュニケーションと期待値調整
- 退職理由と現在の状況のヒアリング: なぜ以前退職したのか、そして現在なぜ戻りたいのか、その理由を丁寧にヒアリングします。これにより、企業側が改善すべき点や、本人が抱える期待や不安を正確に把握できます。また、ブランク期間中の経験やスキルの変化についても確認し、再入社後の役割期待とのミスマッチを防ぎます。
- 現在の会社の状況と変化点の透明な情報提供: 会社の業績、組織体制、企業文化、主要メンバー、業務内容など、以前在籍していた頃からの変化点を包み隠さず正直に伝えます。良い面だけでなく、課題や困難な点も伝えることで、入社後の「こんなはずではなかった」というギャップを最小限に抑えます。
- 役割、業務内容、待遇に関する明確な合意形成: 再入社後のポジション、具体的な業務内容、責任範囲、評価制度、給与、福利厚生などについて、曖昧さを残さず明確に提示し、双方合意の上で進めます。特に待遇面では、以前の経験やブランク期間のスキルアップを適切に評価することが、本人のモチベーション維持に繋がります。
- 懸念事項の払拭とサポート体制の説明: 本人が懸念している点(人間関係、新しい業務への適応など)があれば、それに対して企業としてどのようなサポートができるのかを具体的に説明し、安心感を与えます。
受け入れ部署への事前共有と協力体制の構築
- 出戻り社員受け入れの背景と期待の共有: 受け入れ部署のメンバーに対し、なぜその社員を再雇用するのか、どのような役割を期待しているのかを事前にしっかりと説明します。これにより、部署内での受け入れムードを醸成し、不要な憶測や誤解を防ぎます。
- 既存社員の懸念や不安への配慮: 既存社員の中には、出戻り社員に対して複雑な感情を抱く人もいるかもしれません。そのような感情にも配慮し、オープンなコミュニケーションの場を設けるなどして、円滑な関係構築をサポートします。
- メンター制度やバディ制度の導入: 受け入れ部署内に、出戻り社員をサポートするメンターやバディを任命し、業務面だけでなく精神面でも相談しやすい環境を整えます。特に、新しいルールや人間関係に慣れるまでの期間、頼れる存在がいることは大きな安心材料となります。
- 歓迎の雰囲気づくり: 形式的な挨拶だけでなく、歓迎会やランチミーティングなどを企画し、出戻り社員が早く部署に馴染めるような雰囲気を作ることも有効です。
入社後のオンボーディングプログラムの実施
- 出戻り社員向けのカスタマイズされたオンボーディング: 一度在籍していたとはいえ、ブランクがあり、会社の状況も変化しています。一般的な新人向けオンボーディングとは別に、出戻り社員の状況に合わせたプログラムを用意します。これには、最新の社内ルール、システムの使い方、組織体制、主要な関係者の紹介などが含まれます。
- 定期的な面談とフィードバック: 入社後、定期的に上司や人事担当者との面談機会を設け、業務の進捗状況、困っていること、感じていることなどをヒアリングします。そして、適切なフィードバックを行い、早期に課題を発見し解決に繋げます。
- 目標設定と評価基準の明確化: 再入社後の具体的な目標を設定し、その達成に向けたプロセスと評価基準を明確に共有します。これにより、本人は何を目指して努力すればよいかが分かり、モチベーションを維持しやすくなります。
- 社内コミュニケーションの促進: 社内イベントへの参加を促したり、部署を超えた交流の機会を提供したりすることで、出戻り社員がより早く社内のネットワークを再構築できるよう支援します。
これらの対策を講じることで、出戻り社員が抱える不安を軽減し、スムーズな再適応を促すことができます。企業側の積極的な関与とサポートが、彼らの定着と活躍に不可欠です。
出戻り社員を温かく迎える職場環境とオンボーディングの重要性
出戻り社員が再び組織の一員としてスムーズに溶け込み、持てる力を最大限に発揮するためには、彼らを温かく迎え入れる職場環境の醸成と、効果的なオンボーディングプロセスが極めて重要です。これは単なる手続きではなく、彼らの再出発を成功に導くための投資と言えるでしょう。

「おかえりなさい」の気持ちを伝える雰囲気づくり
- 経営層や上司からの歓迎メッセージ: 経営層や直属の上司から、歓迎の意を示す言葉やメッセージを伝えることは、出戻り社員にとって大きな励みになります。「再び一緒に働けることを楽しみにしている」というポジティブな姿勢を示すことが大切です。
- 同僚からの自然な受け入れ: 周囲の社員が、変に詮索したり、腫れ物に触るような態度を取ったりするのではなく、自然体で接することが重要です。以前の関係性があった場合はそれを活かしつつ、新しいメンバーとして改めてコミュニケーションを取る姿勢が求められます。
- 歓迎の機会の設定: ささやかな歓迎会やランチミーティングなど、かしこまらずに話せる場を設けることで、打ち解けるきっかけを作ることができます。これにより、業務以外の面でもコミュニケーションが取りやすくなります。
- 社内イントラやメールでの紹介: 可能であれば、社内イントラネットや部署内のメールなどで、出戻り社員の簡単な紹介と歓迎のメッセージを発信することも、受け入れムードを高めるのに役立ちます。
出戻り社員に特化したオンボーディングプログラム
- 現状把握と情報アップデート:
- 会社の最新情報: 組織図、主要メンバー、事業戦略、新しいルールやポリシーなど、以前の在籍時から変更があった点を網羅的に説明します。
- システム・ツールの再研修: 使用するITシステムやツールが変わっている場合は、改めて研修の機会を設けます。
- 人間関係の再構築サポート: 主要な関係者を紹介し、コミュニケーションのきっかけを作ります。
- 期待役割の再確認と目標設定:
- 明確なミッション: 出戻り社員に期待する役割や業務範囲、責任を明確に伝えます。
- 短期・中期目標の設定: 入社後の具体的な目標を共に設定し、達成に向けた道筋を示します。
- メンターや相談役の存在:
- 気軽に相談できる相手: 業務上の疑問点や、人間関係の悩みなどを気軽に相談できるメンターや先輩社員をアサインします。これにより、孤独感を軽減し、早期の適応を支援します。
- 定期的なフォローアップ面談:
- 進捗確認と課題共有: 入社後1週間、1ヶ月、3ヶ月など、定期的に面談を行い、業務の進捗や困っていること、感じていることなどをヒアリングします。
- フィードバックと軌道修正: 必要に応じてフィードバックを行い、目標達成に向けての軌道修正をサポートします。
温かい職場環境と、出戻り社員の状況に合わせた丁寧なオンボーディングは、彼らが「またここで頑張ろう」という意欲を高め、早期に戦力化し、長期的に定着するための土台となります。企業側のきめ細やかな配慮が、双方にとって良い結果を生む鍵となるのです。
出戻り社員のキャリアパスを明確に!エンゲージメント向上の秘訣
出戻り社員が再び組織に貢献し、長く活躍してもらうためには、彼らのキャリアパスを明確に示し、エンゲージメントを高める取り組みが不可欠です。一度組織を離れた経験を持つ彼らは、自身のキャリアについてより深く考えている可能性があり、将来への展望が見えないと、再び離職を考える要因になりかねません。
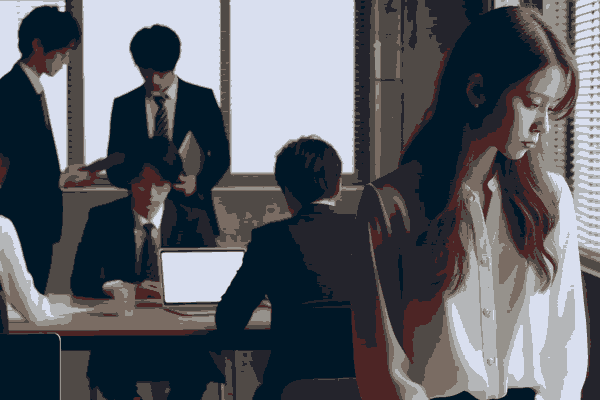
再入社後のキャリアプランの共有と目標設定
- ブランク期間の経験も踏まえたキャリア相談: 再入社面談などの機会に、ブランク期間中にどのような経験を積み、どのようなスキルを身につけたのか、そして今後どのようなキャリアを築いていきたいのかを丁寧にヒアリングします。以前の在籍時の情報だけでなく、最新の本人情報を基にキャリアプランを考えることが重要です。
- 会社が提供できるキャリアパスの提示: 本人の希望を踏まえつつ、会社としてどのようなキャリアパスを提供できるのか、具体的な選択肢(専門性を深めるコース、マネジメントコース、新しい分野への挑戦など)を提示します。その際、各パスで求められるスキルや経験、達成すべき目標なども明確に伝えます。
- 短期・中期・長期の目標設定サポート: キャリアパスに沿って、具体的な短期(例:半年後)、中期(例:1~2年後)、長期(例:3~5年後)の目標を本人と共に設定します。目標は具体的で測定可能、達成可能、関連性があり、期限付き(SMART)であることが望ましいです。
- 目標達成のための育成プランの策定: 設定した目標を達成するために必要なスキルや知識を習得するための研修プログラムの提供、OJT計画、資格取得支援など、具体的な育成プランを策定し、本人と共有します。
定期的なキャリア面談とフィードバックの実施
- 定期的な1on1ミーティング: 上司は、少なくとも月に一度など定期的に1on1ミーティングを実施し、業務の進捗状況だけでなく、キャリアに関する本人の考えや悩みを聞く機会を設けます。これにより、早期に課題を発見し、サポートすることができます。
- キャリア面談の実施: 年に1~2回程度、人事部門も交えたキャリア面談を実施し、本人のキャリアプランの進捗状況を確認し、必要に応じてプランの見直しや新たな目標設定を行います。
- 具体的なフィードバックと成長支援: 日々の業務や面談を通じて、本人の強みや改善点について具体的なフィードバックを行います。単に評価するだけでなく、どのようにすれば成長できるのか、具体的なアドバイスやサポートを提供することが重要です。
- 成功体験の共有と称賛: 目標を達成したり、成果を上げたりした際には、それをきちんと評価し、称賛することで、本人のモチベーションを高め、エンゲージメントを強化します。
エンゲージメントを高めるための施策
- 裁量権の付与と責任ある仕事の委任: 本人の能力や経験に応じて、適切な裁量権を与え、責任ある仕事を任せることで、仕事へのやりがいや主体性を引き出します。
- 社内公募制度や異動希望の尊重: 本人のキャリア志向に合わせて、社内公募制度を活用したり、異動希望を可能な範囲で尊重したりすることで、キャリアの選択肢を広げ、成長機会を提供します。
- 成果に対する正当な評価と報酬: 達成した成果に対して、公平かつ透明性の高い評価を行い、それに見合った報酬(昇給、賞与、昇進など)で応えることが、エンゲージメント維持の基本です。
- 良好な人間関係と心理的安全性の確保: チーム内でのコミュニケーションを促進し、互いに尊重し合える、心理的安全性の高い職場環境を整備することも、エンゲージメント向上に繋がります。
出戻り社員のキャリアパスを明確にし、エンゲージメントを高めることは、彼らの定着だけでなく、組織全体の活性化にも貢献します。企業は、彼らが再び自社で輝けるよう、長期的な視点でサポートしていく姿勢が求められます。
もし出戻り転職を断られたら?次のステップと心構え
勇気を出してアプローチした出戻り転職。しかし、残念ながら選考で断られてしまうケースも十分にあり得ます。その結果はショックかもしれませんが、そこで立ち止まってしまうのはもったいないことです。重要なのは、その結果をどう受け止め、次にどう活かすかです。
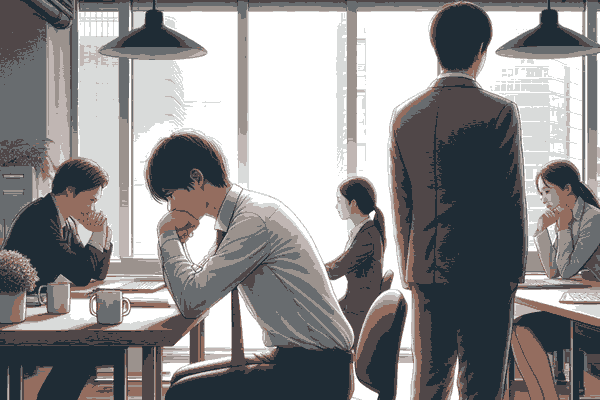
結果を冷静に受け止め、理由を分析する(可能であれば)
- 感情的にならず、まずは事実を受け入れる: 不採用の通知は誰にとっても辛いものですが、まずは感情的にならずに、その事実を冷静に受け止めましょう。自己否定に陥る必要はありません。
- 不採用理由の確認(もし可能なら): 企業によっては、不採用理由を開示してくれない場合も多いですが、もし可能であれば、具体的な理由を尋ねてみましょう。フィードバックが得られれば、今後の転職活動に活かせる貴重な情報となります。ただし、深追いは禁物です。
- 自己分析の機会と捉える: なぜ今回はご縁がなかったのか、自分なりに分析してみましょう。
- タイミングの問題: 企業の採用ニーズと自分のタイミングが合わなかっただけかもしれません。
- スキルや経験のミスマッチ: 企業が求めるスキルや経験と、自分のものが合致していなかった可能性があります。
- 企業文化との相性: 企業が求める人物像と、自分の価値観や働き方が異なっていたのかもしれません。
- 面接での準備不足: 面接での受け答えや自己PRが不十分だった可能性も考えられます。
この分析は、決して自分を責めるためではなく、次の機会に向けての改善点を見つけるために行うものです。
今回の経験を次に活かすために
- 自己分析を深める: 出戻りを考えた企業だけでなく、自分が本当に何をしたいのか、どのような環境で働きたいのか、自分の強みや弱みは何か、といった自己分析を改めて深めましょう。
- 転職市場の情報を収集する: 今回の経験で、現在の転職市場の状況や、企業がどのような人材を求めているかについて、新たな気づきがあったかもしれません。積極的に情報収集を行い、視野を広げましょう。
- スキルアップや経験を積む: もし、スキルや経験の不足が不採用の一因だと感じたなら、必要なスキルを身につけるための学習を始めたり、現在の職場で新たな経験を積む努力をしたりすることも有効です。
- 他の企業への応募も検討する: 出戻りに固執せず、他の企業にも目を向けてみましょう。今回の経験で得た自己分析や市場の知見は、他の企業への応募にも必ず役立ちます。自分に合う企業は、他にもたくさんあるはずです。
前向きな心構えを維持する
- 今回の不採用は「終わり」ではない: 一つの企業との縁がなかっただけで、あなたの価値が否定されたわけではありません。これは、より自分に合った場所を見つけるためのプロセスの一つだと捉えましょう。
- サポートを求める: 信頼できる友人、家族、あるいはキャリアアドバイザーなどに話を聞いてもらい、客観的なアドバイスをもらうのも良いでしょう。一人で抱え込まず、サポートを求めることも大切です。
- 休息も忘れずに: 転職活動は心身ともにエネルギーを使います。時には休息を取り、リフレッシュすることも忘れないでください。
出戻り転職が叶わなかったとしても、それは新たな可能性を探るチャンスでもあります。今回の経験から学びを得て、前向きに次のステップに進んでいきましょう。
出戻り社員が定着する組織文化とは?社風改善のポイント
出戻り社員が再び組織に根付き、長期的に活躍するためには、個別の対策だけでなく、彼らを受け入れ、活かすことができる組織文化、つまり社風そのものが重要になります。風通しが良く、多様性を受け入れる文化は、出戻り社員だけでなく、全ての社員にとって働きやすい環境と言えるでしょう。
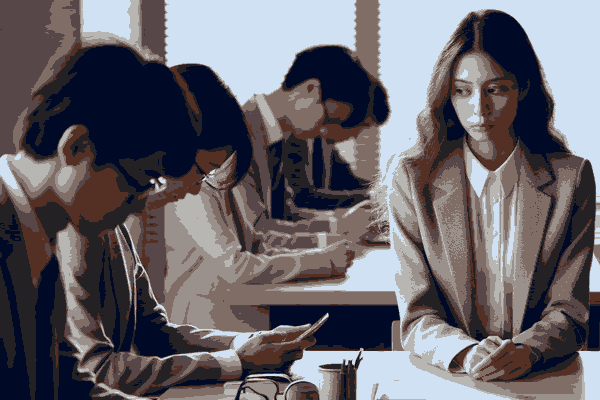
オープンで透明性の高いコミュニケーション
- 情報共有の促進: 経営状況、事業戦略、組織変更など、企業に関する重要な情報は、役職や立場に関わらず、社員にオープンに共有される文化が大切です。情報がクローズドな環境では、出戻り社員は疎外感を抱きやすくなります。
- 意見を言いやすい雰囲気: 社員が役職や年齢に関わらず、自由に意見や提案を発言できる心理的安全性の高い環境を醸成します。出戻り社員が持つ外部の視点や新しいアイデアは、組織にとって貴重な財産となり得ます。
- 双方向のフィードバック文化: 上司から部下へだけでなく、部下から上司へ、あるいは同僚同士で建設的なフィードバックをオープンに行える文化を育てます。これにより、誤解を防ぎ、相互理解を深めることができます。
変化への柔軟性と受容性
- 新しいやり方や価値観の尊重: 過去の成功体験に固執せず、新しい技術、市場の変化、多様な働き方などを積極的に取り入れようとする柔軟な姿勢が求められます。出戻り社員が持ち込む新しい視点やスキルを歓迎し、活かそうとする文化が重要です。
- 失敗を許容し、学びの機会と捉える風土: 新しい挑戦には失敗がつきものです。失敗を過度に恐れたり、個人を攻撃したりするのではなく、失敗から学び、次に活かそうとする文化は、社員が安心してチャレンジできる環境を作ります。これは、出戻り社員が新しい環境に再適応する過程でも重要です。
- 多様なバックグラウンドを持つ人材の受容: 年齢、性別、国籍、職務経歴など、多様なバックグラウンドを持つ人材を受け入れ、それぞれの個性を尊重し活かすダイバーシティ&インクルージョンの考え方を推進します。出戻り社員も、その多様性の一翼を担う存在として認識されます。
再チャレンジを応援し、成長を支援する文化
- 学び続ける姿勢の奨励: 研修制度の充実、資格取得支援、社内勉強会の開催などを通じて、社員が継続的に学び、成長できる機会を提供します。出戻り社員がブランクを埋め、最新の知識やスキルを習得することを支援します。
- キャリアパスの多様性と柔軟性: 社員一人ひとりのキャリア志向に合わせた多様なキャリアパスを用意し、社内公募や異動希望などを通じて、キャリアチェンジやキャリアアップの機会を提供します。出戻り社員に対しても、過去の経験と将来の希望を踏まえたキャリア形成を支援します。
- 公正な評価と機会の提供: 出戻り社員であることを理由に不当な扱いをしたり、昇進や重要なプロジェクトへの参加機会を制限したりすることなく、実績や能力に基づいて公正に評価し、機会を提供します。
このような組織文化を醸成することは、一朝一夕にできることではありません。経営層の強いコミットメントのもと、全社員が意識的に取り組んでいく必要があります。しかし、出戻り社員が定着し活躍できる組織文化は、結果として全ての社員にとって働きがいのある、魅力的な職場環境に繋がるはずです。
再雇用後のミスマッチを防ぐためのコミュニケーション術
出戻り社員の再雇用が成功するかどうかは、入社後のコミュニケーションの質に大きく左右されます。企業側と出戻り社員双方が、意識的に良好なコミュニケーションを築く努力をすることで、期待のズレや誤解を防ぎ、スムーズな再適応と早期の戦力化を実現できます。
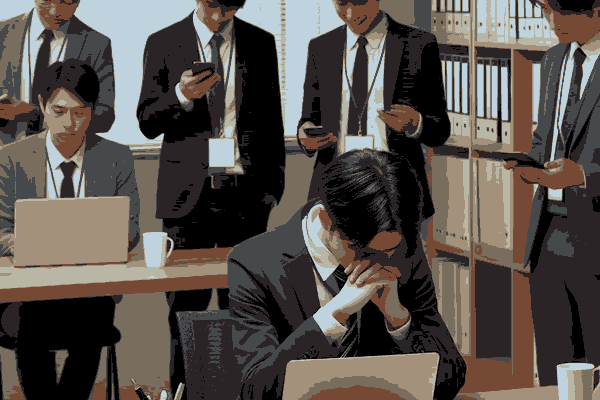
企業側(上司・同僚)が心がけるべきこと
- 定期的な1on1ミーティングの実施:
- 目的: 業務の進捗確認だけでなく、出戻り社員が抱えている不安や課題、人間関係の悩みなどを早期に把握し、サポートするため。
- 頻度: 入社初期は週に1回、その後は月に1~2回など、状況に応じて調整。
- 内容: 「困っていることはないか」「新しい環境に慣れたか」「期待している役割と現状にギャップはないか」など、オープンな質問で本音を引き出す。
- 期待役割の明確な伝達と共有:
- 曖昧さの排除: 「よしなにやってほしい」といった曖昧な指示ではなく、具体的な業務内容、目標、責任範囲、評価基準を明確に伝えます。
- 認識のすり合わせ: 伝えた内容について、出戻り社員が正しく理解しているかを確認し、必要であれば再度説明します。
- フィードバックの質とタイミング:
- 具体的かつ建設的: 良かった点、改善すべき点を具体的に伝え、どうすればより良くなるかという建設的なアドバイスを添えます。
- タイムリーな実施: 問題が大きくなる前や、記憶が新しいうちにフィードバックを行うことが効果的です。
- チームメンバーへの情報共有と協力依頼:
- 出戻り社員の強みや経験の共有: チームメンバーに出戻り社員の強みやこれまでの経験を伝え、どのように連携すればチームの成果に繋がるかを共有します。
- サポート体制の明確化: 誰がどのようなサポートをするのかを明確にし、チーム全体で受け入れる雰囲気を作ります。
- 「昔の話」と「今の話」のバランス:
- 過去の経験への敬意: 出戻り社員が持つ過去の経験や知識は貴重な財産ですが、それに固執しすぎないよう促します。
- 現在の状況への適応支援: 新しいルールやプロセス、人間関係への適応をサポートし、「今はこうなっている」という情報を積極的に提供します。
出戻り社員自身が心がけるべきこと
- 謙虚な姿勢と学ぶ意欲:
- 「教えてもらう」スタンス: たとえ以前の知識や経験があっても、新しい環境では「新人」という意識を持ち、謙虚に教えを請う姿勢が大切です。
- 変化への適応: 過去のやり方に固執せず、新しいルールや進め方を積極的に学び、取り入れようとする柔軟性が求められます。
- 積極的な質問と報告・連絡・相談(報連相):
- 不明点の早期解消: 少しでも分からないことや不安なことがあれば、遠慮せずに質問し、早めに解消します。
- 状況の共有: 業務の進捗状況や問題点などを、上司や関係者にこまめに報告・連絡・相談することで、誤解やトラブルを未然に防ぎます。
- 周囲への感謝と配慮:
- サポートへの感謝: 教えてもらったり、助けてもらったりした際には、感謝の気持ちをきちんと伝えることが良好な人間関係の基本です。
- 既存メンバーへの配慮: 自分がいなかった間に築かれたチームワークや業務フローを尊重し、一方的な意見や批判は控えるように心がけます。
- 自己開示とコミュニケーションの努力:
- 自分の状況や考えを伝える: 自分が今どのような状況で、何に困っていて、どうしたいのかを適切に伝えることで、周囲の理解と協力を得やすくなります。
- ランチや懇親会への参加: 業務外のコミュニケーションの機会にも積極的に参加し、打ち解ける努力をすることも有効です。
- 期待値のすり合わせ:
- 自身の希望や懸念を伝える: 会社から期待される役割だけでなく、自分がどのような働き方をしたいか、どのような点に不安を感じているかを率直に伝え、期待値のギャップを埋める努力をします。
再雇用後のミスマッチは、コミュニケーション不足から生じることがほとんどです。企業側と出戻り社員双方が、相手の立場を理解し、オープンで誠実なコミュニケーションを心がけることが、良好な関係を築き、共に成長していくための鍵となります。
まとめ:出戻り社員がまた辞める連鎖を断ち切るために
「出戻り社員がまた辞める」という問題は、企業と社員双方にとって大きな課題です。本記事では、その背景にある理由、例えば以前の退職理由の未解決、期待と現実のギャップ、新しい環境への適応の難しさ、そして時には「嫌われる」と感じてしまうような人間関係のもつれなどを掘り下げてきました。
しかし、出戻り社員が再び輝ける道は必ずあります。そのためには、企業側が再入社前の丁寧な情報共有と期待値調整、入社後の手厚いオンボーディング、そして明確なキャリアパスの提示とエンゲージメント向上策を講じることが不可欠です。温かく迎え入れる職場環境の醸成や、オープンなコミュニケーションを基本とした組織文化の改善も、彼らが定着し活躍するための重要な土台となります。
一方、出戻り社員自身も、謙虚な姿勢で新しい環境を学び、積極的にコミュニケーションを取り、周囲への感謝を忘れないことが求められます。過去の経験は活かしつつも、変化を受け入れる柔軟性が大切です。
出戻り社員が「また辞める」のではなく、「再び貢献してくれる貴重な人材」となるためには、企業と社員双方が互いを理解し、歩み寄る努力が何よりも重要です。この記事が、その一助となれば幸いです。